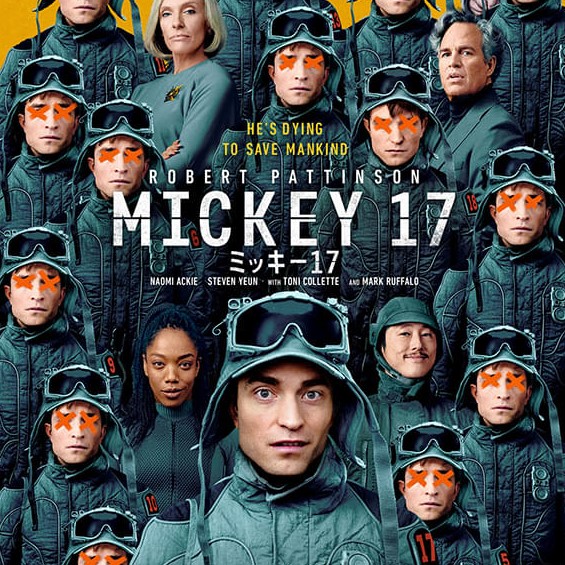映画「ヴィレッジ」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
ここ最近の日本映画では、どこかホッとするような人情噺が注目されがちだが、本作は真逆をいく。全編に漂う怪しげな空気と、田舎の集落ならではの閉塞感がダブルで襲ってくるため、観終わったあとは妙に肩がこってしまう人もいるだろう。それでも、横浜流星が演じる主人公の苦悩に共感したり、予想のつかない展開にワクワクしたりと、観客の心を鷲づかみにする力があるのが「ヴィレッジ」の魅力である。監督は「新聞記者」や「余命10年」など数々の社会派作品を手がけた藤井道人。重厚なテーマを扱うことで有名な人物だけに、今回もどこかでガツンとやられると覚悟して臨んだほうがいいかもしれない。
とはいえ、肩肘張るばかりでなく、時折ニヤリとさせられる場面もあるのでご安心を。閉ざされた村で行われる謎めいた行事や、ゴミ処理施設をめぐる不穏な動きが絡み合い、「こんな世界が本当にあるのか?」と疑いたくなるような展開の連続である。気軽な田舎巡りを想像していると痛い目を見るが、そのギャップこそが最大の見どころでもある。
映画「ヴィレッジ」の個人的評価
評価: ★★★☆☆
映画「ヴィレッジ」の感想・レビュー(ネタバレあり)
「ヴィレッジ」は、そのタイトルからして日本のどこかの鄙びた村を舞台にしたほのぼの系かと思いきや、実際は土着の風習と闇深い人間模様が交錯する濃密なドラマである。主役を担うのは横浜流星が演じる片山優という青年で、彼は村で“罪人の息子”として白い目で見られ続け、まるで閉じ込められた小鳥のような息苦しさを抱えている。
そんな優が暮らす霞門村(かもんむら)は、自然こそ美しく、伝統文化としての薪能まで根付いている場所だが、ゴミ処理施設の設立によって村は大きく様変わりしている。表向きは補助金を得て活性化を狙う村長たちの“明るい未来”構想があるものの、実際には違法な廃棄物処理や不法投棄がはびこり、一部の権力者やヤクザが好き放題しているのが現状だ。
この作品で特筆すべきは、村人たちの何気ない会話や視線からにじみ出る“排他性”である。どうやら優の父親が過去に殺人と放火を犯したらしく、その汚名を理由に、優までが村全体から疎まれているのだ。表面上は誰もが穏やかに暮らしているように見えるが、心の底では「厄介者は外へ出ていけ」という感情を誰もが抱えている。村の若きリーダー候補である透などは、優をいじめの標的にして憂さ晴らしをしているようにも映る。
とはいえ、そんな優に救いの手を差し伸べる存在がいる。幼なじみの美咲である。東京から帰郷してきた彼女は、ゴミ処理施設の広報として村のイメージアップを図ろうと奮闘しているのだが、優がかつて能教室に通うほど好きだった薪能の話題をうれしそうに振り、彼の閉ざされた心をそっとほぐしていく。横浜流星と黒木華が醸し出す微妙な距離感は、観る者に「もしかしてここからラブストーリーが展開するのでは?」と期待を抱かせるが、そこは本作らしいひと筋縄ではいかない流れが用意されている。
村の巨大ゴミ処理施設の業務は過酷だ。身体的にも精神的にもつらい仕事をしている人々のなかには、借金や犯罪歴など、何らかの“後ろ暗い事情”を抱えている者が少なくない。夜な夜なヤクザに脅され、不法投棄を黙認せざるを得ない優もその一人だ。「見て見ぬふりをするしかないのか」「父親の一件があるから、自分にはどうせ逃げ場がないんだ」と諦めモードに浸る姿は、暗いトンネルに迷い込んだ人間の絶望を痛感させる。
ところが、幼なじみである美咲の存在が優の状況を揺り動かす。美咲は都会で心を消耗しながらも、どこか強い意志を持っているように見える。むしろ「こういう泥臭い田舎だからこそ、自分の力で何かを変えられるはずだ」と信じている節があるのだ。実際に、子ども向けの施設見学やテレビ取材の準備などを推進し、優を前向きな仕事へと誘う場面もある。
しかし、悲しいかな、そこは閉鎖的な村社会。透をはじめとする村の有力者側からすると「勝手なことをするな」「余計な波風を立てるな」という圧力が絶え間なく降りかかる。さらに、美咲にとって優は“単なる幼なじみ”の域を超えた存在になっていくので、透の嫉妬を買うのは時間の問題でもあった。ある夜、透が美咲に手を出そうとし、優が割って入るが、結果的に激しい争いに発展してしまうのは、ある意味で必然だったのかもしれない。
それまでじわじわと積み上がってきた因縁が、一気に噴き出すような乱闘の末、透は命を落としてしまう。このシーンは非常にショッキングだ。日頃から暴力的で高圧的だった男にとうとう天罰が下ったともいえるが、刺したのは美咲であり、死体を隠すのに加担したのは優。そう、ここで一線を越えてしまうのだ。もはや後戻りできない状態に踏み込んでしまったふたりを観ていると、「村の閉鎖性が生んだ悲劇」というだけでは片づけられない切なさがこみ上げてくる。
この事件を機に、優は一躍“施設の顔”として祭り上げられるものの、幸福の絶頂にいるわけではない。上層部は村のイメージを守るために情報をコントロールし、優を使ってテレビ番組などで「この村は再生した」と印象づけようとしている。テレビ画面に笑顔で映る優の姿は、一見すると立ち直った青年のサクセスストーリーのようだが、その裏で抱える罪悪感と恐怖はすさまじい。しかも不法投棄や闇の金が絡む裏事情をまるごと隠蔽している以上、いつバレるかもわからない爆弾を抱えているような状態だ。
さらに村長を務める大橋修作は、利権を守ることに執念を燃やしている。彼はテレビカメラの前では穏やかな父親像を演じ、実際に仲間からも「面倒見のいい人」という評判を得ているが、蓋を開ければ違法行為にも平然と手を染めている。いや、もしかしたら表舞台の優しげな顔すら計算づくかもしれない。村長の弟である光吉が何度も優に「もうやめておけ」と説得するような態度を見せるのだが、残念ながら時すでに遅し。優はどんどん深みにはまり、父親と同じような火の粉を振り払えなくなっていく。
クライマックスでは、透の失踪が捜査線に浮上し、ゴミ処理施設で死体が見つかる恐れが高まっていく。美咲は取り返しのつかない事態になったことを痛感しながらも、どうしようもできない。優は村長と対峙し、「全部を白日の下にさらすしかない」と覚悟を決めかけるが、そこで村長の口から明かされる過去の真相が、優をさらなる絶望に突き落とす。
実は、優の父親が起こしたとされる事件も、村の裏事情によって歪められていた可能性がある。それをネタに、村長は「このまま黙っていれば、父親の名誉回復もしてやれるかもしれない」などと、優の心をかき乱す。何かに縋りたい優は、一瞬、村長の甘言に乗りかけるが、最終的には激怒のあまり取り返しのつかない行動へ踏み込む。すべてを知ったうえで、自分が苦しめられた元凶を断ち切ろうとするのだ。皮肉にも、それは父親と同じ“放火”という形をとる。
ラストシーンで燃え盛る大橋家の屋敷と、薪能の「邯鄲」が重なって響き渡るあたりは、本作の象徴と言えよう。夢のように手にしかけた幸せも、現実をねじ曲げて手に入れた繁栄も、一瞬で灰になる。その無常観こそが「ヴィレッジ」に宿る大きなテーマであり、観終わったあとに「人生の儚さとは何なのか」と問いかけられる気分になる。
もっとも、この作品が単なる陰鬱な悲劇で終わらないのは、美咲の弟・恵一が最後に村を出るシーンの存在が大きい。彼は障がいを抱えながらも自分の正義を貫き、悪事を見逃さず、最後まで真実を追い求めようとしていた人物だ。確かに彼が村を出たところで何が変わるわけでもないかもしれないが、狭苦しい集落の外へと自ら踏み出す姿は、後味の悪さだらけの物語に一筋の光を差し込む。それは「やり直しはできる」「どこかに未来がある」という希望を示しているように思えてならない。
そう考えると、本作はただ重苦しいだけの人間ドラマではなく、歪んだコミュニティのなかで、人はどう抗い、どう自分を解放していくのかを突きつける作品とも言える。優は最後に火を放ったことで取り返しがつかない罪に手を染めてしまったが、同時に「そこから新たに歩み出すチャンスは残っているのでは」と想像させられるのだ。たとえ地獄のような村であっても、そこに暮らす人間が絶望の果てに下す選択は多種多様。美咲が覚悟を決めて透を刺したのも、死を望んだわけではなく「もう限界だ」という人間の悲痛な叫びが形を変えただけであろう。
こうして振り返ると、本作の魅力は“村の闇”と“人間の闇”がシンクロしている点にある。ゴミ処理施設の汚濁は、まるで人々の罪や汚点を見えないところへ押し込めようとする姿そのもの。能の演目「邯鄲」は、現実と幻想の境界があやふやになる物語だが、この村そのものが何かの夢のようにも思える。儚く消えてしまうからこそ美しく見える瞬間と、どうしようもないほど醜い現実が同時に存在するのが「ヴィレッジ」の恐ろしさである。
監督の藤井道人は「新聞記者」などの社会派作品で培った鋭い視点を用いながら、人々が抱える心の闇やコミュニティの負の連鎖を生々しく掘り下げたといえる。そして主演の横浜流星も、爽やかなイメージを覆すかのような暗く荒んだ表情を見事に演じ切っているのが印象的だ。黒木華の持つ優しさと痛々しさが入り混じった空気感も絶妙で、作品に深みを与えている。
そういう意味で、この「ヴィレッジ」は、観る人を選ぶかもしれない。一種の泥臭さや救いのなさを伴うので、「スカッとしたい」「何も考えずに楽しみたい」というタイプの人には厳しいかもしれない。だが、ただ重苦しいだけでなく、そこに秘められた一瞬の“美しさ”や“絆の光”を見出せるならば、きっと忘れられない作品になるだろう。たとえラストの展開が絶望的に見えても、そこに至るまでの人物たちの行動は一本芯が通っている。
筆者としては、村という密閉空間で暴かれる人の本性こそが最大の見どころだと思う。能や薪能といった文化的要素がときおり神秘的な幻想を生み出すが、その幻想が崩れたときに人は何をするのか、どう変わってしまうのかを描ききった点が素晴らしい。まさしく現代の日本社会にも通じる、一種の縮図を見せられたようで、なんとも背筋がゾクッとする。
とはいえ暗さだけで終わらず、ちょっと笑いたくなるような人間関係の機微も潜んでいるので、あまり身構えすぎずに鑑賞してほしい。観終わったあとに気づく細かい伏線も多く、「ああ、あのシーンで言っていたことはこういうことだったのか」と膝を打つ瞬間があるはずだ。こうした発見の積み重ねもまた「ヴィレッジ」の醍醐味である。
誰もが胸の内に隠している秘密や葛藤が、村という名の大きな箱に閉じ込められた結果、一気に噴き出してしまう。その光景を目の当たりにしながら、「自分だったらどう行動するのか」と考えさせられるのも興味深い。人間誰しも、追いつめられたときはわけのわからない行動に出る可能性があるのだから、他人事ではいられない。
「美しい自然と神秘的な能の舞台に仕掛けられた暗部と悲劇がインパクトを残すサスペンス映画」と言えるだろう。とりわけ、横浜流星と黒木華の演技、そして能の迫力ある音楽や舞の演出に心を奪われる。クライマックスの燃える屋敷と舞台の映像は、悪夢のように焼き付くはずだ。この先、誰かと議論する機会があれば「村を守るとは何か?」というテーマをぜひ持ち出してみてほしい。そこには、きっと自分たちの社会や人間関係に通じる問題が隠れているはずである。
映画「ヴィレッジ」はこんな人にオススメ!
本作は、田舎の美しい風景に憧れつつも「実はそう単純じゃないよな」とうすうす感じている人にとって、刺さる要素が満載である。また、社会派ドラマやサスペンス作品を好み、物語の深い部分をあれこれ考察したいタイプにはたまらない。村社会の排他性や、ゴミ処理施設をめぐる汚れた利権、それに縛られる人間たちの運命が重くのしかかるため、いわゆるエンタメ感覚でワイワイ楽しむ作品とは言いがたい。むしろ、どっぷりと人間の暗部を味わいたい観客こそが、最後まで飽きずに見通せるのではないだろうか。
一方で、能や薪能といった日本古来の芸術に興味がある人にもおすすめしたい。劇中には謎めいた薪能のシーンが出てきて、現実世界との境界が溶け合うような不思議な感覚をもたらす。これまで能に縁がなかったとしても、映画を通じて「なんだか面白そうだな」と思えてくるかもしれない。作品のなかで語られる演目「邯鄲」の解説シーンなども印象的で、物語とのリンクを知るほどに奥深さを感じるだろう。
さらに、横浜流星のイメージに“爽やか”や“王子様”のようなものを抱いている人は、良い意味で衝撃を受けるかもしれない。本作では暗闇に沈む青年の姿を体当たりで演じており、これまで抱いていた彼の印象がガラリと変わるはずだ。そのギャップに魅力を感じるなら、なおさら楽しめると思う。
重苦しい題材ゆえ、見る前はちょっと気が滅入るかもしれないが、ダークなテーマでも骨太な作品が好きな人や、日本映画の新たな可能性を探している人にはうってつけである。ひとたび鑑賞すれば、人間関係のえぐり方や精神的に追いつめられていく様子が、妙にリアルに迫ってきて、心がザワザワする感覚がやみつきになってしまうかもしれない。
まとめ
「ヴィレッジ」は、一見すると美しい自然と伝統文化に彩られた村の物語でありながら、その奥底には人間の欲望や葛藤がぎっしり詰まっている作品である。
横浜流星が演じる主人公・優をはじめ、表向きの顔と裏の顔を使い分ける登場人物たちのやり取りは、どこか現実社会に通じるものを感じさせる。暗澹たる事件が次々と起こる一方で、能の舞台がもたらす幻想的な雰囲気や、美咲と優の儚い絆など、わずかな救いも散りばめられているのが印象的だ。
この作品を観終わると、誰もが少なからず「もし自分があの村にいたらどうするだろう?」と想像してしまうだろう。そうした問いを抱えつつ、最後に訪れる悲劇と火の象徴的なイメージは、観客の記憶に強く焼き付く。もしダークな物語が苦手でなければ、きっと得難い衝撃と深い余韻を体験できるはずだ。閉ざされた世界の恐怖と、そこに渦巻く人間の思惑をダイレクトに味わえる一本である。