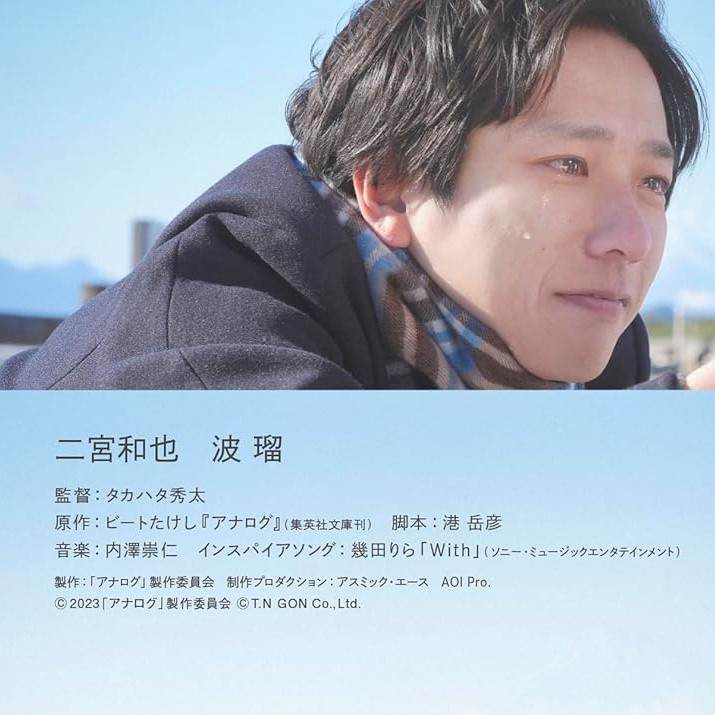映画「正欲」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
まず最初に言っておくが、この作品は相当に刺激的である。観終わったあとに強烈な余韻が残り、頭の片隅でずっと何かがざわつく感覚を味わった。稲垣吾郎の演技には独特の切れ味があり、一見穏やかそうに見えるが、その内側から吹き出す怒りや葛藤がリアルに伝わってきたのだ。新垣結衣の清涼感ある存在感も加わり、物語に深みと柔らかさを同時に与えている。さらに、社会的なテーマを扱いながらも、登場人物たちの“ここだけの話”を覗き見するようなスリルがある点も見逃せない。
日常と地続きながら、一歩踏み込むと未知の感情が広がる世界――そんな世界観に引きずり込まれたのは自分だけではないはずだ。気軽に観始めた人ほど、後半でその奥深さに驚かされるだろう。ここから先は、作品の核心に触れる内容を含むため、未視聴の方は十分注意して読み進めてほしい。
映画「正欲」の個人的評価
評価: ★★★☆☆
映画「正欲」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本作を一言で表すなら、人間の“普通”が実はどれほど多様かを思い知らされる物語である。社会生活を送るうえで当たり前とされている価値観や常識が、一歩外に踏み出すとまるで異国の文化のように感じられる――そんな感覚を突きつけるのがこの映画の本質だと思う。
稲垣吾郎演じる検事・寺井は、一見すると「真面目」「常識人」「堅物」というイメージがぴったりの人物である。息子が不登校になり、妻とのすれ違いも増える中で、いわゆる“正しい父親”像に縛られているかのように見える。彼が問題に直面するたび「それは普通じゃないだろう」とバッサリ切ってしまう姿には、観ているこちらも「いやいや、それだけが正解じゃないぞ」と言いたくなる。しかしながら、彼の態度はある意味で“社会に適応した結果”とも言える。職務上、犯罪や不正を排除しなければならない立場にいて、法のもとに線を引く必要がある。だからこそ「普通か否か」という基準を明確に設け、そこから外れたものは危険だと思ってしまうのだろう。
一方、新垣結衣が演じる桐生夏月は、広島のショッピングモールの寝具売り場で契約社員として働きながら実家暮らしをしている。彼女は水という存在に対して特殊な感覚を持っている。具体的に言うならば、それは身体を貫くような強烈な興奮と安堵、いわば“性”的な領域に踏み込むほどの執着だ。しかし周囲の人々からすれば「なんで水が好きなんだ?」とまったく理解されず、彼女自身も「こんな私を人は受け入れるはずがない」と思い詰める。世の中には「特殊嗜好」を肯定的に受け止める土壌が育ちつつあるとはいえ、こと水フェチのように理解されにくい領域ともなると、まだまだ壁は高い。彼女が抱える孤独感は相当なものだが、その表情はどこか澄んでいて、こちらが勝手に「救われてほしい」と祈ってしまうほど魅力的に映る。
そんな夏月の前に、中学時代の同級生・佐々木佳道がふらりと再会する。佐々木もまた水フェチであり、“誰にも言えない秘密”を抱えて生きてきた。劇中で二人が同じ“異質”を共有していると気づく瞬間は、観る側に不思議な感動をもたらす。二人にとって、それは救済であり、共犯のようでもあり、ある種の“契約”めいた誓いに感じられるからだ。「分かってもらえない」と思い続けていた者同士が出会い、「ここに仲間がいたのか」と自覚する瞬間の尊さは計り知れない。だが同時に、それが周囲から理解されるかどうかはまた別問題である。少なくとも寺井のような“普通”至上主義の人間にとっては、到底受け入れがたい感覚だろう。
本作にはさらに、大学のダンスサークルに所属する諸橋大也や学園祭実行委員の神戸八重子という若者たちも登場する。大也は準ミスターに選ばれるほどのイケメンだが、その外見に似合わず内面には重たい孤独を抱えている。周囲は勝手に「モテ男だろう」「自信満々だろう」と思い込むが、当の本人は自分の秘めた嗜好を誰にも言えないまま、表面的な“人気者キャラ”を演じているにすぎない。神戸は男性恐怖症を抱えながらも大也をダンスイベントに誘い、心を通わせていく。けれど一足飛びに“わかり合う”わけではなく、彼らなりの遠回りや衝突を経て少しずつ互いに歩み寄っていく姿が描かれる。
この映画が巧みなのは、寺井を含めたすべての登場人物がそれぞれの“正義”や“倫理観”を持っており、それらが真っ向から対立するシーンをじっくりと見せる点だと思う。誰かが圧倒的に悪いわけでもなく、極端に善人というわけでもない。ただ「普通であることに安堵を得る人」と、「普通とされる枠組みに苦しんできた人」がぶつかり合う構図があるだけなのだ。その摩擦の火花が、家族崩壊や逮捕といった事件として表面化していく展開は、観ていて息が詰まるほどの緊張感がある。
また、水フェチというテーマを取り上げた大胆さは本作の肝である。世の中にはさまざまな性のあり方があるが、「水に惹かれる」というフェチはまだまだメディアでもほとんど取り上げられないマイナーな領域だ。だからこそ、夏月や佐々木、大也の告白シーンには強烈なインパクトがある。だがこの作品の面白いところは、それを単に“異端”として描くだけで終わらない点にある。「水が好き」な人々の視線を通して、逆に“普通”を疑問視させる力があるのだ。水に対して特別な感覚を抱かない人も、実はどこかで“他人からは変に思われそうだから黙っている”ものを抱えているのではないか――と問いかけるようにも感じる。
寺井が担当する事件に絡んで、小児性愛者という危険な存在も描かれる。ここで作品は単なる「マイノリティの苦悩」では片付けられない領域に踏み込む。「受け入れられない性癖」と「人を傷つける犯罪」はまったく別物である、という線引きが必要になってくるのだ。寺井の立場としては、小児性愛を伴う加害の可能性を厳しく糾弾せねばならない一方で、「ただ水が好きなだけ」と必死に訴える佐々木たちまで一括りにするのは乱暴すぎる。しかし、“普通じゃないもの”を十把一絡げに排除しようとする社会の圧力は、そこで簡単には緩まない。だからこそ寺井の硬直した姿勢と夏月たちの苦悩が対立し、その間にある“溝”が浮かび上がる。
クライマックスでは寺井と夏月が直接対峙し、彼女が決定的な言葉を残す。周囲の環境を変えようともがいた末、夏月がたどり着く答えは決して“普通に順応する”ことではない。むしろ「自分は自分として生きる」「たとえ理解されなくても、私はいなくならない」という強い宣言だ。あれほど孤独そうだった彼女が、ほんの少し笑みを浮かべながらその言葉を発するシーンは、本作一番の見どころでもある。「水フェチ」という特異なテーマで始まったはずが、最後には誰もが共感できる“自分自身を受け入れる覚悟”へと結びついていくのだ。
しかし、ここで「じゃあ結局みんなハッピーエンドなのか?」と言えば、そう単純ではない。寺井が家庭で失ったもの、佐々木が法の裁きの前に突きつけられる重み、神戸と大也が越えねばならない心の壁――どれも簡単には解消できない根の深い問題である。だからこそラストシーンにはある種の苦味が残り、同時に「それでも生きていくんだ」という力強さが感じられる。これが“多様性”や“受容”を扱う物語にありがちなキレイごとで終わらない理由だろう。
稲垣吾郎は寺井というキャラクターを、いわゆる“一般的な中年男性”として違和感なく演じ切る。普段はスマートで寡黙なイメージの強い稲垣だが、本作では苛立ちや苦悩をむき出しにする場面も多く、そこがかえってリアリティを増していると感じた。新垣結衣は透明感のある佇まいで、夏月の閉ざされた世界を柔らかく、しかし確実に表現している。彼女が悲しみや不安を抱えつつも、小さな希望を見いだそうとする演技は抜群だ。磯村勇斗、佐藤寛太、東野絢香ら若手陣のエネルギッシュな存在感も見逃せない。キャスト全員が自分の立ち位置に真摯に向き合っているからこそ、この作品は説得力を持つのだと思う。
映像面も印象的だ。特に水をモチーフにしたカットは、美しさと背徳感が同居している。監督・岸善幸の冷静な視線が、過度な演出に走ることなく“水”という存在を神秘的に、そして危うい存在として映し出しているのが素晴らしい。音楽の使い方も控えめで、むしろ静けさが際立つ場面が多い。登場人物たちの呼吸や心の声が聞こえてくるような演出は、画面に釘付けになってしまうほど緊迫感がある。
物語は、ダイバーシティフェスや家族の対立、事件捜査など複数のラインが平行して進んでいくが、それらが最終的に交わる形になる構成も見事である。人生は往々にして自分だけでは完結しないし、他者との思わぬ接点が新たな道を切り開くこともある。大げさかもしれないが、「誰かとの出会いが自分を救ってくれるかもしれない」と感じさせるメッセージが、本作には潜んでいる。
長い尺の中で語られる問題提起は決して軽いものではないが、どこか人間味があって温かい。それは、多様性を描きながらも「人は他者を完全には理解できない」という冷徹な事実を直視しているからではないかと思う。互いに理解し合うのは容易ではないし、時には激しくぶつかるかもしれない。けれど、そこから目を背けずに向き合う者たちだけが、少しずつ前進していく――そんなメッセージに心を揺さぶられた。
以上のように、正欲という作品は観る人を選ぶかもしれない。それでも、この映画は“自分が知らない世界の扉”を開いてくれる貴重な体験であることは間違いない。誰の胸にも少しはあるはずの「人に言えない嗜好」や「後ろめたさ」に触れてくるからこそ、観終わったあとにドキリとしたものが残るのだ。そうした余韻が、鑑賞後の生活に微妙な変化をもたらすかもしれない。寺井のように“普通”を振りかざすことがいかに危ういか、あるいは夏月のように“ありのまま”を貫くことがいかに困難か、それを自分自身に問いかけずにはいられない。
ラストを迎えたとき、心に刺さるものがあったなら、この作品が描いた“みんな違うけど一緒に生きるしかない”現実に少しは近づけたということだろう。誰もが満たされるわけではないが、歩みを止めずに進む彼らの姿を、観客もまた見守りながら一歩を踏み出せるのではないか。まさに、人との違いにとまどいながらも共存を目指す現代社会にふさわしい映画だと感じた。
映画「正欲」はこんな人にオススメ!
まず、自分の中に隠している“どうしようもないこだわり”や“ちょっと他人に言いにくい趣味”がある人には強く勧めたい。本作は特殊な性癖を正面から扱っているので、観ていると「ああ、ここまで振り切った形もあるのか」と妙な安心感や共感を覚えるかもしれない。さらに、自分と違う価値観に触れるのが苦手な人ほど、あえて挑戦してみると新たな扉が開く可能性がある。寺井のように“普通”を頑なに信じてきた人にこそ、他者の世界観を覗き見る契機になるのではないだろうか。
また、家族関係やパートナーシップで悩んでいる人にも刺さる部分が多い。人は皆、自分が理解できないものや受け入れがたいものに直面すると、思わず排除や否定に走ってしまいがちだ。しかし、本作の登場人物たちのように、真正面から衝突することで初めて「これは単なる好き嫌いの問題で終わらないのだ」と気づくことがある。だからこそ、身近な人との関係にモヤモヤを抱えているなら、この映画を通して「相手をわかろうとする姿勢」と「わかり合えなくても否定しない在り方」の大切さを考えてみてほしい。
社会の中で孤立感を抱きがちな人、あるいは自分だけがおかしいのではないかと悩んでいる人にも手に取ってほしい一本だ。何かに悩んでいるとき、人間は誰もが“普通から外れてしまった”ような不安を抱く。本作はそんな孤独をひとりで背負わず、「他の場所にも似た思いを抱えている人がいるんだ」という気づきを与えてくれるだろう。
まとめ
正直に言うと、本作は観る人を選ぶかもしれない。特殊な性癖やマイノリティな感覚に生々しく踏み込んでいるので、苦手に感じる人もいるだろう。だが、そのぶん得られるものも大きい。自分と違う価値観を前にして心が騒ぐのは、人が他者を理解しようともがいている証拠でもある。この映画はそんな“もがき”を目をそらさずに描いているからこそ、重く刺さる場面が多いのだと思う。
登場人物同士の関係が交錯する終盤では、人間関係の綻びや絆の形が浮き彫りになり、まるで自分の生活を振り返るような錯覚に陥る。そのとき、本作で描かれる“理解し合えないことへの葛藤”や“それでも寄り添おうとする努力”が真に迫ってきて、自分自身の人生観を揺さぶってくるのだ。たとえ分かり合えなくても、まったく別の存在として尊重し合いながら一緒に生きていくしかない。本作を通じて、そんな当たり前のようで難しい真実に気づかされる人はきっと多いはずである。