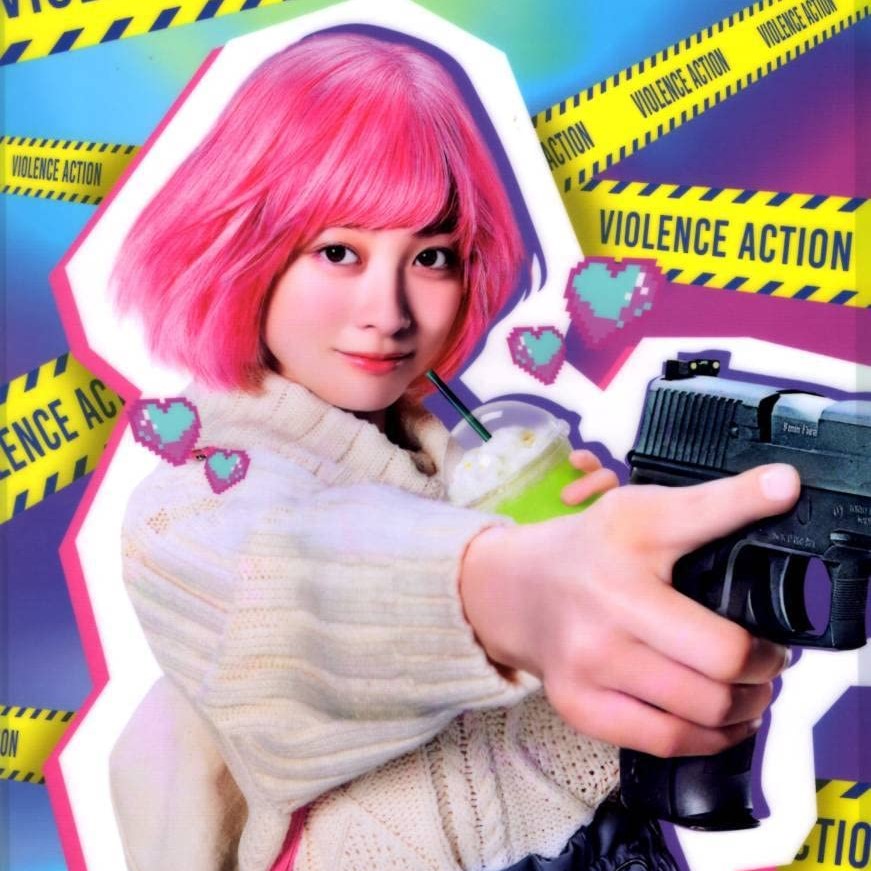映画「メタモルフォーゼの縁側」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
芦田愛菜主演の本作は、一見するとただの“のんびりハートフル”映画かと思いきや、じわじわと胸に染み込むドラマが詰め込まれている作品である。17歳の女子高生と75歳の老婦人という年齢差コンビが、BL(ボーイズラブ)という趣味を通じて心を通わせる姿は、肩の力を抜いて観ると意外な発見があるに違いない。セカセカした日常を送る者ほど、このゆったりした空気に巻き込まれて「あれ、気づいたら自分も笑ってる…?」と感じるかもしれない。実際、自分もどこかで見落としていた大切な“好き”という気持ちを思い出させられたのだ。
物語の中心にあるのは“変化”であり、登場人物それぞれの人生観のシフトがしっかり描かれている。懐かしくも新鮮な少女マンガ的ときめきを抱えながら、年齢を超えた友情がゆるやかに深まっていく。そのプロセスこそが大きな見どころであり、後半には思わず泣ける展開が待っている。さて、ここからは遠慮なくネタバレに踏み込んでいこうと思うので、覚悟して読み進めてほしい。
映画「メタモルフォーゼの縁側」の個人的評価
評価: ★★★★☆
映画「メタモルフォーゼの縁側」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本作を一言で表すなら、人生の先輩と後輩が一緒になって“好きなもの”を追いかけるロードムービー的物語である。とはいえ、車に乗って遠くへ出かけるわけではなく、行く先は近所の本屋や喫茶店、そしてコミティアと呼ばれる同人誌即売会。そこにあるのは派手な事件でも壮大な冒険でもない。ただ、ささやかな“楽しみ”を通じて、人が少しずつ自分を解放し、人生を前向きに捉えていく過程が描かれているのだ。
芦田愛菜演じる高校生・佐山うららは、学業に熱心というよりも、放課後やバイトの合間にBLマンガをこっそり読みあさっては一人で盛り上がる女の子である。学校での派手な居場所はなく、クラスのリア充女子たちとは少し距離がある。それでも孤独に沈んでいるわけではないが、どこか踏み出せない“壁”を感じている節があるのだ。その壁とは「好きなものを大っぴらに語れない息苦しさ」と言っていいだろう。
一方、75歳の市野井雪(宮本信子)は、夫に先立たれ、広い家で一人暮らしをしている。娘は遠くノルウェーで暮らしており、たまに帰ってくるものの、老人ホームなどを検討する話が持ち上がると雪はなんとなく言葉にしきれない寂しさを感じている。そんな彼女が本屋でふと手に取ったのがBLマンガで、表紙の絵が「きれいだわ」と思わず購入してしまう。そのレジ対応をしていたのが、うららだった。両者はその小さな“きっかけ”を通じて徐々に距離を縮めていく。
雪はBLマンガを初めて読みながらも、まるで乙女のようにドキドキし、その世界を純粋に楽しむ。うららはまさか自分の祖母世代とも言える女性が同じ趣味を持っているとは思いもよらず、最初は戸惑いつつもうれしさを隠せない。現代日本では、BLというジャンルは決して珍しいものではなくなったが、それでも年齢のギャップが大きい者同士で語り合うとなると、なかなかない展開である。しかし本作の面白さは、こうした“BL好き”という設定をきっかけに、年齢に縛られない心の通い合いを描いている点にある。
物語が進むと、雪とうららはカフェでおしゃべりをしたり、雪の家の縁側で一緒にカレーを食べたりするようになる。いわゆる日常風景なのだが、そこにあるのは互いを「変に気遣わない」関係性だ。家の広い縁側が持つ解放感も手伝ってか、2人とも徐々に心を裸にしていく。うららは大学受験が目の前に迫っているのに将来の目標が見つからずモヤモヤしているし、雪も体力の衰えを感じながらも「今さら夢中になっていいのか?」と少しだけ尻込みしているところがある。そんな微妙な不安をぶっちゃけられる相手ができたことで、お互いに小さく弾けるわけだ。
笑いを誘うシーンは多い。といっても爆笑するような“大騒ぎ”のコメディではなく、肩の力がふっと抜ける“おかしみ”がある。やがて、うららは「マンガを描いてみたい」という思いに突き動かされる。読んでいるだけではなく、何かを生み出してみたいという創作意欲に駆られたのだ。これが少年漫画的なら「俺は連載を目指すぜ!」といった熱血展開になるのだろうが、本作で描かれるのはもっと等身大で地味な一歩。まずは同人誌イベントで作品を出してみよう、というレベルなのが妙にリアルである。雪はそれを全力で応援し、自分の知り合いの印刷会社を紹介したり、腰痛に耐えながらもできる限りのサポートをしてあげたりする。そうしているうちに、雪自身もまた“新しい景色”を手にしようとしているのだ。
劇中では、雪の娘が帰国して老人ホームの件を改めて相談したり、うららの幼なじみ・紡(つむぐ)やクラスメイトの英莉(えり)がちょいちょい物語に絡んできたりと、サブストーリー的要素も散りばめられている。どれも直接的なアクシデントにはならないが、それぞれが何かを抱えている。たとえば英莉は留学を決意していて、うららがそれを知って複雑な気持ちになる。うららからすれば、陰キャで大人しい自分と違い、英莉は“華やか”に見える存在だ。「あの子はずるいくらいに輝いているな」と思ったりもするのだが、実際は英莉も将来に対する不安を抱えている。そうした互いの心情がほんの少し交差する場面には、じんわりとした励まし合いを感じる。
さて、物語の大きなヤマ場の一つが、うららが自分の描いたオリジナル作品をコミティアに出展するくだりだ。もともと内気な性格の彼女にとって、イベントのあの独特な活気はハードルが高い。果たしてうららは無事に会場で本を並べることができるのか…というところがちょっとしたクライマックスになっている。そこでは、自分の作品が“他人に読まれる恐れ”と闘いながら、同時に「誰かに手に取ってほしい!」という願望も混ざっている。いわば“自己表現”を一歩踏み出す怖さと期待。その緊張感が手に汗を握らせるのだ。
そして雪はその日、腰痛が悪化して会場に行けなくなるという試練に見舞われる。どうにも立ち上がれない雪にとって、コミティアは人生に一度きりの大冒険のようなイベントなのに、参加できないもどかしさが募る。さらに、道中で偶然出会った人物が実はうららの好きなBL漫画家本人だったという運命的な要素もあり、思わず「そんなことある!?」と突っ込んでしまいそうになる。しかしファンタジックなほどの偶然が、この物語にはぴったりハマっている。それは、「年齢も環境も違うふたりを引き合わせたのだから、多少の偶然も許してほしい」という作者のメッセージにも感じられる。
クライマックスのもう一つのポイントは、うららがイベント会場でなんとか出展しようとするのだが、萎縮してしまってベンチで時間を潰してしまう部分だ。これを観ていると「やっぱり内気な子ってそうなるよな」というリアルさが胸に刺さる。ついに覚悟を決めるのは友人や家族の力、あるいは“何かを守ろうとする気持ち”が芽生えた瞬間だ。実際、うららを後押しするのは幼なじみの紡だった。紡自身も留学問題で揺れる英莉との関係にモヤモヤしているが、それでも友人の初チャレンジを支えようとする。そういう優しさが、うららを最後の勇気に駆り立てたのだろう。
結局、そのコミティアではほとんど売れず、雪も間に合わず、うらら自身も「もっと準備しておけば良かった!」と後悔の連続だ。それでも終わってみれば「楽しかった」と言い切るうららと、それをあたたかく見守り「私も本当は行きたかったわよ」と笑う雪の姿が印象的である。人生の新しい扉を少しだけ開けてみた後味が、スクリーンいっぱいに広がっていく。
その後、雪は娘のいる海外に移住するという決断をする。最初は「こんな大きな家を離れるなんて…」と踏ん切りのつかない様子だったが、うららとの出会いを経て「自分の未来を変化させるのは悪いことじゃないかもしれない」と思い始めたのだろう。2人が最後に訪れるのは、雪が熱中して読んでいたBL漫画の作者・コメダ優のサイン会だ。そこでは奇跡のような再会があり、うららが描いた同人誌がコメダ優本人の手に渡るという展開が待っている。リアルさを追求するなら「世の中そんなに上手くいかない」と突っ込みたくなるが、この作品では「そうなってくれてありがとう!」と素直に思える。なぜなら本作は、最初から最後まで「人は案外、少しのきっかけで変化を起こせる」ことを信じているからだ。
こうしてみると、本作の根底に流れるテーマは“他者との出会いを通じて自分を認められるようになる”ということに尽きる。高校生のうららが「こんなこと誰にも言えない」と隠していたBL好きという趣味が、年齢差のある雪にあっさり受け止められ、一気に世界が開けた。その結果、うららは自分で同人誌を作るところまで成長する。そして75歳の雪も「年齢的に無理だわ…」と決めつけず、思い切ってコミティアに参加したり海外移住に踏み切ったりと、これまで想像しなかった景色へ向かう。そこに深いドラマがあり、観客は「ああ、私だって今からでも何かできるんじゃないか」と希望を抱けるのだ。
芦田愛菜と宮本信子の自然体の演技は、この淡々としたストーリーを魅力的に見せる最大の原動力といえる。芦田愛菜は幼い頃から知名度が高いが、本作では“ぱっとしない女子高生”になりきっている。目線の落とし方や走り方一つをとっても、地味さや照れくささがにじみ出る仕草が丁寧だ。一方、宮本信子は名女優らしい安心感で、雪のおっとりとした雰囲気をどこまでもやわらかく演じている。BLにときめく姿も可憐であり、まるで乙女回帰を果たしたような明るさを放つ。2人が並んで縁側に座るシーンは微笑ましさの塊だ。
そして原作マンガの中での“作中作”であるBL作品「君のことだけ見ていたい」のビジュアルも、本作の大切な要素になっている。映画製作にあたって、人気BL作家・じゃのめが書き下ろしたというから、その本気度がうかがえる。キャラクター同士の視線の交わりや絶妙な距離感、カバーイラストのきらめきが「そりゃ雪もハマるよな」と思わせる説得力を持っている。そこに魅了された雪と、もともとBL大好きなうららが意気投合するのは至極当然だと納得できるわけだ。
全体を通して、その世界観は“ほのぼの”かもしれないが、テーマの中核は「好きなものを胸を張って好きだと言う強さ」と「その楽しさが誰かを救う」可能性だ。何気ない一歩が人生を大きく転換させることは、現実でも起こり得る。だからこそ本作を観ると、「こんな些細なきっかけが巡ってきたら、私も乗っかってみたい」と背中をそっと押された気分になるのだ。良くも悪くも急展開はなく、クライマックスでも大事件は起こらない。しかし登場人物たちが少しずつ進化し、自分の可能性を信じようとする姿を見せてくれる。その日常的で控えめな盛り上がりが、逆にクセになってしまうのである。
ラストシーンでは、雨降る中を雪とうららがタクシーで帰り、縁側で「今日はいろいろあったから大変だったね」と笑い合う。うららは「いや、むしろ完璧な一日でした」というような台詞を口にする。実はここで劇中のBLマンガの名セリフとリンクしているのだが、その瞬間に2人の世界がまるでフィクションと現実を飛び越えたように温かく重なり合うのが最高に気持ちいい。未来は誰にも分からないが、今は“好き”を大切にしていいんだというメッセージに胸を打たれる。
映画「メタモルフォーゼの縁側」は、人間関係に疲れたり、なんとなく自信を失ったりしている人にこそおすすめしたい。“新しい出会い”は、もしかしたら年齢も境遇も違うところから転がり込んでくるのかもしれないと思うと、世界がちょっとだけ楽しくなる。BLというジャンルに抵抗がある方でも、映画そのものは丁寧に優しく作られているので、いつの間にか自然と物語に引き込まれてしまうだろう。芦田愛菜の魅力と宮本信子の柔らかな存在感が融合し、観終わった後に心をぽかぽか温めてくれる良作である。
映画「メタモルフォーゼの縁側」はこんな人にオススメ!
本作をおすすめしたいのは、まず“自分の好きなものをまだ見つけられない人”だ。うららと同じく周囲に話しづらい趣味や関心がある人はもちろん、それを堂々と言えずに悶々としている人にも響くものがあるだろう。好きなものがあるだけで人生はちょっと面白くなるし、それを分かち合える相手がいればさらに世界が広がる。その過程が作品全体からしみじみと伝わってくるのだ。
また、年齢を理由に新しいことを諦めがちな人にも観てほしい。雪は75歳でありながら、新たなジャンルに飛び込んだり同人イベントに参加しようとしたりと、まさに“小さな挑戦”にワクワクしている。若い頃に比べれば体力や時間は限られているかもしれないが、“やりたい気持ち”は何歳になっても湧き上がるのだということを本編は教えてくれる。だから「歳だから…」と二の足を踏む人こそ、雪の姿を見て一歩踏み出してもらいたい。
さらに、人間関係に窮屈さを感じている人や、今ひとつ自分の殻を破れないという人にも合うだろう。この映画の登場人物たちはどこか不器用で、互いを大事に思いながらも遠慮したり臆病になったりする。でも、その不器用さがリアルであり、かつ他者との何気ない会話や協力を通じて状況を好転させていく。観ているうちに「人を頼っていいんだ」「意外とみんな優しいかもしれない」とほっとするはずだ。
最後に、BL作品に縁のない人もぜひ試してみてほしい。劇中に登場するBLマンガは決して過激な要素ばかりではなく、むしろ友情や青春の甘酸っぱさが詰まった純粋な物語として描かれている。そこにハマった雪が生き生きとしていく姿を見れば、「年齢も性別も関係なく、好きなジャンルを楽しむっていいなあ」と素直に思えるはずだ。そんな感慨を与えてくれるこの作品は、きっとあなたの心をゆるやかに揺さぶってくれることだろう。
まとめ
「メタモルフォーゼの縁側」は、自分の好きなものを好きと言うことを後押ししてくれる映画である。17歳と75歳という年齢差コンビが時にテンポよくやり取りをしながら、互いの人生に少しずつ風穴を開けていく。そのきっかけがBLマンガという意外性もおもしろいが、重要なのは誰かと何かを共有することで人は思いがけない力を発揮できるということだろう。
特別な才能や華やかな舞台がなくても、人は自分の“好き”や“応援”を励みに行動を起こせる。うららと雪はそんな姿を見せてくれるし、周囲の人々も優しさをもって応じるので観ていて心がほどけていく。観終わる頃には「自分だって何か挑戦していいのでは?」と、そわそわした前向きな気持ちに変化しているかもしれない。そういう意味では、人生の次のステップを踏み出すためのちょっとした“後押し”となる良質な作品だ。