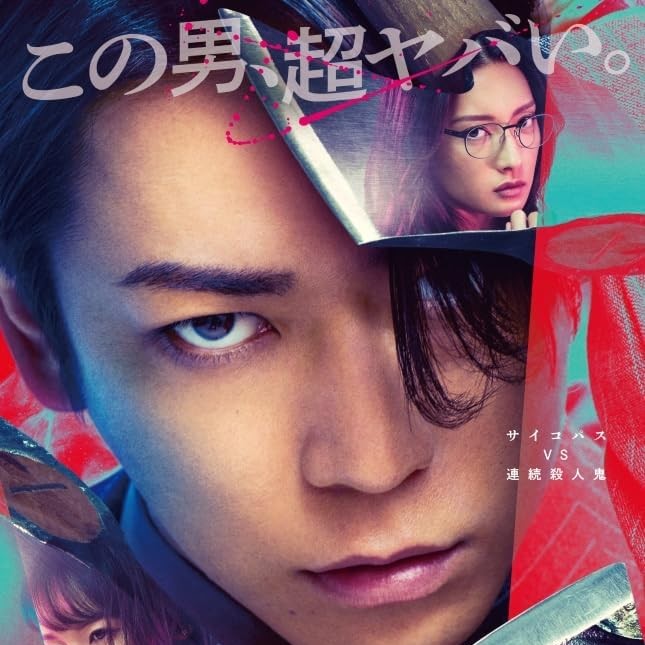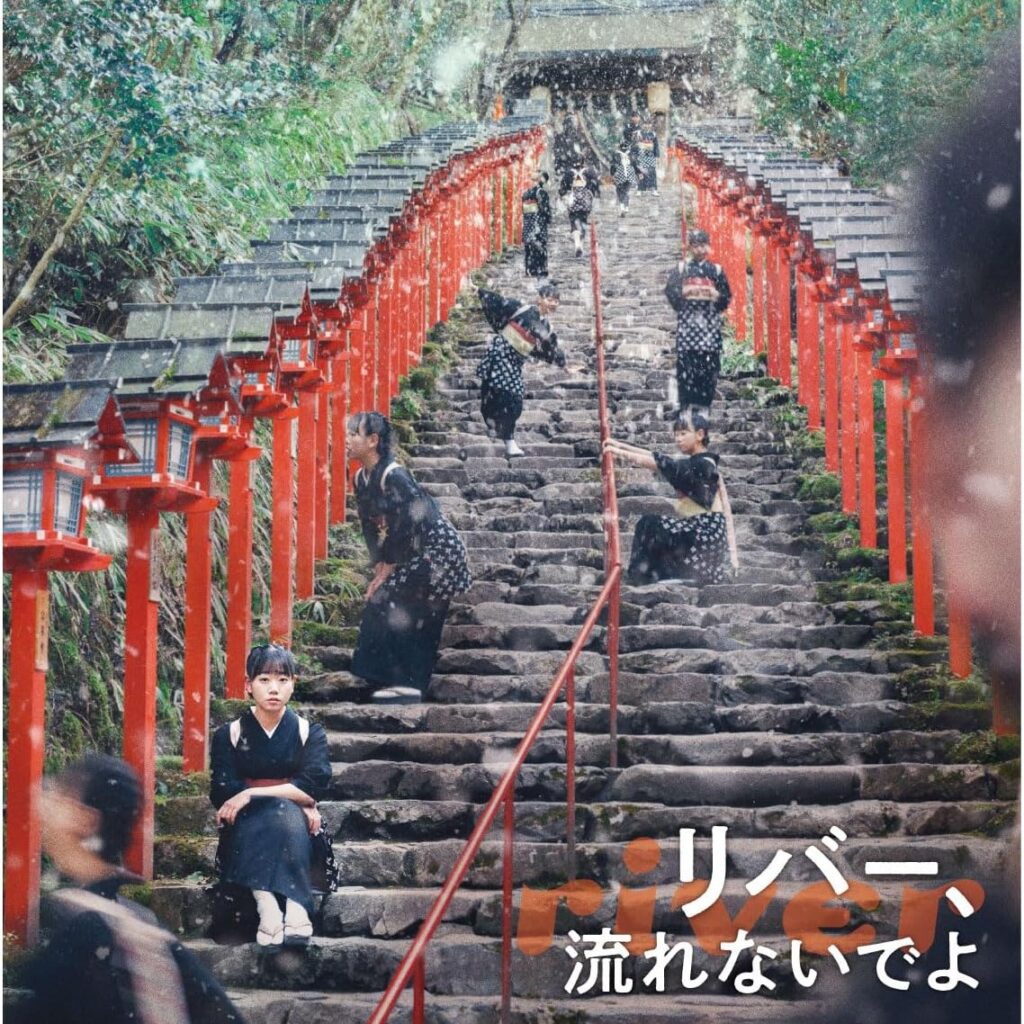映画「首」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
戦国時代を舞台にしつつ、どこか現代的な風刺も感じさせる一作である。監督・脚本を務めた北野武氏ならではの大胆な演出と、豪華俳優陣による迫力の演技が詰め込まれているのが特徴だ。冒頭から人の首が飛び交い、「そこまで見せるのか」と目を背けたくなる残酷さを描きつつも、妙に気が抜けるような軽妙な場面もあって、思わず笑いがこみあげる瞬間がある。血なまぐさい合戦や凶暴な信長像など、“いかにも”な戦国絵巻に留まらず、百姓上がりの人物が悪戦苦闘しながら天下を狙う姿や、策略を巡らす武将たちのすれ違いが、観客の度肝を抜く展開へとつながっていくのだ。
勢いのまま突き進むシーンが多い反面、それぞれの登場人物が見せる表情や、一瞬の静寂が生む緊張感なども見どころ。肉薄する殺気と脱力する間のコントラストに、自分の感覚があやうく振り回されそうになる瞬間が心地よい。本作に潜む一筋縄ではいかない魅力を、ここから徹底的に語っていく。
映画「首」の個人的評価
評価: ★★★☆☆
映画「首」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本作は、織田信長に仕える武将たちが互いに跡目を争う中で裏切りと愛憎が錯綜する、いわば“戦国版の狂乱劇”といえよう。あらすじ自体は歴史的事実として語り尽くされてきた本能寺の変を下敷きにしながらも、監督の手によって随所に独創的な表現が盛り込まれている。とりわけ血生臭い描写と、脱力感を誘うシーンが混在しているのが目を引く。
まずは織田信長(加瀬亮)の暴れっぷりである。一般的なドラマや史書では「カリスマ性が高い天下人の候補」として描かれることが多いが、本作ではより凶暴かつ執念深い姿が強調され、家臣相手に飛び蹴りをかましたり、刀に刺した饅頭を無理やり食べさせて血塗れにしたりと、まさに常軌を逸した男として登場する。しかも、信長自身が家臣を愛でるような“行為”を見せ、森蘭丸との絡みや明智光秀(西島秀俊)との複雑な関係を示唆する場面が幾度も差し込まれるのだ。このあたりは、かつての大河ドラマや歴史映画が持っていた“荘厳さ”をあえて壊しにかかっているように見え、観ている側の意表を突く。
一方、羽柴秀吉(ビートたけし)は、いわゆる「百姓から天下人になった男」というお馴染みの人物像を踏襲しつつも、どことなく照れ屋で強引なところがあり、実際には「そこまで知略を巡らせるタイプではない」というアレンジが施されている。たとえば会議の場面では、参謀役となる黒田官兵衛(浅野忠信)や弟の秀長(大森南朋)に背中を押されてはじめて行動を起こす姿が描かれ、本人はぶっきらぼうに怒鳴り散らすだけ。しかし武功を上げる機会を虎視眈々と狙っており、“次の天下取り”という目標を口にするあたり、弱気と野心が同居する秀吉像が浮き彫りになるのがおもしろい。人をコマ扱いするような嫌な顔を見せつつも、どこか親しみを感じさせるのは、役者ビートたけしの存在感ゆえだろう。
明智光秀は物語上、かなり焦点を当てられているキャラクターだ。恋仲として描かれる荒木村重(遠藤憲一)を助けるために、堂々と織田方の追及をはぐらかす場面があり、さらに千利休(岸部一徳)の茶室で密会したりする展開が続く。このあたりは名うての軍師というより、愛情に揺さぶられる人間臭い光秀の姿にフォーカスされている。やがて信長が家康を殺そうと暗躍する中で、信長が絶対的な力をふるう姿を目の当たりにし、「自分はただの捨て駒なのか」と憤りを募らせる。この人物の苦悩が最大化する流れの先に、「本能寺での反乱」へと至るわけだが、そのクライマックスでは思いもよらぬかたちで信長の死が描かれる。信長の首を探す光秀が「首がなければ証明にならない」と焦る場面こそ、本作のテーマが凝縮されているように感じられる。
作品の随所にあらわれる百姓たちの姿は、さらに異様な迫力がある。中でも、難波茂助(中村獅童)は最初から最後まで“どうしようもない”キャラクターとして突き進む。親友を欺いて首を奪い、家族が殺されても「むしろ気楽になった」と言い放ち、さらには戦場で敵将の首をねつ造して手柄をかすめ取ろうとするなど、その卑劣さたるや凄まじい。一般的な合戦映画であれば、百姓あがりの脇役が奇跡的な大功を挙げて出世するという“痛快譚”が描かれがちだが、本作はむしろ現実的に「弱者は弱者なりに手段を選ばない」という一面をあぶりだしているようだ。そんな茂助が最後に明智光秀の首を手に入れて歓喜するが、あっという間に他者に討たれてしまうシーンは、本作の凶暴な世界観を象徴している。いかに首を取ろうが、取った直後に新たな敵が現れれば意味がない――戦国時代という殺伐とした舞台を端的に示す瞬間でもある。
さらに、千利休の茶室まわりで繰り広げられるやり取りもユニークだ。茶道に通じた名士としてではなく、政治と暗躍の中継地点を担うフィクサーとして描かれるのが新鮮である。彼は明智光秀、秀吉、そして荒木村重をつなぐ影の存在でありながら、裏切る者にはあっさり容赦しない。部下の間宮無聊(大竹まこと)と曽呂利新左衛門(木村祐一)が最期に“刺し違える”結末を迎えるあたりは、互いが裏切りを警戒している戦国の怖さを端的に表しているといえよう。しかもその刺し違えがどこか滑稽でもあり、不思議な空気感を生んでいるのが印象的だ。
本作を語るうえで大きな要素となるのが、首をめぐる執着心だ。合戦で敵将の首を取ることがそのまま評価や恩賞につながるため、下克上や出世を狙う者にとっては首こそが実績の証明となる。だからこそ、どの武将も「敵将を討ち取った」とアピールできる首を欲しがるし、首を奪うためには平然と仲間をも捨て石にする。しかし、いざ豊臣秀吉が明智光秀との最終戦に勝利した後、首の確認を行った際に「こんなもの意味がない」とばかりに蹴り飛ばすのは、彼が“実はそんなものに頼らない”人間だからなのかもしれない。或いは、自分が勝利しさえすれば首の有無など些事、という強烈な自負の表れとも見られる。これこそ北野武監督が皮肉めいて描く「首」へのアンチテーゼのようでもある。
そのほか映像面では、殺陣や合戦シーンにおいてかなり生々しい血飛沫や断末魔が描かれ、息を吞む迫力がある。その一方で急に場面が切り替わり、地味に間の抜けたやり取りが挿入されることもあり、気を張っているといきなりズッコケそうになる。こうした流れが連続するため、作品全体が緊迫感と脱力の両輪で走っており、観客の想像する戦国絵巻とは一線を画す仕上がりになっていると感じた。いわば超ド派手な歴史スペクタクルでもあり、奇妙な滑稽劇でもある、という相反するテイストを同時に成立させている点が興味深い。
役者陣の競演も見逃せない。信長役の加瀬亮は、普段の落ち着いたイメージをかなぐり捨て、荒々しい雄叫びを上げるかと思えば突然誰かを蹴り飛ばし、明智光秀に挑発的なキスをするなど、常に狂気を放っている。明智光秀を演じる西島秀俊は、献身的でまじめな家臣という表面を保ちながらも、腹の底でくすぶる怒りを滲ませ、笑みなのか苦悩なのか判別しづらい表情を作り出す。遠藤憲一が演じる荒木村重は、光秀との絡みで「嫉妬」すら感じさせる感情を露わにし、本能寺の変直前に突き落とされる悲哀を宿したまま姿を消す。いずれの人物も、細やかな所作や目線で激しい感情を体現しており、観客としては視線を外せない。
こうして見ると「ここまで戦国武将を乱暴に再解釈して大丈夫なのか」と思うほどだが、むしろその振り切り方こそが本作の魅力だろう。表面的な史実忠実度を求める人にとっては違和感のある演出や改変が目立つかもしれない。しかし、本来“下克上”が当たり前だった戦乱の世を、あくまでフィクションとして徹底的に叩き込んだことで、本能寺の変という大事件に「血も涙もない凶暴な人間同士の欲望のぶつかり合い」という説得力を付与しているように思える。
本作は壮絶な血の物語でありながら、どこか突き放すような感覚と奇妙さを備えている。歴史映画や時代劇の常識をものともしない演出は好みが分かれるだろうが、北野武監督の新境地を存分に感じ取れるのではないか。首をめぐり、結局は人間が欲と欲とで争う姿を断面図のようにえぐり出したその鮮烈さに、自分は大いに刺激を受けた。戦国時代はもとより“殺るか殺られるか”という過酷な世界であったはずだが、それを現代の感覚で眺めたときに生じる戸惑いやおかしさこそが、本作の真髄なのではないかと感じさせられる。
映画「首」はこんな人にオススメ!
歴史ものが好きであれば、まずは目を奪われるに違いない。登場人物は誰もが名将として知られる武将や軍師たちだが、その実態は裏切りと打算に満ちている。歴史の授業で学んだ「織田信長」「明智光秀」「豊臣秀吉」といった名前に、つい格式ばったイメージを抱きがちだが、本作では良くも悪くもその幻想がぶち壊される。きれいごと抜きの戦国絵巻を体験してみたい人には格別だろう。
また、壮大なスケールの合戦シーンと、そこに紛れ込む足軽や百姓の不条理さに興味がある人にも推したい。戦(いくさ)自体が過酷なものであることを否応なく突きつけられ、その一方で必死にもがく人間の姿を見ていると、いつしか自分も“生き残りを賭けて足掻く一人”の気分になってくるかもしれない。誰しもが出世や功名を夢見ているものの、最後には容赦ない現実が襲いかかる――そのシビアさを容赦なく描く点が、しんみりする反面、思わず苦笑いしたくなるポイントでもある。
時代劇を見慣れていない人でも、いきなり飛び出すバイオレンスや奇妙な掛け合いに圧倒されることで、むしろ新鮮に楽しめるかもしれない。重厚な歴史研究よりも、型破りな物語を好む人、または北野武監督特有の切れ味ある表現に触れたい人には絶好の一作だ。「こんな描き方があったのか」と驚かされると同時に、役者たちの迫真の演技に引き込まれ、気づけば熱中しているだろう。要するに、王道の時代劇や美談的な歴史映画を期待するより、「なんだかすごいものを見てしまった」という衝撃を味わいたい人におすすめだ。
まとめ
ここまで振り返ってみても、映画「首」は従来の歴史映画や時代劇とは一線を画すアプローチで描かれているといえる。織田信長が神格化されることもなく、明智光秀が忠義一筋でもなく、羽柴秀吉が完全無欠の知将でもない。それぞれの腹の内が丸見えになり、血なまぐさい合戦の果てにあっさりと首が転がっていく。そんな乱世の混沌と人の欲望を、エグい残酷さと予測不能のやりとりで表現している点が刺激的だ。
また、浮世離れした奇妙な場面の連続に面食らいながらも、気づけばスクリーンに引き寄せられているあたり、本作には独特の魔力がある。特に終盤、誰がどの首を狙い、何のために争っているのかが混沌と化すなかで、最終的に首そのものが「どうでもいいもの」として扱われる瞬間はなんとも言えない虚無感を誘う。そこにこそ北野武監督流の皮肉や大胆さが凝縮されており、ただの歴史再現ドラマに終わらない深みがあるのではないか。血みどろの戦国時代をぶち壊しにしながら、斜め上の角度から描き切った本作は、一度観たら忘れられない印象を残すだろう。