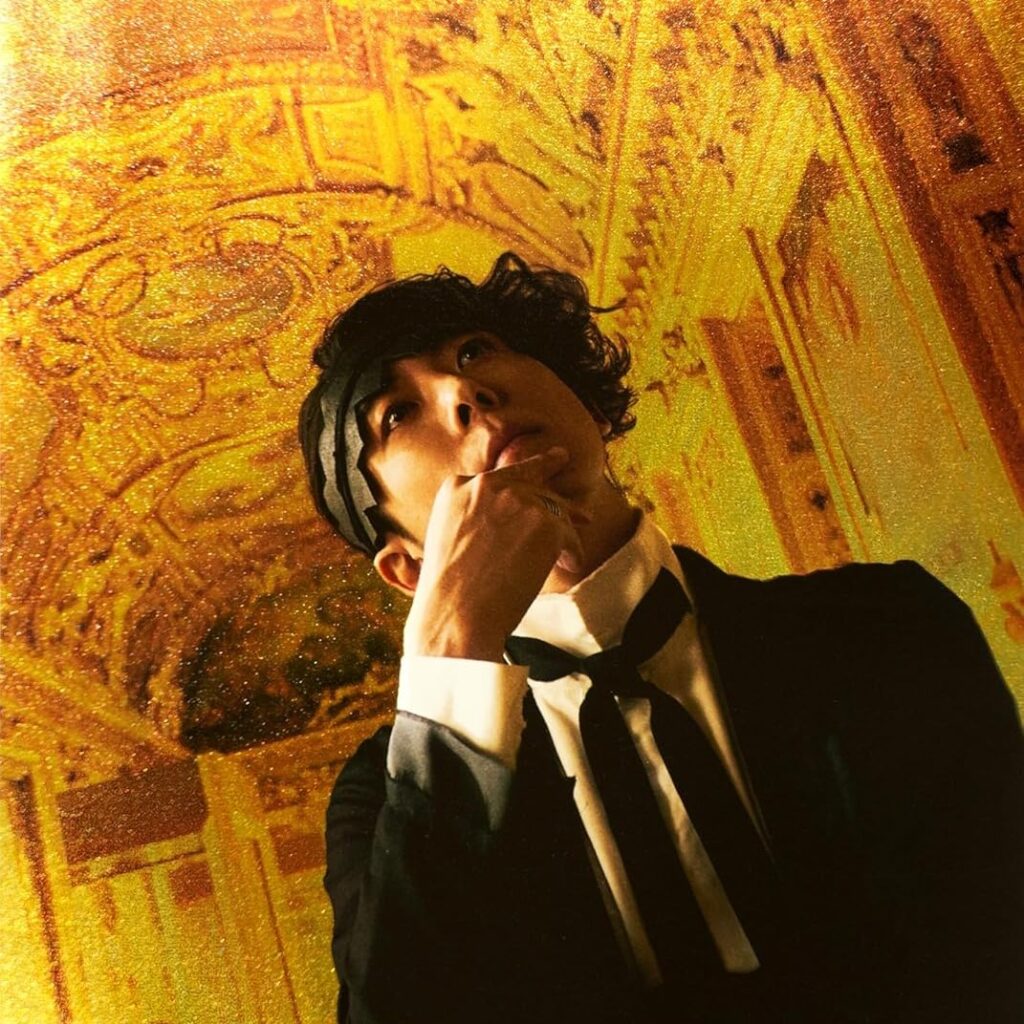映画「金の国 水の国」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
2017年に「このマンガがすごい!」で第1位を獲得した岩本ナオの原作コミックをアニメ化した本作は、一見すると可愛らしいイメージだが、その内側にはなかなか手強い人間模様が隠れていると感じた。
舞台となるのは、水を除けば何でも豊富な“金の国”と、緑と水は豊かだがいかんせん貧しい“水の国”の2つ。仲が悪いと知りつつも、それぞれの思惑に巻き込まれた王女サーラと建築士ナランバヤルが“偽りの夫婦”となるところからストーリーが動き出す。
「おっとり姫×お調子者の建築士」という組み合わせは、まるで伝統的な童話かと思えば、実は政治的な駆け引きあり、両国の未来をかけた攻防ありの大騒ぎ。明るく柔らかいタッチのアニメーションで表現されるからこそ、スルッと入ってくるが、その裏には国を揺るがす厳しい現実も詰め込まれている。そうしたギャップが妙にクセになる作品だと感じたのだ。騙されたと思って観てみると、思いがけず笑いつつ考えさせられる展開に驚くはずである。
映画「金の国 水の国」の個人的評価
評価:★★★☆☆
映画「金の国 水の国」の感想・レビュー(ネタバレあり)
まず、本作の魅力は“金の国”アルハミトと“水の国”バイカリという2国の対立構造にある。仲の悪さを示すエピソードがなかなか秀逸で、500年という途方もない歳月にわたり、小さな諍いから大きな衝突までゴタゴタが絶えないという話が冒頭でテンポよく語られる。それだけ聞くとシリアス極まりない歴史ドラマを予想するかもしれないが、実際には「犬のフンがどう」とか「猫のオシッコがこう」といった些細なことでケンカに発展してしまうのだから、なんだか拍子抜けする。だが、その“拍子抜け感”が狙いなのではないかと思う。大昔の絵本のようなナレーションと相まって、「ああ、そういうゆるいノリでずっと続いてきたわけね」と観客を素早く作品世界に馴染ませる効果があるからだ。
ここで主人公となるのが、“金の国”アルハミトのおっとり王女サーラと、“水の国”バイカリの建築士ナランバヤルである。物語上は、アルハミトが「国で一番美しい娘を嫁に出す」、バイカリが「国で一番賢い若者を婿に出す」という約束を交わしたことがきっかけらしいが、実際にサーラとナランバヤルに届いたのは猫と犬だったというとんでもないすれ違いが発生していた。両国の偉い人たちも面子を保つのに必死なので、そこら辺の混乱をうまいこと隠そうとする展開が笑いを誘う。サーラのほうは、王女の中でも地味扱いされがちで引っ込み思案。ナランバヤルは口が立ち、商人ばりの商才や交渉力を持っているが、あまり勤勉というわけでもなく、でもなぜか愛嬌はある――そんなキャラクターだ。
ふたりは国境付近で偶然出会うわけだが、普通なら「まさかあなたが……!」「きゃー!」みたいな劇的なロマンチック場面があるかと思いきや、けっこう緩いスタートである。サーラは犬(ルクマン)が迷子になりそうだったから探しに来ただけ、ナランバヤルはちょっと散歩がてら何かの用事に出ていた、くらいのニュアンスでストンと出会う。この自然体の“偶然”こそが、彼らの関係性を象徴しているといえる。あくまで「両国を救うために結婚せよ!」と絶対的な圧力をかけられたわけでもないし、「運命的にビビッと一目惚れ!」でもない。気づけばなんとなく一緒に行動してしまう、その距離の縮まり方が微笑ましい。
しかし、サーラは王女という立場ゆえ、周囲に「バイカリの婿がちゃんと来ました」とアピールする必要に迫られる。そこでナランバヤルに「悪いけど、しばらく花婿のフリをしてくれない?」と頼むのだ。逆にナランバヤルはナランバヤルで、族長から「あんたに嫁をやるから迎えに行け」と言われていたのに、実際に来たのは猫。こっちも「女性のフリをしてくれ」と頼めるはずもないが、バレると戦争どころではない騒ぎになる可能性もあるから、うまく口を濁してその場をしのごうとしている。つまり、ふたりとも「正直、国の面子や評判なんてどうでもいいけど、下手なことを言うとトラブルが大きくなるから黙っておこう」という姿勢で一致してしまうわけだ。そこがまた、どうにも親しみやすい。
このあたり、アニメ版の描き方はかなりテンポが良い。サーラとナランバヤルは、そこそこ巻き込まれ体質なわりに発想力と行動力があるので、どこへ行っても事件が起きるたびに「どうやって切り抜けようか……」と即興的に作戦を立てる。たとえばアルハミトの王宮では、大臣同士の派閥争いや王女たちの思惑が絡んで、どっちの陣営に転がっていくか次第でナランバヤルの安全が左右される。そこで彼は巧みな弁舌とノリのよさで、イケメン左大臣サラディーンを味方につけ、あれよあれよという間に“水路建設計画”をぶち上げるのだ。
この“水路建設計画”こそが本作の核心のひとつであり、文字どおり“水の国”から“金の国”に水を通そうというものだが、それは単なる技術の話だけに留まらず、両国が手を取り合って未来を共有するという政治・外交の要でもある。実際、アルハミトは気候的にも水不足が深刻という設定だし、バイカリは十分な資金がない。だから双方協力すればいいものを、歴史的に水と油の関係のせいでまともに話がまとまらないのだ。そこでナランバヤルは、「だったら自分が動いて皆を説得するしかない」と腹をくくる。普段はお調子者なのに、こういう場面になると意外な行動力を発揮するから憎めない。
一方のサーラは、ナランバヤルが仕掛ける壮大な計画に巻き込まれながらも、「私なんかに何ができるのだろう」と悩む。王女とはいえ、93番目の姫という立場もあって地味扱いされており、“美しい女性代表”などというおとぎ話みたいな看板を背負わされることにも緊張している。実家の姉たちは派手好きでプライドが高く、何かと張り合ってくる。そうしたちょっとした“家族あるある”が現実味を帯びており、なまじ幻想的な世界観なのに変に生々しいギャップが生まれるのが面白い。加えてサーラは体型のせいもあってか、昔から外見を笑われがちだったようだ。そのあたりのコンプレックスが、彼女の優しい笑顔の裏でくすぶっているというのが切ない。
そんなサーラが“水の国”に足を踏み入れたとき、ナランバヤルの実家にたどり着き、彼の家族や地元の人々とふれあう場面も印象深い。あちらはあちらで「一番賢い男が選んだ嫁=絶世の美女だろう」と高をくくっているが、実際に姿を見たら「あれ、意外と普通……?」とイジワルを言われる。でもそこにいたのは、サーラが馬鹿にされて黙っていられなくなるナランバヤルの父親や仲間たちであり、彼らは自分の身を呈してまで助けるのだ。こうした場面を通してサーラは徐々に“誰かのために行動する勇気”を覚え、ナランバヤルも“家族のためにがむしゃらに頑張れる”という本質をさらに明確にしていく。両国のイザコザは相変わらず厄介だが、ふたりの絆はどんどん深まっていくのが微笑ましい。
後半では、いよいよ両国を巻き込んだ大事件が起きる。アルハミトの右大臣ピリパッパは“国王にゴマをすること”だけを生業としている人物で、戦争をちらつかせてでも力を得たいという危険な考えを持っている。それに対抗するレオポルディーネ王女やサラディーン、投獄されていた学者ジャウハラなど、味方サイドもなかなかキャラが濃い。ところが追い詰められてしまうのはやはりナランバヤルとサーラで、なんだかんだでアルハミトの宮殿で大立ち回りを演じる羽目になる。もちろん彼らは戦闘の達人ではないから、武器を振りかざす敵兵を力づくで倒すわけにはいかない。そこを機転や仲間の助けで切り抜けるのがスリリングかつ小気味いい。
クライマックスでは、国王ラスタバン3世も登場し、ナランバヤルやサーラとやり合う場面が描かれる。実はラスタバン3世にとっても、父ラスタバン2世が「バイカリに和平を持ちかけたまま腰抜け王扱いされてしまった」という記憶が大きなトラウマとなっていた。つまり、戦争を望んでいるのではなく、自分の名誉を守るために強硬策に走っていただけであり、実は周りが思っているほど恐ろしい存在でもなかったのだ。ナランバヤルはそこに目をつけ、「父王が残せなかった偉業を自分たちで成し遂げてみせる」「そのほうがずっと歴史に名を残せる」と説得を試みる。ここから先の展開は、二国の未来をかけた会話劇でありながら、しっかりハラハラできるし、アニメ表現としても壮大なスケールを感じさせる構成になっている。
最終的には、ナランバヤルとサーラは両国の衝突を収める大きなきっかけを作り、水路建設の計画も軌道に乗っていく。かねてから予想される通り、ふたりは本当の意味で夫婦となり、この先は平和な未来が広がるだろう――という温かな結末を迎えるわけだ。しかし安直なハッピーエンドというより、挫折や葛藤、周囲のイジワルなどもたっぷり描いたうえでの到達なので、どこかスカッとした納得感がある。特にサーラの「こんな私だって、誰かと手を携えて生きていけるんだ」という喜びや、ナランバヤルの「最初は勢いで引き受けただけだったが、気づいたら本気で皆を守りたいと思っていた」という流れが実に丁寧で、観ていて頷ける恋愛譚に仕上がっている。
声優として参加している俳優陣も、耳を傾けているうちに違和感が薄れていく。ナランバヤル役の賀来賢人は原作イメージからすると“軽妙で頭の回転が速いキャラ”をどれだけ演じられるかが鍵だったが、思いのほかしっくりきた。浜辺美波が声を当てるサーラも控えめな優しい声質がマッチしているし、オドンチメグ(猫)やルクマン(犬)たちの細やかなリアクションも愛らしい。さらに「サマーウォーズ」などを手がけたマッドハウスの作画は色彩豊かで、昔読んだ少女漫画の扉絵のような世界をアニメで観る楽しさが詰まっていた。加えて、脚本は「コウノドリ」の坪田文、音楽は「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」やNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で注目を集めたエバン・コールが担当しているなど、各所で力量のあるスタッフがしっかり仕事をしている印象だ。
原作コミックを読んだファンからすると、一部エピソードの端折りや再構成もあるだろうが、映画として一気に観せるには十分な完成度だと感じた。2国のそれぞれの文化や街並み、衣装デザインの差などが映像表現で楽しめるのもアニメ映画ならではである。また、“金の国”は豪華で小難しそうに見えるが、中身はけっこう庶民が生き生きしているし、“水の国”はどこか素朴でぬくもりを感じる風景だが、案外ドロドロした派閥争いもあったりと、どちらが善でどちらが悪とも言いきれない微妙なバランスが面白い。そうやって細部を見ていくと、この物語が「戦争ってやっぱり互いの無理解や偏見から生まれるんだな」というメッセージを、わざと大げさに説教せずコミカルに示していることに気づく。
「ゆるい雰囲気」と「緊迫した争い」の入り混じり方が独特で、その温度差がクセになる作品である。「恋愛ものはあまり得意じゃない」「ファンタジーと聞くととっつきにくい」と思う人でも、意外とスッと物語に入り込めるはずだ。気軽に観られるのにしっかりと胸に響く何かがあるからこそ、このコミックがかつて各界から絶賛されていたのだろう。自分の地元や家族を大切に思う気持ち、それによって踏み出せる一歩の重みが生むドラマは、ちょっと昔ながらのおとぎ話を思わせつつ、現代にも通じるテーマだといえる。
結論をいえば、本作は観終わったあとにじんわりと温かい気持ちになれるタイプの作品だ。国と国が相手でも、誠意と優しさをもって取り組めばまだ間に合うのかもしれないと思わせる。王道の夢物語と思うかもしれないが、その“王道”を正面から真摯にやりきっているからこそ説得力があるのだ。偽りの夫婦を演じる2人が本当の愛を育んでいく過程も、本作なりの独自の道のりがしっかりと用意されている。そこに何度も笑いを挟むテンポの良さが、最後まで飽きさせないポイントになっていると思う。
もし“金の国”の眩いばかりの黄金と、“水の国”の潤いある大地、その両方に興味があるなら、ぜひ本作を体験してみるといい。いがみ合うことが当たり前になっている世界であっても、「誰かが最初に手を差し伸べる」だけで未来が変わるというロマンが、しっかりアニメーションとして花開いているのだ。無意識のうちに抱えていた先入観すら、その柔らかな世界観によってスルリと解きほぐされていくはずである。
映画「金の国 水の国」はこんな人にオススメ!
この映画は「おとぎ話のような世界観が好きだけど、ただの子ども向けでは物足りない」という人に向いていると思う。ストーリーの根っこにあるテーマは“国同士の争い”とか“階級”といった重めの題材だが、それをアニメの柔らかいタッチでくるんでいるので、シリアスだけど見やすい絶妙なバランスが保たれている。普段あまりアニメを観ない大人でも、気づけば最後まで一気に物語に引き込まれるはずだ。
また、王道の恋愛話にちょっとひねりを効かせてほしい人にもオススメである。何しろ男女のビジュアルがいわゆる“超美男美女”というわけではなく、ごく普通っぽいところが新鮮だ。外見にコンプレックスを抱えたヒロインと、それをあまり気にしない建築士の青年という組み合わせは、現実に近いリアリティを感じさせつつも、ファンタジーの世界観ともうまく合致している。だからこそ起きる誤解やスレ違いが、微妙に切なくも笑えるポイントになっているのだ。
さらに“家族を大切にする気持ち”や“仲間との絆”が好きな人にも心に刺さるはず。ナランバヤルはふだんの軽妙な口ぶりと裏腹に、本質的には家族への想いを熱く抱えているキャラだし、サーラに関しても周囲への優しさから一歩を踏み出す勇気を獲得していく。そういった成長物語的な要素があるから、ファンタジーに興味のない人でも感情移入しやすいと思う。ややこしい事情だらけの世界を舞台にしながら、しっかりと“人間くささ”を描いているところが本作の強みだといえる。
まとめ
映画「金の国 水の国」は、2つの国の長年の対立を背景にしながらも、どこか懐かしい温もりを感じさせる作品だ。派手な戦闘シーンや迫力満点のアクションがあるというわけではないが、犬と猫の行き違いや、王宮でのちょっとした駆け引きなど、ところどころに笑える出来事が散りばめられており、緊張感と軽やかさが絶妙に共存している。とりわけ、少し地味だけど愛らしいサーラと、口はうまいけど根は純粋なナランバヤルが織り成すドラマは、観るほどに愛着が湧いてくるから不思議だ。
物語の結末はハッピーエンドではあるが、それに至るまでには両国それぞれの複雑な事情や登場人物の悩みがリアルに描かれているため、ただの夢物語には感じにくい。むしろ「自分たちも実はこういう小さな誤解を抱えながら生きているのではないか」と考えさせられる部分もある。だからこそラストシーンには素直に心がほぐされるのだ。観終わったあとは、ちょっとばかり生活が明るくなるような、そんなポジティブな力を持った作品だといえる。