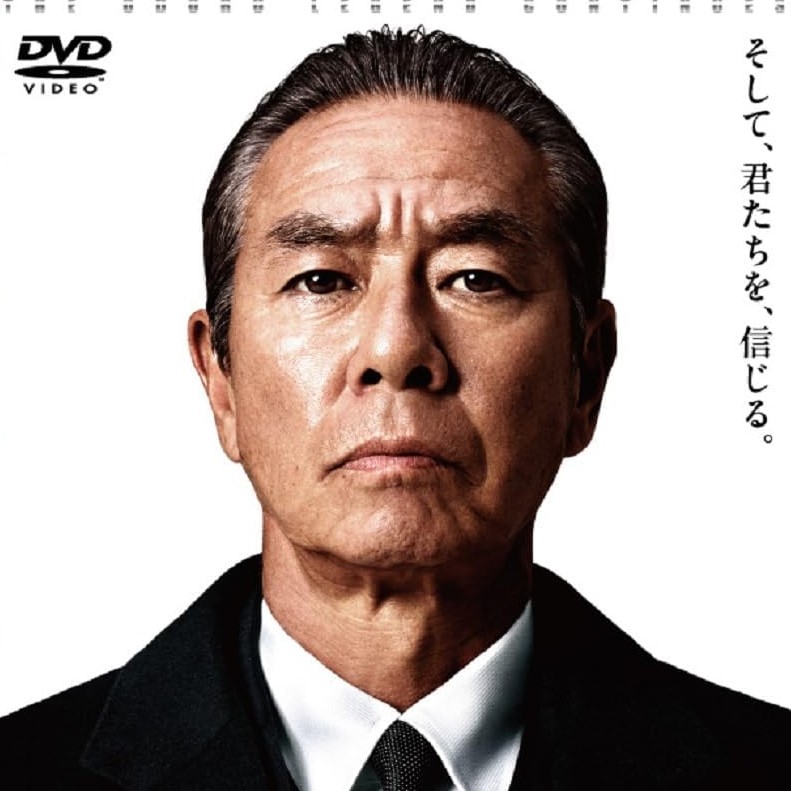映画「きみの色」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
青い海と坂道が印象的な長崎をモデルにした街を舞台に、人の思いが色として見える主人公・日暮トツ子の視点から始まるのが「きみの色」である。監督は『聲の形』や『平家物語』などで知られる山田尚子で、脚本は数々の名作を手がけた吉田玲子が担当。新作が出るたびに話題をさらうコンビだけに、本作品も公開前から注目されていた。実際に鑑賞してみると、シスターが見守るミッション・スクールを舞台にしながらも、どこか不思議な空気が漂っており、観る者を独特の世界に引き込んでくれる。表面的には落ち着いていそうで、実はモヤモヤした悩みを胸に抱えた高校生たちが、バンドを通じて一歩ずつ成長していく姿は感慨深い。特に、視野の広いルイと、少し秘密めいたきみ、それにトツ子という三人の組み合わせが絶妙で、このチームだからこそ生まれる特有のハーモニーにグッとくる。
さらに、ラストの盛り上がりでは想像以上に感動させられ、見終わった後の余韻もなかなか消えない。とはいえ、笑いを誘うやりとりや印象的な挿入歌もあり、全体として軽快さが保たれているのも素晴らしいところだ。青春の悩みや絆を、鮮やかな色彩とともに繊細に描いた作品なので、「青春ものはちょっと苦手…」という方にも意外と刺さるかもしれない。ここからはネタバレを含む話もするので、鑑賞前の方はくれぐれも注意されたい。
映画「きみの色」の個人的評価
評価:★★★★☆
映画「きみの色」の感想・レビュー(ネタバレあり)
主人公の日暮トツ子は、他人の感情や本質を色として視覚化できるという、珍しい力を持っている。この力は彼女にとって便利なようでいて、実は大きなコンプレックスでもある。幼い頃に好きだったバレエを諦め、今は寮生活を送りながらミッション・スクールに通う日々。実家を離れ、周囲と合わせて大きくはみ出さないように暮らしているようでも、どこかで自分の色を見つけたいと思っている――そんな彼女の心情が非常に丁寧に描かれているのが印象的だ。
ストーリーの鍵を握るのが、あっさり学校を退学しながらも、古書店でバイトを続ける作永きみと、離島で開業医を営む母を手伝いながらも音楽に情熱を持つ影平ルイの存在である。きみは祖母に内緒で学校を辞めたという秘密を抱え、ルイは将来は医者を継ぐと周囲から期待されているなかでこっそりバンド活動をしている。二人は、それぞれに本音を言えず苦しんでいる部分があるため、トツ子の不思議な雰囲気に惹かれつつも、どこか距離を測っていたように見える。しかし、トツ子が強引ともいえる勢いで「一緒にバンドをやろう!」と誘ったことで、思わぬ三人組が誕生してしまうのだ。
ここで気になるのは、バンドを組むきっかけがよくある「文化祭」や「大会出場」といった明確な目標ではなく、「しろねこ堂(古書店)での何げない出会い」と「言い出しっぺのトツ子の衝動的な思いつき」という点である。普通なら、練習場所にも困るし楽器すらちゃんと触ったことがない人がいるのだから「大丈夫か…?」と思うが、本作品はそこをかなり大胆に突き進んでいく。実はルイがテルミンやオルガンといった珍しい楽器を自力で集めてきたり、自宅のある教会(離島)を使って練習できる環境があったりと、かなり自由度が高い展開なのだ。観ている側も「そんなに都合よくいくか?」とツッコミたくなるが、そこには若者特有の勢いと、シスター日吉子の温かいサポートが絡んでいるので納得してしまう。
シスター日吉子が実は相当ロックな過去を持っていたという裏設定も面白い。寮生活のルールに厳しそうなのに、バンドを結成したいというトツ子たちには妙に甘い。と思いきや、要所要所で信念を感じさせるアドバイスをくれるので、まるで悩める子羊を導く牧師のようである。作品後半で、バレンタインに合わせた学校行事に三人を参加させようと動く彼女の姿は胸に響くものがある。単なる“おせっかい”とは違う、人を助けることへの情熱と、自身の若き日へのちょっとした照れくささが混じっているようでもあり、教師や大人の理想像を具現化したような人物に思える。
一方で、きみとルイが抱える家庭の問題はなかなかシビアだ。きみは祖母の期待を裏切る形で退学してしまい、ルイは母に言えずこそこそ音楽をやっている。共通するのは「大切な人を失望させたくないのに、どうしても打ち明けられない」という弱さである。この二人が合宿(という名の逃避行)を経てようやく秘密を話し合うシーンでは、クスッと笑えるようなやり取りもありつつ、それぞれが固く閉ざしていた胸の内を少しずつ解放していく。同じ悩みを抱える仲間がいるというだけで、背中を押されるのだ。
そして、真のクライマックスはバレンタイン祭のステージで披露される三曲のライブパフォーマンス。「反省文」「あるく」「水金地火木土天アーメン」というインパクトある曲名だけで心をくすぐられるが、その歌詞やメロディにも三人の思いがぎゅっと詰め込まれている。最初の曲「反省文」は、学校側に提出する反省文をそのまま歌詞にしてしまうという荒業で、思わず「こんなのでいいのか!」と笑ってしまうが、同時に彼らの切迫感が伝わってきて妙に説得力がある。二曲目の「あるく」は、きみが讃美歌に通じる清らかな声で歌い上げる穏やかなミドルテンポ。聴いていると、自分の人生を見つめ直す不思議な力があるように感じてしまう。
そして、最後に炸裂するのが「水金地火木土天アーメン」。惑星名を唱える単純なフレーズに合わせて、トツ子の頭の中のカラフルな世界が弾けるかのような展開になり、これまで悩んできたすべてを吹き飛ばす勢いを見せる。観客もシスターたちも、曲が進むうちに立ち上がって踊りだす様子が微笑ましく、劇中のキャラクターたちだけでなく、こちらも画面越しに力をもらえるようだ。きみとルイの家族もしっかり間に合い、ようやく彼らの秘密と好きなことを肯定してくれた瞬間には胸が熱くなった。
さらに、ライブ後のエピローグも見逃せない。春になり、トツ子が校庭でバレエを踊りきるシーンには、彼女のずっと拭えなかった後悔が解消された爽快さがある。みんなの色ばかり見えていたトツ子が、ようやく自分の赤い輝きに気づく場面は、ただの能力というより「自己肯定」のメタファーに思えてグッとくる。自分自身を受け入れられなかった彼女が、仲間と一緒に楽曲を作りあげることで成長し、「私ってこんな色だったのか」と気づくのは実にドラマチックだ。
最後にルイが船に乗って島を出ていくくだりも切なさと希望が入り混じる。きみが全力で「頑張れー!」と叫ぶシーンでは、普段クールなきみが見せる珍しい全開の感情に驚きつつも、何やら今後の物語を想像させる余韻に浸らせてくれる。視覚的にも色彩の洪水のような演出があり、「色」というコンセプトが存分に活かされていると感じた。山田尚子監督特有の繊細かつ大胆なカメラワークや音の使い方も相まって、単なる青春物とは一線を画す独特の魅力を放っている。
もちろん、筋がシンプルで起伏が少ないと感じる面はあるかもしれない。だが、行間に漂う人々の温かさや、諸事情を抱えた若者たちのリアルな悩みがじわじわと刺さってくるのが「きみの色」の醍醐味だと思う。勇気を出して秘密を打ち明けること、失敗や後悔を肯定し合うこと、その一歩を踏み出すためのエネルギーがバンド活動を通じて生まれたのだと考えると、観終わった後にじんわりと感動が広がるはずである。さらに、作品全体に漂う不思議な軽妙さが、鬱々しすぎず前向きにさせてくれるので、エンドロールが終わるころにはもう一度観たくなるような余韻を残す。
日常の中にちょっとだけ踏み込んだ空想と、若者の本音と建前がほどよく混ざったこの世界は、恋愛要素だけではない多様な感情を受け止めてくれる。まさしく「自分の色を知りたい」「隠し事があるけれど誰にも打ち明けられない」という人にこそ響くのではないか、と思わずにはいられない。夢に向かう人、あるいは夢を諦めかけた人、どちらもきっと心が少しだけ軽くなる。そういう優しい光に満ちた物語である。
映画「きみの色」はこんな人にオススメ!
自分の「好き」がなかなか言えずにもやもやしている人に、とにかく刺さる作品である。バンド活動という熱量の高い行為そのものが、すべてをぶちまけるための良い口実となっているので、胸の中の本音を出せない人ほど共感できるはずだ。
また、音楽映画にはよくあるプロ志向の熱血展開というよりは、「自分たちが今、これをしたい」というピュアな動機が主体になっているため、ストイックすぎる雰囲気が苦手な方でも楽しめるだろう。さらに、宗教が背景にあるからといって重苦しさはまったくなく、ほのかに漂う敬虔な気配がむしろ新鮮さを引き立てている。長崎の坂道や美しい海、離島の空気感も相まって、作品全体が柔らかく包み込むような空気を帯びており、「疲れたときにふらっと鑑賞して癒されたい」というニーズにも応えてくれそうだ。悩みを抱えている若い世代はもちろん、大人になってから「やりたいことを諦めた」記憶を持つ人も、何かしら得るものがあるだろう。
三人組の不器用な優しさと、そっと背中を押してくれる大人の姿勢に触れると、日常の小さな不安が少しだけ軽くなる気がする。合唱や礼拝のシーンが好きな方、音楽を通して成長する物語に惹かれる方、あるいは「色彩」をモチーフにした作品に弱い方には特におすすめである。
まとめ
「きみの色」は、長崎の風景や教会の神聖さに彩られながらも、青春の葛藤をしっかり描いている点が魅力的である。バンドを通じて自分の秘めた思いを解放するトツ子、家族に打ち明けられなかった真実と向き合うきみ、そして夢を追いつつ周囲を気遣うルイと、それぞれが背負った悩みを抱えつつも前に進んでいく姿が心に残る。不思議な能力を持つトツ子の視点によって、人間関係や感情の色彩が一層鮮明に映し出され、派手ではないが優しい光を放つ作品となっている。
ライブシーンでは笑いあり感動ありの展開で一気に盛り上がり、最後には少しの寂しさと大きな希望が同居した余韻が訪れるのだ。観終わったあと、「自分もあの場所で一緒に演奏してみたい」と思わせるほど、三人が奏でる音はあたたかい。本音を言いづらい人も、過去に挫折を味わった人も、どこか肩の力を抜いて楽しめる名作である。