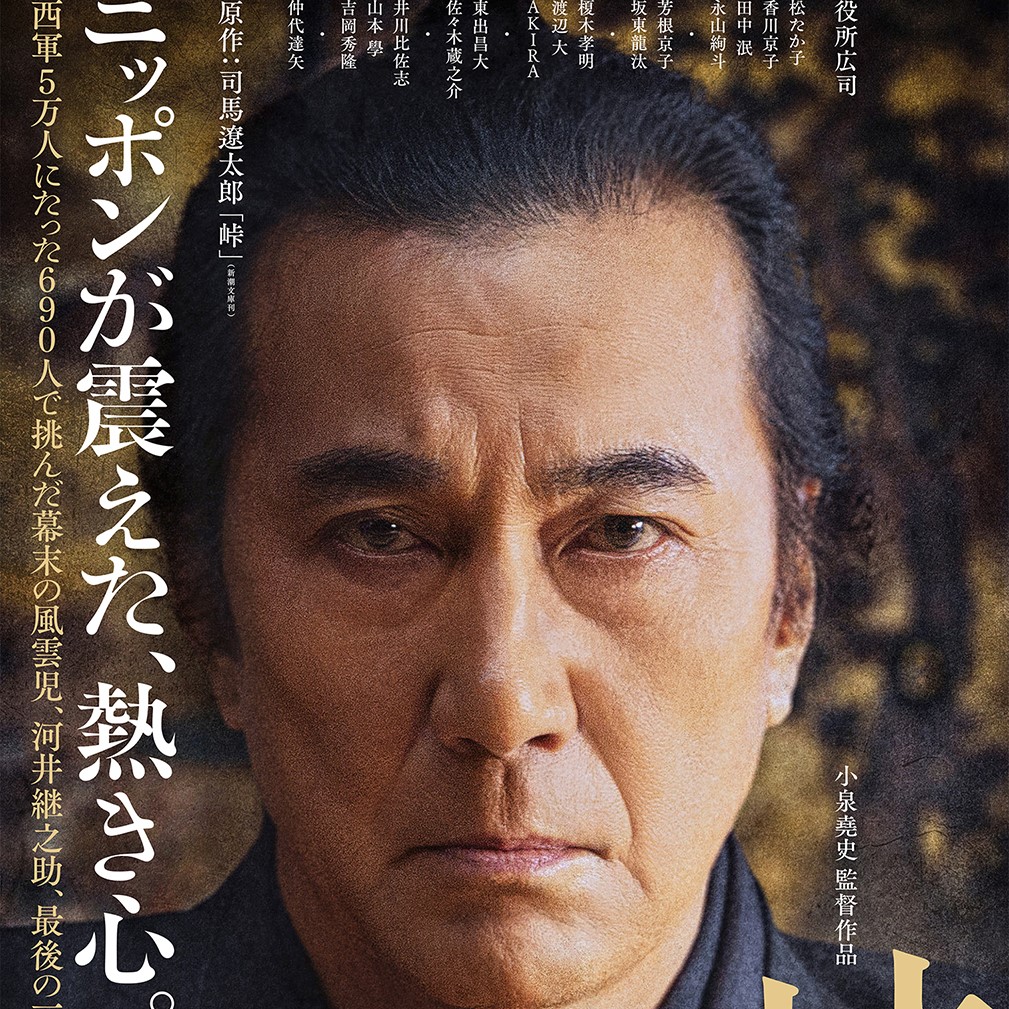映画「はい、泳げません」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
本作は綾瀬はるか主演の一風変わった人間ドラマである。哲学教授でありながら水が怖くて泳げない男と、水中こそが自分の居場所だと信じる水泳コーチ。両極端な2人がプールという特異な空間で出会い、互いの人生にじわじわと入り込んでいく姿は、なんとも笑いを誘う展開だ。しかも、水泳教室に集う個性豊かな主婦たちのエネルギッシュな姿や、思わぬかたちで重なり合う過去の記憶が物語を一筋縄ではいかない方向へ運んでいく。
見た目はクールなはずの哲学教授が水と格闘するさまは、まさに珍妙な光景。その裏で繰り広げられる切ない思いと再生の物語は、プールの水面のように静かでありつつも揺れ動く。そんな“できそうでできない”もどかしさを、笑いとシリアスの絶妙なバランスで描いた本作を、隅々まで掘り下げていきたいと思う。
映画「はい、泳げません」の個人的評価
評価:★★★☆☆
映画「はい、泳げません」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本作は、一見すると「泳げない大人が水泳を習うだけの話か」と思いきや、その裏側には実に多層的なテーマが詰め込まれている。舞台となるのは小さな水泳教室。そこに足を踏み入れるのが、長谷川博己演じる哲学教授の男性だ。彼は幼い頃のトラウマによって水に対する恐怖を抱き、まったく泳ぐことができない。いや、正確には「泳ぎたい気持ちはあるが、どうしてもできない」というジレンマに陥っている状態である。
そんな彼を待ち受けるのが、綾瀬はるか演じるコーチ。プールの中に身を置くときだけは誰よりも生き生きとする彼女は、陸を歩くときに不安を覚える人物だ。交通事故のトラウマで外界を自由に動けず、雨でもないのに傘を手放せない姿が印象的である。プールでは強気に「怖がる暇があったら動きなさい!」と檄を飛ばすのに、いざ外に出ると周囲の車を警戒しておどおどするギャップがなんとも人間味を帯びている。
この水泳コーチと哲学教授の凸凹コンビが繰り広げるやりとりが実に面白い。教授のほうは「水と自分は対等ではない」「水が攻撃してくるイメージが離れない」などと難しい理屈を並べ立てては、なかなか一歩を踏み出せない。しかしコーチが言う「勝ち負けの話じゃない」「水に身を任せるんだ」のひと言に、ハッとさせられる。何でも頭で考えすぎるタイプの人間にとっては、理屈ではなく感覚で覚える行為はなかなかの難関だ。だがここで彼女の言葉が妙に説得力を持つのは、コーチ自身もまた陸を歩くことが苦手で、常に警戒を強いられる立場にあるからだろう。違う方向から似たような悩みを抱える者同士の対話は、ほほ笑ましさとともに深い共感を呼ぶ。
さらに、彼らを取り巻く登場人物も曲者ぞろいだ。たとえば水泳教室の常連である主婦たちは、人なつっこく陽気に教授をいじりまくる。プールサイドでは、「あんた若いのに泳げへんなんて、そんなことある?」とからかい、わざと声をかけたり背後から水をかけたりしながら、彼を水に慣れさせようと奮闘する。いわゆる“おせっかいなご近所のおばちゃん”像に近いが、そのおかげで主人公が無理なく雰囲気に溶け込めるというわけだ。時に言い過ぎてしまうが、気づいたらちゃんと謝ったり励ましたりするあたりに、彼女たちなりの“人情”がにじむ。ちょっと滑稽でありながらも温かい空気がこの教室に漂っているのは、彼女たちのパワーが大きい。
主人公の男性には、一度壊れてしまった家族の記憶がある。かつて麻生久美子演じる妻とともに暮らし、幼い息子がいた。しかし、その子が川で事故に遭い、主人公自身も何もできなかった自分を責め続けている。水と聞くだけで、あの時の恐怖がフラッシュバックする。しかし彼は、心のどこかで「泳げさえすれば」という願望を捨てきれない。それが現在の水泳レッスンへとつながっているのだが、練習を進めるにつれ、封じ込めていた思い出が顔を出し始める。
実は、主人公には新たに親しくしている女性がおり、彼女には小学生くらいの子どもがいる。教授はその子ともうまくやっていきたいと思う反面、過去のトラウマが頭をよぎり、一歩踏み込むことができない。もし再び誰かを守るべき状況が訪れたとき、自分は逃げずに行動できるのか。あるいは、水に溺れる自分の姿をまたさらしてしまうのではないか。そうした葛藤が、彼の行動や言動をそっと縛り付けている。
一方、コーチのほうにも隠された悩みがある。さっきも触れたように、彼女はプールの中では堂々としているが、外に出れば不安が波のように押し寄せる。実際、彼女は過去の事故をきっかけに、「水の中のほうが安全だ」と感じるようになっているらしい。陸上で車の音や人通りに怯えながら小さくなっている姿を見ると、あれほど力強いコーチが抱える苦しみの根の深さを思わず想像してしまう。主人公の「泳ぎへの恐怖」とコーチの「外を歩く恐怖」が重なり合い、それぞれが自分の苦手分野を通じて人生を模索しているという点で、二人は静かに心を通わせていくのである。
さて、本編の終盤では、主人公がプールで泳いでいる最中に、ついにあの事故の記憶をフルで思い出してしまう場面がある。息子を助けられず溺れてしまったこと、自分だけが気を失い、目覚めたら病室だったという事実。再びその苦しさを目の当たりにした彼は、水から逃げるように教室に通わなくなってしまう。ここで終わってしまったらただの後味の悪い話だが、本作では決してそこで打ち切られない。コーチが夜のプールに主人公を呼び出し、「やめるのはいつでもできる。だけど、あんたは本当にそれでいいのか?」と問いかける場面はかなり印象的だ。
その後、主人公はプールの底でコーチに抱きしめられながら、思い切り涙をこぼす。水の中だから誰にも聞こえないし、誰にも見られない。余計な言葉もいらない。ただ“浮かぶ”という行為を通して、過去の重荷を少しずつ外へ流し出していく。ここの演出はかなり象徴的で、水中という静寂の中で人が泣くという描写が、悲しみだけでなく安堵や希望の感覚を生々しく伝えてくる。この時点で、観る側も「泳ぐ」という単純な動作を超えて、人生の再出発や“生きるためのリハビリ”としての水泳を強く感じられるはずだ。
一か月ほどサボり続けた主人公を再び動かすのは、「生きるのは1人じゃない」という事実である。結局、人が泳ぐのは自分1人でできるかもしれないが、人生となれば話は別だ。誰かの助けを受けたり、誰かに寄り添ったりして初めて前に進む勇気が湧いてくる。主人公は妻だった女性や、新しく大切に思う相手と向き合い、「今度こそ守りたい」と踏み出す気持ちに目覚める。そして最終的には、「はい、泳げます」と笑顔で言えるまでになる。その変化の大きさに、こちらも素直に拍手を送りたくなる。
本作の魅力は、重たいテーマを扱っているのにどこか軽妙に進んでいく点にある。主人公がプールでバシャバシャと苦闘する姿はどこかコミカルでありながら、まったく笑えないような過去の悲劇が同時進行している。コーチもまた同様に、自分が不安定なのに人を助けられるのかという葛藤を抱えている。こうした矛盾やジレンマがキャラクターに厚みを与え、観客は「ああ、人って弱いけど同時にたくましくもあるんだな」と実感する。
また、劇中には哲学の講義のシーンが差し挟まれ、「なぜ人は生きるのか」という問いも呈示される。主人公が学生に向かって「知性とは、新しいことを受け入れる勇気だ」と説く場面があるが、当の本人はその“新しいこと”として泳ぎを選んだわけだ。結果、泳ぎを覚えるプロセスで人生を見つめ直すハメになった。やれ筋肉が痛いだの、息が続かないだのとヒーヒー言いながらも、意地っ張りな教授がふと水の中で解放される瞬間は実に清々しい。水と和解することが、彼にとって自分自身への許しにつながっていく過程は、観ている側にもわずかながら心の浄化を感じさせてくれる。
登場人物たちのやりとりも見どころの一つだ。特に、元妻役の麻生久美子が軽快な口調で関西弁をあしらい、主人公を不意打ちのように励ましたり、きつい言葉をぶつけたりするところは印象深い。一見すると口うるさいだけに思われるが、本当に憎めない存在感があるし、「何やかんや言ってあんたを応援してるんやで」という優しさが後ろに透けて見える。シングルマザーの女性もまた、主人公にとっては新しい人生への希望を象徴する人物だろう。彼女の子どもが彼を慕う姿に救いの光を感じるが、それがトラウマにもつながるという皮肉をはらむ。そうした“善意と不安”のせめぎ合いがあるからこそ、物語に甘さだけで終わらない奥深さをもたらしている。
本作は「泳ぐ」という行為を通じて“生きる”ことを再考させる作品だ。水泳は1人でもできるが、実生活は決して1人で完結しない。そこには人との関係、過去の重荷、未来の希望、すべてが折り重なって波を立てている。そこをどうかき分けて進むのかは、人によって違うし正解があるわけでもない。ただ、今回の主人公のように水泳を入り口にして小さな達成感を積むことで、心が一歩ずつ楽になることもあるのだ。ラストの「はい、泳げます」という一言に至るまでの葛藤を共有することで、観客もまた「よし、自分もまだまだ前に進めるかもしれない」と思わず希望を感じるに違いない。
プールサイドでのコーチとの言い争いや、全身がこわばって沈みかける姿など、滑稽な描写も多いが、その背後では大切な人を喪った悲しみや自己嫌悪が同居している。そういう陰と陽を合わせて引き受けることで、人は初めて「泳げる」と胸を張れるのかもしれない。作品を見終えたあと、「意外と自分も新しいことを始めたら変われるかもしれない」と思わせてくれる一種の爽快感がある。いかにも完璧に再生できるわけではなく、現実には浮いたり沈んだりを繰り返すものだろうが、少なくともプールの水面を切って進む主人公の背中は、立ち止まっていた頃よりもずっと軽やかで明るい。
苦味のあるストーリーでありながら、そこをポップに彩るキャスト陣の掛け合いが絶妙で、くすりと笑ってしまう場面がいくつもある。水泳教室でのアットホームな雰囲気は、悲しみを背負った主人公の心を少しずつほぐしてくれるし、教師というプライドが空回りして背伸びする様子も「頑張れよ、教授!」と応援したくなる。最後まで見届けると「水の中なら、きっと何もかも忘れられる」というコーチの言葉が、まるで観客の心の荷物も軽くしてくれたような感覚になる。その感覚こそが、本作の最大の見どころではないだろうか。
映画「はい、泳げません」はこんな人にオススメ!
まず、泳げない人や水が苦手な人には、もちろん大いに刺激になるだろう。主人公が「泳げるようになりたいけど怖い」という思いを抱えながら、少しずつ水に慣れていく過程は、自分の経験と重ね合わせやすい。子どもの頃に水泳教室で苦労した人や、いまだにプールで立ち泳ぎしかできない人にも共感ポイントが満載だと思う。
そして、何かしらのトラウマを抱えて「一歩踏み出したいのに踏み出せない」人にも心を揺さぶる要素がある。主人公は悲しい過去から逃げようともがくが、その過去を真正面から受け止めることで再び人生を動かし始める。自分は動かずに世界だけが変わることはない、というメッセージが伝わってくるので、どこかで行き詰まりを感じている人ほど本作の励ましを受け取れるはずだ。
さらに、笑いと涙が入り交じるドラマが好きな人にはぴったりだ。悲壮感だけを積み重ねるのではなく、プールの滑稽な空気感や賑やかな主婦の姿が随所に登場するので、いわゆる“重苦しいだけの作品”とは一線を画す。むしろ、笑い話のように見えるシーンほど、じわりと心に刺さるメッセージがこめられていて、見終わったあとに不思議な爽快感を味わえる。水と格闘する主人公を見るうちに、「自分だってもう少し頑張れるかもしれない」と思わせてくれるのが大きな魅力だろう。
まとめると、水が苦手な人、トラウマを抱えて停滞している人、人生を少しずつでも前に進めたいと感じている人、そして笑いと切なさが同居する物語を楽しみたい人にぜひおすすめだ。コーチの奮闘やプール仲間たちの温かい視線が、あなたの心をほんの少し軽くしてくれるはずである。
まとめ
本作は「泳げない人が泳げるようになる」というシンプルな動機から始まる物語だが、その背景には深い哀しみや自己嫌悪が横たわっている。しかも、水に対する恐怖と陸上での恐怖をそれぞれ抱えた主人公とコーチの組み合わせが、奇妙な形でお互いの心を刺激し合うのが見どころだ。水泳教室の騒がしくも温かい雰囲気があったからこそ、主人公は自分の殻を破り、過去を受け止める強さを手に入れる。
結局、人が前に進むためには、誰かとの関わりを避けては通れないという事実を再確認させられる作品だと思う。ラストで主人公が「はい、泳げます」と笑う瞬間には、小さくガッツポーズをとりたくなる。できないことができるようになる喜びは何歳になっても格別だし、その達成感が人生そのものを好転させるきっかけになるのだと、本作は穏やかに教えてくれる。観終わったあと、プールに行きたくなったら、それはもう立派な“心のリハビリ”の第一歩だろう。