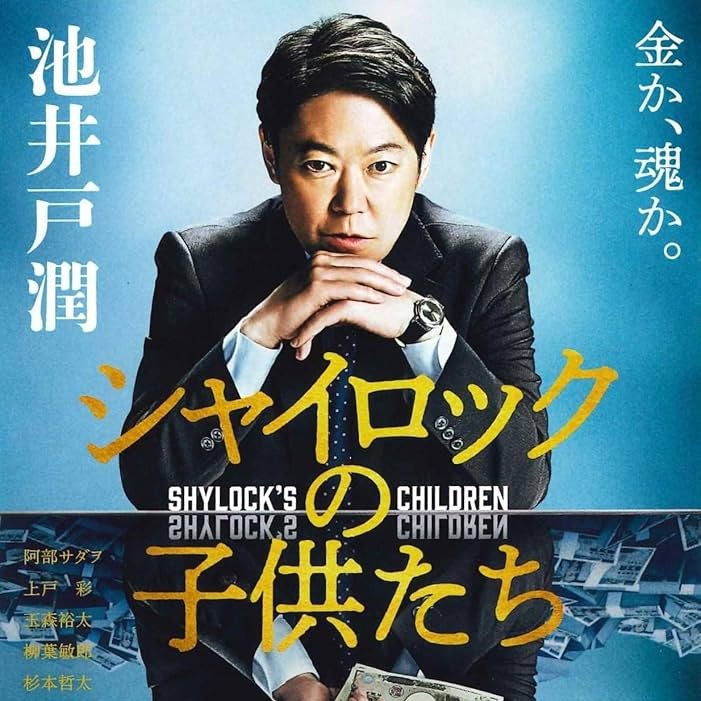映画「銀河鉄道の父」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
岩手県の花巻を舞台に、宮沢賢治と彼を溺愛する父・政次郎の物語が展開される本作は、まず主役として役所広司がズドンと構えている時点で期待と不安が入り混じる代物だ。なにしろ彼の演じる親父像は、厳格でありながら息子には猛烈に甘いという、矛盾が詰まった愛すべき存在。相手役の菅田将暉は、優しくも頑固な賢治を独特の空気感で表現しており、その組み合わせだけでも劇場へ足を運ぶ価値があると思わせる。
実際に観賞してみると、親子ゲンカやすれ違いの連続に加え、時折見せる淡い笑いと切なさが入り乱れ、気がつけばこちらも感情を振り回されていた。だがそのぶん、何ともいえない余韻が最後まで残り、もう一度じっくり味わいたいと感じたのも事実である。エンタメ性と時代背景、そして宮沢賢治の人生を彩る要素がバランスよく混ざり合い、観終わったあと「やっぱり日本映画も侮れないな」と思わせる仕上がりだ。
映画「銀河鉄道の父」の個人的評価
評価: ★★★☆☆
映画「銀河鉄道の父」の感想・レビュー(ネタバレあり)
まず最初に断言しておきたいのは、宮沢家の長男として生まれた賢治の生きざまを追体験するには、この映画だけでは足りない部分もあるということだ。史実と照らし合わせた場合、誰もが「あれ? ここはどうだったの?」と疑問に思う瞬間が出てくるかもしれない。だが本作は、あくまで父親の視点から息子を見つめる物語であり、賢治の華々しい作品世界の全貌ではなく、“親子のドラマ”を軸にまとめられている。そこを理解したうえで観ると、親子愛の裏側にある苦悩や遠回りがしみじみと胸に染みる仕掛けがあり、その点がいかにも日本的な人情物語として愛おしく感じられた。
主演の役所広司が演じる宮沢政次郎は、絵に描いたような厳格な父親だが、その実態は思いのほか我が子に甘い。いや、“甘い”というより、ほとんどメロメロといってもいいくらいの入れ込みようである。周囲からは「父でありすぎる」と突っ込まれるシーンが登場するが、観ているこちらは「そんなに愛情を注いで大丈夫か?」とニヤけつつも心配になってしまう。特に序盤では、政次郎がまだ幼い賢治を看病する場面が印象的だ。普通なら妻のイチに任せるところを、父親みずから付きっきりで世話をしてしまう様子に「そこまでやるか」と脱帽する。いわゆる“溺愛”ぶりが強烈なのだ。
しかし、さすがに大人になった賢治が商売を嫌がり、「農民のために生きたい」と言いだす段になると、政次郎もわりと本気でブチ切れる。時代的に考えても、長男が家業を継ぐのは当たり前。ところが賢治は、そんな空気をまるで読まない。むしろ、「まったく別の道を歩むのが自分の使命だ」とすら思っている節がある。なまじ頭も良く、感受性が豊かなぶん、他人の苦しみを見ていられないからこそ、質屋という職種そのものが“弱い者いじめ”に映ってしまうらしい。この善人ぶりが行きすぎて、周りを振り回す結果になるあたりが賢治らしいが、親父としては何度も雷を落としたくなるところだろう。実際に映画でも、部屋から閉め出したり、小言を言ったりと、政次郎も必死に“厳しい父”の立場を守ろうとする。だが結局は、賢治のわがままをなんだかんだで受け止めてしまうのだから、どれだけ親バカなんだと笑ってしまった。
とはいえ、賢治の“わがまま”は本気で人の役に立ちたいという優しさから生まれているものだ。東京へ行って宗教を学び、自分を見失いかけるほど信仰に傾倒するのも、その根底には「どうすれば他人の苦しみを和らげられるのか」を常に考えているからなのだ。周囲から見れば「そこまでやるなんて、ちょっと怖い」と思われるかもしれないが、自分の幸せよりも他者の幸せを優先してしまう辺りが、なんとも不器用である。この不器用さが災いして、政次郎と賢治は激しくぶつかる。家を出てしまう賢治を政次郎が追いかけたり、祖父や妹のトシをめぐるエピソードで親子関係がゴタゴタしたりと、ややこしいドラマが山ほど詰まっているのが本作の特徴だ。
特に妹トシの病気と死は、宮沢家に大きな影を落とすイベントであり、賢治が執筆にのめり込む大きなきっかけとなる。いつか“日本のアンデルセン”になると夢見ていた賢治を、トシはずっと応援していたらしい。映画のなかでも、トシは賢治の背中を押す存在として描かれていて、「兄ちゃん、物語をいっぱい作ってくれないと困る」と言わんばかりに励ましてくれる。これまで散々家族を振り回してきた賢治が、妹の願いを叶えようと紙に筆を走らせるシーンは、なんとも胸が締めつけられる思いだ。妹が喜んでくれるなら、家業も投げ出してしまうし、お経を唱えてでも救おうとする。その真っすぐさこそが、宮沢賢治という人物の根っこの部分を表しているように思う。
このあたり、映画では悲しい場面も多いが、全体としては意外にこそばゆい笑いが散りばめられている。政次郎と賢治が顔を突き合わせて、互いにヒートアップする場面もどこか滑稽で、お互いを想い合っているからこそ噛み合わないのだとわかる。役所広司と菅田将暉の演技が絶妙にマッチしているおかげで「親子のすれ違いって大変だけど、なんだか温かい」と思わされるのだ。そこに森七菜演じる妹トシの可憐さが加わり、さらに花巻の方言がいい味を出す。おかげで映画全体は重たさに沈むことなく、どこか人情あふれる人間ドラマに仕上がっている。
後半になると、賢治は妹を失った悲しみを背負いつつ、今度は自らも体調を崩し始める。ここから先はかなり切ない展開で、観ている側も「まさか、またこんな試練が…」と肩を落としかねない。そこへきて政次郎が見せる愛情の深さは、もう一種の執念のようにも見える。それまでの人生を賢治中心で動かしてきた政次郎にとって、息子を失うかもしれない状況は耐えがたいはずだが、それでも必死に支えようとする姿勢には頭が下がる。宗教の壁をめぐってあれだけケンカしてきた親子が、最後にはお互いを認め合う姿には、素直にグッときた。
また、最期のシーンにおける政次郎の対応は涙なしには観られない。あの場面はほぼ静かな演出なのに、役所広司の目の動きや表情がすべてを物語っていて、この俳優の底力をまざまざと見せつけられた気がする。さらにそこへ菅田将暉の小声が絡み、賢治が抱えていた思いがポロリとこぼれ落ちる。あそこは確実に“泣き所”として仕込まれているはずだが、押しつけがましくならない程度に感情を揺さぶってくるのがニクい。思わず鼻をすすっている観客が多かったのも頷ける。
音楽や映像面でも、岩手の自然が醸し出す空気感がじっくりと描かれており、賢治がなぜファンタジーや詩に傾倒したのかが不思議と納得できる。森が青々と揺れ、風が吹くたびに草木がさわぐ情景に、観ているだけで気持ちが洗われそうになる。ただ、その中で修羅のように自分を追い込む賢治の姿を見ていると、ひたすら「なんて不器用な奴なんだ…」と思ってしまうのも事実だ。それを包み込もうとする父親はやはり苦労が絶えない。でも、苦労するほど燃えるのが父親というものかもしれない。
本作は、歴史的に有名な文豪の若き日を描きつつも、実際にはもっと地味で生々しい家庭のドラマを前面に押し出している。賢治の創作や人生を大きく動かした背景に、政次郎という父親の献身があったのだという事実を、改めて意識させられる構成だ。この父親がいなかったら、世界中で愛されるあの童話はどうなっていただろう…と想像すると、面白いような怖いような、不思議な余韻が残る。いわゆる“親バカ”も突き詰めれば一つの才能なのかもしれない。
一方で、わずか37年で息を引き取った賢治の苦悩や孤独にも思いを馳せると、どうしても切ない気持ちになる。自分の書く物語を父親に読んでほしい、褒めてほしいという子どもじみた願望が最後に描かれるが、そこに至るまでの賢治は、少しも大人らしくなれなかったのではないか。だが、その“未熟”こそが賢治の魅力であり、特別な感性の原動力になっていたとも考えられる。政次郎という巨大な器があったからこそ、この不思議なクリエイターは伸び伸びと作品を生み出せたのだろう。
本作は甘口一辺倒のホームドラマではなく、やるせない苦味が散りばめられた人間物語だ。明治から昭和の激動期を生きた家族の姿は、現代の我々にも学ぶところが多いと思う。宮沢賢治の作品を愛読している人はもちろん、そこまで詳しくない人でも親子関係を真正面から描いた人情物に触れる感覚で楽しめるだろう。観終わったあと、自然と役所広司ふんする政次郎に「お疲れさまでした、あんた最高だよ」と言いたくなる一作である。
映画「銀河鉄道の父」はこんな人にオススメ!
まず、家族の絆にグッとくる話が好きな人にはドンピシャだ。特に「親子のすれ違いと和解」に弱い方は、泣く準備をしておいたほうがいいかもしれない。息子を溺愛する父親が空回りしながらも必死に支え、最後にその愛情が報われる展開は、どうしようもなく胸が熱くなる。さらに、菅田将暉演じる賢治の不器用さにイライラしつつも「わかるわかる」と共感してしまう人は多いはずだ。理想に駆られて現実が見えなくなるタイプや、やりたいことが多すぎて周囲を巻き込んでしまうタイプは、賢治をまるで他人事に思えなくなる可能性が高い。
次に、文学作品の舞台裏や作家の人生を知るのが好きな人にも刺さるはずだ。宮沢賢治というと、教科書や文庫本で名前を見たことはあっても、具体的にどんな家庭環境で育ったかを深く知らない人もいるだろう。本作は原作が直木賞受賞の小説をもとにしているだけあって、あの作品群がどんなバックボーンから生まれたのかを、父親の視点から解き明かしてくれる。もちろんフィクション的な脚色もあるだろうが、そこがむしろドラマとしての面白さにつながっている。
また、岩手の風土や、昔ながらの商家の暮らしぶりを味わいたい人にもオススメだ。質屋の仕事ぶりや地方都市の雰囲気、家族が食卓を囲む場面など、どこか懐かしい空気が映し出される。そうした背景描写に「なるほど、こんな風土からあの独特な発想が出てきたのか」と感心する瞬間もあるだろう。堅苦しい文芸映画というより、親子コメディの要素が散りばめられた人情噺として楽しめる点もポイントだ。
まとめ
本作は、岩手県花巻の質屋を営む宮沢家が舞台となり、文豪・宮沢賢治の“父親目線”で描かれた新鮮なアプローチが光る映画だ。実際の賢治像を完全に再現するというよりは、息子を溺愛しながらも翻弄され続ける父親の姿を通じて、“人を愛する”という行為の泥くささを浮き彫りにしている。なんでも許容してしまう政次郎と、純粋すぎる賢治のぶつかり合いは一見コミカルだが、そこには時代背景や宗教観の相違も混じり合い、ままならない現実が垣間見える。
ただ暗いだけではなく、笑える場面や心温まるシーンも多く、家族ドラマとしての見応えは十分だ。何より役所広司と菅田将暉の演技合戦が見事で、それぞれのキャラクターに対する愛着がどんどん湧いてくる。この親子がいてこそ、あの名作が誕生したのだと思うと、なんとも感慨深い一本である。