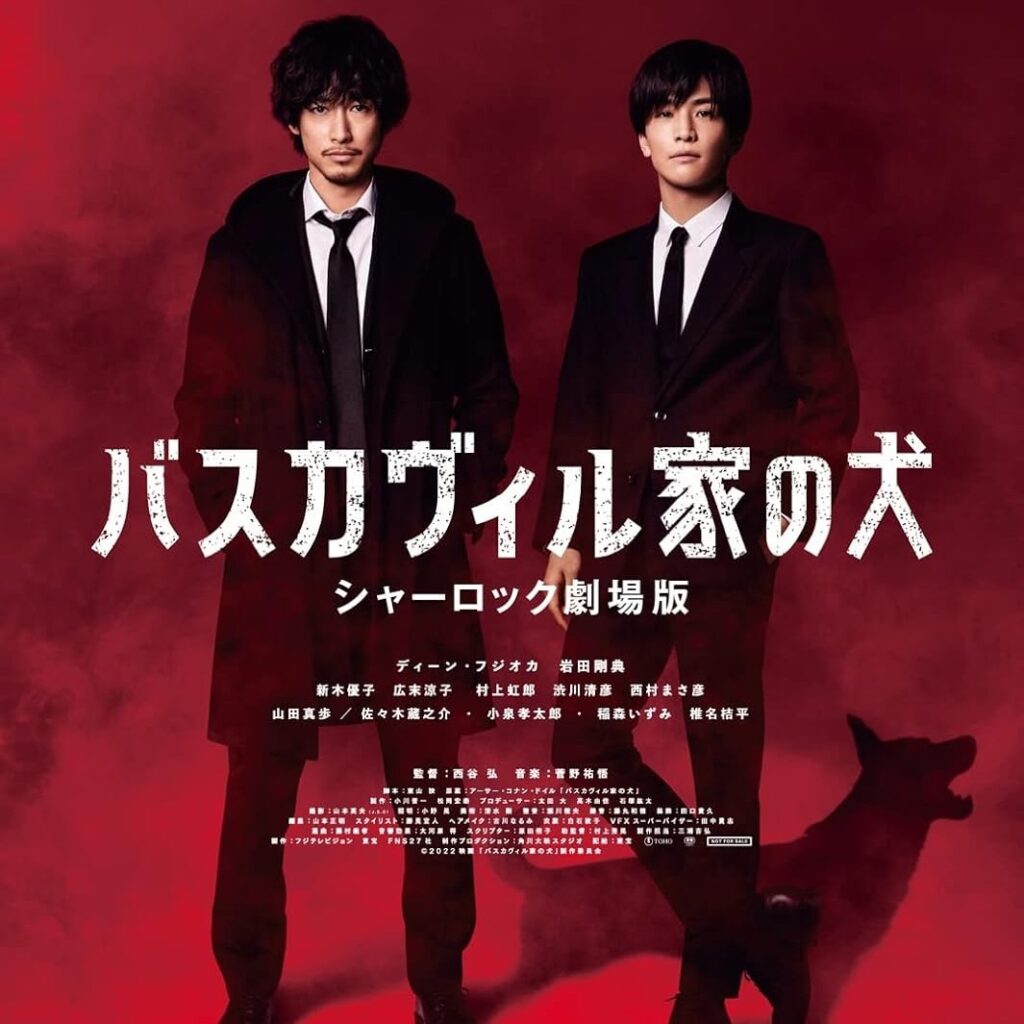映画「大怪獣のあとしまつ」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
巨大怪獣が突然死んだら、そのあとどうなるのか――そんな斬新な視点を描いたのが本作である。事前情報を見たときは「巨大生物の死体処理をどうエンタメにするのか?」と興味をそそられたが、鑑賞後はなかなか辛口の意見が止まらなくなってしまった。そもそも“怪獣が死んだあとの残務処理”という設定には独特の面白さを期待していたのだが、実際には肩透かしを食らった印象である。本編がはじまってみると、登場人物たちが必死に対策を練えているわりに、どこか観客としてはシラけた空気を感じてしまう場面が多かった。
一方で、キャスト自体は豪華であり、山田涼介を筆頭に実力派がそろっていたのは確かだ。にもかかわらず、設定の割り切り具合や物語の結末をどう落とし込むかといった点に関しては、いまひとつ踏み込んでいない印象が強い。結果的に「怪獣映画としてもパロディとしても微妙な立ち位置」に収まってしまい、鑑賞直後は頭の中にクエスチョンマークが浮かんだままだったという人も多いのではないだろうか。
本記事では、本編を通して見えてきた不完全燃焼な要素をあれこれ突っ込みつつ、「それでも気になる部分」を拾い上げて語っていきたいと思う。物語の重要ポイントも含めた内容を扱っているので、まだ観ていない方は注意してほしい。ここから先はネタバレが含まれるため、心して読み進めていただきたい。
映画「大怪獣のあとしまつ」の個人的評価
評価: ★☆☆☆☆
映画「大怪獣のあとしまつ」の感想・レビュー(ネタバレあり)
ここからは、上記評価にふさわしい本作の残念ポイントを中心に語っていく。まずは概要を振り返っておくと、ある日突然、街を蹂躙していた巨大怪獣がピタリと動かなくなり、まさかの“死亡”という状況に陥るところから物語がはじまる。通常の怪獣映画なら、「ヒーローが怪獣を倒して大団円!」だが、本作は“死体”の始末に着目した特撮エンターテインメントを謳っている。そこに期待を寄せた観客は多かったはずだ。
しかし蓋を開けてみると、興味深いアイデアをいまいち活かしきれないまま、展開が迷走してしまった感は否めない。まず、政府関係者が怪獣の死体処理をどうするかという政治的な駆け引きをコメディ寄りに描いているのだが、そのやりとりに鋭さが足りず、ずいぶん中途半端な印象を受けた。加えて、大臣や秘書官が一同に集まって会議をしているシーンは、それなりに“くだらない感じ”を狙っているのだろうとは思うものの、笑いのタイミングやテンポがどうにも合わない。
特撮作品として見た場合も、怪獣の存在感を活かした斬新な映像表現はあまり感じられなかった。たとえば死体がガスを放ったり、どこまで腐敗が進んでいるのかといったディテールは興味深いポイントであるが、そこに説得力がなかったり、コメディ演出に寄りすぎてしまった結果、リアリティよりも“思いつきのギャグ”のほうが優先されているように見えるのである。
さらに、脚本面で一番疑問に思うのは“ラストのオチ”だろう。主人公の帯刀アラタ(山田涼介)が奇妙な力を使って怪獣を空に連れ去る結末は、あまりにも説明不足で肩すかし感が強い。途中、彼が謎の存在であるような匂わせはあるのだが、結局そこを深く掘り下げずに終わるため、観客としては「何だったのかさっぱりわからない」という状態でエンドロールを迎えることになる。
この「わからない状態」のまま終わってしまうのが、本作最大のモヤモヤではないかと感じた。ミステリアスに終わらせる作品ももちろんあるが、本作の場合は“謎を謎のままに”というより“放り出したままに”見えてしまう。予告編で煽っていた「衝撃の結末」「ネタバレ厳禁」といった文句が逆効果になっている印象で、期待値を高めたわりに、実際の結末が拍子抜けだったことが、余計に失望感を増幅させているのではないだろうか。
キャストに目を向けると、主演の山田涼介は真面目さとカリスマ性を兼ね備えた雰囲気を持っており、画面映えは十分。土屋太鳳や濱田岳、西田敏行らも個性的なキャラクターを演じている。それぞれが何とか盛り上げようと頑張っているのは伝わるのだが、全体の調和が悪いのか、または脚本の段階で整合性を欠いたまま突っ走ってしまったのか、彼らの熱演が結果的に空回りしてしまったように感じる。
とりわけ残念だったのは、政治家たちのやりとりにコメディタッチを持ち込みながらも、皮肉や風刺をうまく使いこなせていない点である。「実は環境問題を逆手に取って利権に利用している」「怪獣の死体から新しい経済効果を生み出そうとしている」など、面白くなりそうな素材は散りばめられていたものの、その膨らませ方が弱く、単なる茶番劇に終わってしまった。どうせ振り切るならもっと徹底的に不条理劇を描ききってほしかったところだ。
加えて、怪獣の造形は「平成ゴジラ」シリーズなどに携わったプロが手掛けているため、いわゆる“着ぐるみ系怪獣”の持つ昭和的なあたたかみと、現代の特撮技術が融合している点は見どころのはずだ。だが、本編ではその魅力を存分に生かしきれていない。怪獣が死んでいる設定だから仕方がないとはいえ、動かないまま横たわる姿ばかりで、「これが新時代の特撮だ!」という驚きはさほど得られないのである。
また、終盤で突如としてヒーローのような展開が訪れたかと思うと、話はそれっきりで終わってしまう。振り返れば、主人公とヒロインの関係も十分に深掘りされぬまま、ほんの少しの会話と回想を挟んだだけで「そういうものか…」と強引に納得させられる部分が多かった。たとえるなら、三幕構成のうち二幕半ばで急に物語を打ち切られ、「はい、終わり!」と宣言されてしまったような印象だ。
それから「後始末」という肝心のテーマに関しても、言いたいことはわかるがどうも中途半端である。怪獣の膨大な死体を処理するためには、行政や軍、科学者などさまざまな機関の協力が欠かせないし、そこには利害や思惑が絡んでくる。そうしたリアルな課題を徹底的に掘り下げれば、ブラックジョーク満載の社会風刺劇として一気に化ける可能性だってあったはずだ。ところが、実際の描写はドタバタしているだけで、政治側の迷走ぶりを滑稽に見せようとしているものの、結局はスッキリしない。
本作は最初に掲げた「巨大怪獣が死んだらどうするのか?」というテーマが魅力的なだけに、製作陣の狙いが空転したように感じる。もしも、もっと真剣なパニック映画風に仕立ててから合間に笑いを織り交ぜるとか、あるいは『シン・ゴジラ』的な政治ドラマをベースにしながら強烈な風刺を効かせるなど、振り切った方向性をとっていれば、逆にカルト的人気を博したかもしれない。
それでも「観終わったあとのインパクト」だけは、それなりに強いという声もあるようだ。怪獣映画にありがちな高揚感や達成感ではなく、「なんだこの終わり方は……」という戸惑いが印象を残しているからだろう。別の見方をすれば、それこそが製作側の狙いだった可能性もゼロではない。観客を面食らわせるカオスな映画として記憶に残ることを狙ったのだとしたら、その点では成功したとも言える。
とはいえ、そうしたカオスを喜べる人は限られているのが正直なところである。かといって単純に娯楽作として大勢に推奨しにくい理由は、多くの要素を詰め込んだ結果、どれもが中途半端に終わっている点に尽きる。「大作怪獣映画」として見るのも違うし、「ナンセンスコメディ」として見るにしてもパンチ力が足りない。良く言えば“フリースタイル”、悪く言えば“まとまりに欠ける”という評価になりそうだ。
長時間かけて積み上げた物語が、ラスト数分の超展開で一瞬にして片づけられるのは、ある意味斬新かもしれないが、その過程を真面目に追ってきた観客にとっては、少し投げやりすぎると感じてしまう。だったら最初から突き抜けたギャグ路線で攻めてくれたほうが、まだ「笑いどころ」に素直に乗れた可能性もあるのではないか。
個人的には、もう少し丁寧にテーマを掘り下げれば面白い作品になり得たと思うので、そこが残念でならない。怪獣の死体をめぐる環境問題や軍事的リスク、一般市民の暮らしへの影響といったモチーフには、まだまだ未開拓のエピソードが眠っているはずである。上手く料理すれば、痛烈な社会風刺やディザスター映画として一級品になったかもしれないだけに、どうしても「もったいない」という言葉が浮かんでしまう。
以上のように、本作は「いろいろと惜しい部分が多すぎる怪獣エンターテインメント」と言える。評価としては★ひとつになってしまったが、逆に“珍作好き”や“奇抜な作品を楽しめる人”にとっては、話のタネとして観ておくのもアリかもしれない。むしろ、批判されがちな要素を含めて語り合うことで、人とは違った視点を見いだせる可能性は大いにある。
後味が良いとはいえない映画だが、何かしら話題を振りまいてくれるパワーは持っている。観客それぞれが“あとしまつ”に困惑するという意味では、ある種のインパクトだけはしっかり残してくれる作品だったといえるだろう。
映画「大怪獣のあとしまつ」はこんな人にオススメ!
いわゆる“大作怪獣映画”の常識を覆す視点が好きな人は要チェックである。怪獣の死体というありそうでなかったテーマは、それだけで独特の魅力があるし、制作者側の突飛なアイデアを追体験したいなら本作を外す手はない。どれほど残念な仕上がりだと言われようと、その奇抜さに興味をそそられるなら、一度は観てみる価値があるはずだ。
次に、映画鑑賞後にあれこれと批評したり、仲間内で盛り上がったりするのが好きな人にも向いている。いわゆる“ツッコミどころ満載”の作品なので、「ここはこうすればもっと良かったんじゃないか」「いや、このキャラクターの背景が薄すぎる」など、熱く語れる要素が多い。映画を観終わった後もネタが尽きないという意味では、ある種の楽しみ方ができるだろう。
そして、“珍作コレクター”を自負する人には、まさに好都合とも言える一作である。世の中には「完成度が低いからこそ逆に気になる」「人と違ったものを見たい」という好奇心旺盛な層がいる。本作はまさにそうした人の琴線に触れる可能性が高い。どこかハズし気味な展開や、説明不足のままぶん投げられるストーリーが、むしろ一部の観客にはたまらない味わいに映るかもしれない。
まとめると、本作を心から勧められるのは「常識外れの映画を面白がれる」「後日談として盛り上がれる話題性を求めている」「珍作の収集をライフワークにしている」といったタイプだ。先入観にとらわれず、突拍子もない展開を笑って受け止められる人であれば、意外な発見があるかもしれない。
まとめ
本作は「怪獣が死んだあとの処理」を描くという斬新な発想を打ち出しながらも、ストーリーやキャラクター描写の詰めが甘く、観る側を困惑させてしまう部分が多かった。序盤こそ目新しさで興味をひかれるが、終盤の展開は説明不足のまま急に幕を引いてしまい、どうにもモヤモヤが残る仕上がりだと感じる。豪華なキャストがそろっていただけに、もう一歩踏み込んだ演出や脚本の練り込みがあれば、全く違う評価を得られたかもしれない。
しかしながら、観終わったあとに「これは一体何だったんだろう」と考え込んでしまう不思議なインパクトを持つのも事実である。そのイレギュラーな作りに興味をそそられる観客や、あえて“外し”の要素を味わいたい人には、ある種の面白さも感じられるのではないだろうか。たとえ評価が低めであったとしても、人によっては「むしろそこがツボだった」と語りたくなるような破天荒さが隠れているのが本作の特徴だと言える。
いずれにせよ、巨大怪獣の“あとしまつ”という発想を表舞台に出した点は評価に値する。今後、同じテーマをより洗練した形で描く作品が登場したら、それはこの映画が残した足跡の一部かもしれない。