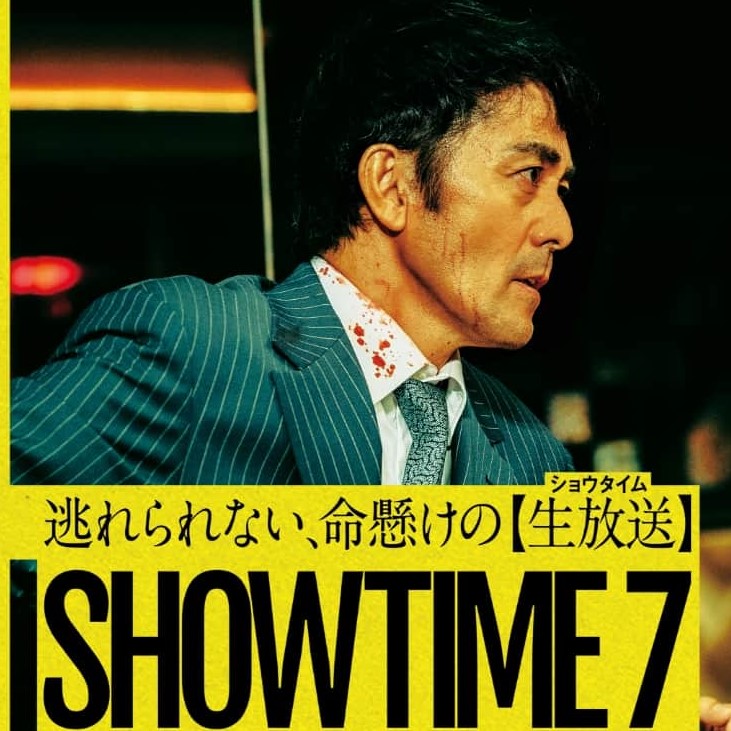映画「ブルータリスト」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
第二次世界大戦の戦禍をくぐり抜けた主人公が、アメリカの富裕層と激突しながら建築プロジェクトを完遂しようとする姿は、シリアスでありながら妙にあけすけな部分もあって一筋縄ではいかない。とはいえ冒頭から自由の女神がひっくり返った絵面が出てきたり、やたらと壮大なアングルで撮ったかと思えば、どこかでツッコミたくなるシーンも散見されるので、ただ重苦しいだけでは終わらないのが厄介だ。実在の人物かと見まがうほど丁寧に作り込まれた設定や、長時間上映を彩る派手な演出が目を引くいっぽう、細部に潜む違和感や不自然さが後々になって効いてくる。
そんな“正体不明”な魅力をまとった作品ゆえ、一度観はじめたら休憩を挟んでも目が離せない。好き嫌いは分かれるかもしれないが、“長さも含めてエンタメ”を体感したいなら一度は挑んでみる価値があるだろう。
映画「ブルータリスト」の個人的評価
評価:★★★★☆
映画「ブルータリスト」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本編は3時間半を超える大作でありながら、途中で15分ほどの休憩が挟まれる構成になっている。最初は「そんなに長いなら大丈夫かな…」と身構えてしまうが、実際に観てみると意外にテンポが良く、気づけばエンドロールを迎えていた、という声も少なくない。ただ、そこには一種の“トリック”が仕掛けられているように思える。
まず物語の発端である。ハンガリー系ユダヤ人の建築家ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)が、ナチスによる迫害から逃れた末にアメリカへ渡るところから幕を開ける。自由と希望の象徴であるはずのニューヨーク港に到着したはずが、カメラはなぜか逆さにそびえる自由の女神像を捉える。そこには「移民たちを受け入れる慈悲の国」どころか、“ひっくり返った世界”へ飛び込むかのような嫌な予感が漂うのだ。実際、物語が進むとその予感は大当たりで、ラースローは再会を望む妻や姪を呼び寄せる前に、いきなり金持ちの実業家たちからのし上がるよう迫られる。さらに言葉が通じない、あるいは通じても噛み合わないアメリカ社会で、多くの軋轢を生むことになる。
物語の核をなすのが、大富豪ハリソン・ヴァン・ビューレン(ガイ・ピアース)との奇妙な主従関係である。ラースローは建築家としての才能を買われ、ハリソンの所有地に巨大なコミュニティセンターを建てる依頼を受ける。ところがハリソンは、自分の“ペット”同然にラースローを扱う場面が度々見られる。アメリカの土着的な宗教観やカネの力で、ラースローの建築プランをやたらといじり回そうとするのも日常茶飯事だ。もっともラースローも受け身一辺倒ではなく、口では従っている風を装いつつ、密かに自分の信念を貫こうとする。ときにそのしぶとさは暴走に近く、現場の労働者たちを振り回し、周囲の黒人仲間との友情まで危うくしてしまう。
注目なのは、ラースローの設計するコミュニティセンターが、ホロコーストでの収容所の空間を下敷きにしているという事実だ。これが作品後半の“からくり”として明らかになっていく。劇中で細かく映されるコンクリートむき出しの壁や、妙に閉塞感を与える通路、視界の悪い構造などは、全て彼がかつて体験した絶望の場を変形させたものだという。ラースローにとっては、失われた尊厳や弔いきれない記憶を“建築”という手段で回収しようとする必死の行為であり、それを知らないハリソンは「新しい様式」と称賛しながら金を出し続ける。つまり、このコミュニティセンターはホロコーストの象徴でもあり、アメリカ流の“夢”をねじれた形で具現化する舞台でもあるわけだ。
観客としては、そんなラースローの心情を理解しつつも、「あれ、ハリソンに対抗するわりに、この人も相当ひどいな」と思わずツッコミを入れたくなるシーンが多々ある。たとえば古くからの仲間を簡単に切り捨てたり、妻の心身がボロボロなのに事業を最優先にしたりと、正義の味方とは言いがたい。だが、この複雑さこそが映画全体の妙味である。戦争や迫害をくぐってきた人間が、その傷を抱えながら新天地で必死に生き延びようとする裏には、泥臭い面やモラルとの衝突が必ずと言っていいほど付きまとう。あくまで気高い被害者としてだけ描かれない主人公像は、観る側にも「果たして誰が本当に加害者で、誰が被害者なのか」という問いを投げかけてくる。
この作品が厄介なのは「やけにリアリティがあるのに、実在のエピソードとは言いきれない」という点だ。劇中で提示される年表や、バウハウスとのつながり、ペンシルベニア州にあるというコミュニティセンターの実在感が妙に具体的なわりに、調べてみると出どころがはっきりしない。さらに物語のラストで描かれる「イスラエルで行われた建築展」のドキュメンタリー風フッテージは、まるで本人映像のように見えつつ、よく見ると小道具めいた安っぽさを醸している。つまり観客は、「これは実話をベースにした作品なのか? それともフィクションをでかでかと飾っているのか?」と戸惑わされる構造になっているのだ。
それを象徴するのが、終盤で姪が行うスピーチである。そこでは「大切なのは道のりではなく到達点」と言いきってしまう。通常、重厚な歴史劇なら「ここに至るまでの苦労こそが重要だ」とまとめそうなものだが、姪はラースローの人生を手短に語り「結果こそが本懐だ」と結論づけるのだ。4時間近くかけて見せられた苦闘や紆余曲折が、そっくりひっくり返されるような展開である。これを聞いたとき、素直に感動できる観客もいれば、「さっきまでの苦労はなんだったんだ」と苦笑する観客もいるだろう。
実際、映画のエンドロールでも軽妙な音楽が流れはじめ、「深刻だったはずのドラマをそこまで軽く扱っていいのか?」と思うほど拍子抜けな雰囲気になる。いわゆる“実話ベース映画”でよくある「モデル本人のその後を紹介する映像」と同じ流れに見せかけて、微妙にチープな仕上がりで終わらせるあたり、作り手側の意地悪な狙いを感じざるを得ない。こうしたフェイク感をまぜこぜにした大作だからこそ、絶妙に観る者を振り回してくるのだ。
では、この作品が訴えかけるものは何なのか。一見するとホロコーストを題材にした“被害者の叫び”に見えるが、蓋を開けると金持ちの横暴やアメリカの保守主義、あるいはユダヤ人の内部矛盾までチラつかせながら、観客に「真実って何?」と問い続ける実験的な姿勢が浮かび上がる。ほとんど漫才のボケとツッコミのように、大袈裟なエピソードで感情を揺さぶったかと思えば、カメラが意図的に肝心の場面を外したり、時系列を飛ばして別の視点を見せたりする。結果、「語られない部分こそが本質なのでは?」と感じた瞬間に、すでにもう次の展開で意表をつかれる。この繰り返しが観客の脳内をぐるぐるかき回す。
そして長い上映時間が終わる頃には、「これは正真正銘のドキュメンタリーではない」「ひょっとすると全部盛大なフィクションかもしれない」という疑念を持ちながらも、不思議と胸に残るものがある。作品の本質は歴史再現よりも、“作られた記憶”や“語りの力”を浮き彫りにすることなのだ。人間は、痛みや傷の物語を耳にすると共感を抱きやすい。そこに壮大な演出やそれっぽい資料映像を差し込めば、事実と勘違いするほどに感動してしまう。逆に言えば、それほどまでに“語り”と“映像”には人を引き込む力があり、裏を返せば操作も容易だという警鐘を鳴らしているのではないか。
ラースローの描き方も同様で、言うなれば“悲劇の天才”という像を巧妙に作り込むことで、観客に「不器用だけれど高潔な芸術家」を信じ込ませる。しかし劇中の行動を冷静に振り返ると、彼自身が周囲を軽視し、他者を利用し、時には野心に溺れている姿がそこかしこに見えてくる。妻との間に生まれる亀裂、黒人労働者への横柄な態度、パトロンに対する屈折した従属と反発。こういった人間的な醜さは、単に“悲惨な過去がそうさせる”と説明できるような単純さではない。
観終わったあと、多くの人は「これは何だったんだろう」とぼんやり考え込むかもしれない。歴史的建築や戦後移民、富裕層の横暴に当時の社会問題など、大きな題材を詰め込んだようでいながら、どこか“壮大なフリ”をされた感じが拭えない。あえて言うなら、この映画自体が「フィクションの力」を使って観客を巻き込み、それを利用して“真実らしきもの”を作り出す実験をしているようにも見える。だからこそ、3時間半という長尺と休憩を挟む体験そのものが、観客の没入感を上手に生み出す仕組みになっているわけだ。
結果として、本作は観る側に何度も「こんなに悲惨で壮大なドラマ、実は本当にあった出来事では?」と錯覚させる。しかし、エンドロールの軽妙さと途中散りばめられた齟齬が、「いやいや、これ全部作られてるかもよ?」と耳打ちしてくる。最終的に「到達点だけが大事」とささやかれ、「じゃあ俺たちが3時間半もかけて見守ってきた壮絶な過程はなんだったんだ…」と肩透かしを食らう。だが、それこそが作品の狙いなのだろう。人が“物語”に飛びつくとき、いかに流されやすく、そしていかに感情移入しやすいのか。その危うさと魅力を同時に突きつける狙いがあると感じる。
だから、この映画はただの“重たい戦争ドラマ”でもなければ“芸術家の伝記”でもない。不確かなプロパガンダをわざと引き延ばしてみせることで、「真実とは何か」「誰が物語を支配しているのか」を問う、ある種の挑発である。観客はその空気を感じ取りつつ、一方で長い上映時間の退屈を上手に回避するための演出(インターミッションや気取った音楽、過剰に豪華なセット)に笑わされてしまう。いわゆるクラシカルな実録映画に見せかけて、実のところかなりアバンギャルドな仕掛けが潜んでいるわけだ。
そう考えると、評価の★★★★☆は単純に「感動した」という意味だけではない。「やられた」という感覚や、見たことのないスタイルの映画体験をさせてくれた面白さ、そして観る人によっては不愉快に感じるかもしれない刺激的な要素が混ざり合った結果の評価だ。ストレートな感動を求める人にとっては「なんだこれは」という感想を抱くかもしれないし、逆に、映画の実験性や意外性を好む人には「これはクセになる」と感じられるかもしれない。とにかく、3時間半+休憩という時間に見合うだけの“摩訶不思議な体験”が味わえることは確かである。
映画「ブルータリスト」はこんな人にオススメ!
まず第一に、長時間の映画でも集中力が持続する人には強く推せる。インターミッションがあるとはいえ3時間半というボリュームがあるため、「一気に深く入り込みたい」「日常を忘れて映画の世界にひたってみたい」というタイプの人にハマるだろう。加えて、ただ感動したいだけでなく「作品の背景を疑いながら観る」「裏を読んでみる」という観賞スタイルが好きな人ほど楽しめるはずだ。表向きは壮大な移民と芸術の物語に見えるが、本当のところ何を語っているのかが一筋縄ではいかないからだ。
海外の大手スタジオ作品だけでなく、ちょっと変わった作家性の強い映画を追いかけたい人にも適している。ドキュメンタリーとフィクションの狭間を行き来するような不思議な空気感があるので、「斬新な構成」「作り手のひねくれた意図」を探るのが好きな人にうってつけだろう。加えて、厳粛な歴史ドラマと思いきや唐突に挿入される刺激のある描写があったり、妙な小道具が登場したりするなど、画面の情報量も多い。観客の中には「いまのセリフって、本音なのかフェイクなのか?」と考えるのが楽しくなるはずだ。
その一方で、歴史的正確さを求める人や、わかりやすい成長物語だけを求める人には合わないかもしれない。あちこちにちぐはぐな部分やご都合主義的な流れもあり、それを「計算づくの仕掛け」として楽しめるかどうかが鍵になる。いずれにせよ、一度観ておくと話題性も相まって、語り合うネタには困らないタイプの作品である。
まとめ
振り返ってみると、映画「ブルータリスト」は“重苦しい移民ドラマ”や“巨匠の伝記映画”など、単純なジャンル分けが通用しない不思議な一作である。3時間半という長尺、強烈な映像表現、そして妙にリアルでありながらどこか疑わしい設定が相まって、観客の予想を大きく裏切る仕掛けを多数盛り込んでいる。
そして物語のクライマックスで突きつけられる「結局は結果がすべて」というドライな台詞は、今まで必死に追体験してきた道のりを否定するかのようだ。だからこそ、観終わってから「本当に真実だったのか」「どこまで計算ずくなのか」とあれこれ考えさせられる。そうした“観客の脳内で続いていく映画体験”こそ、本作の醍醐味ではないだろうか。長尺におよぶ迫力の映像と騙し絵のようなストーリーに興味があれば、一度挑戦してみる価値は十分にあるだろう。