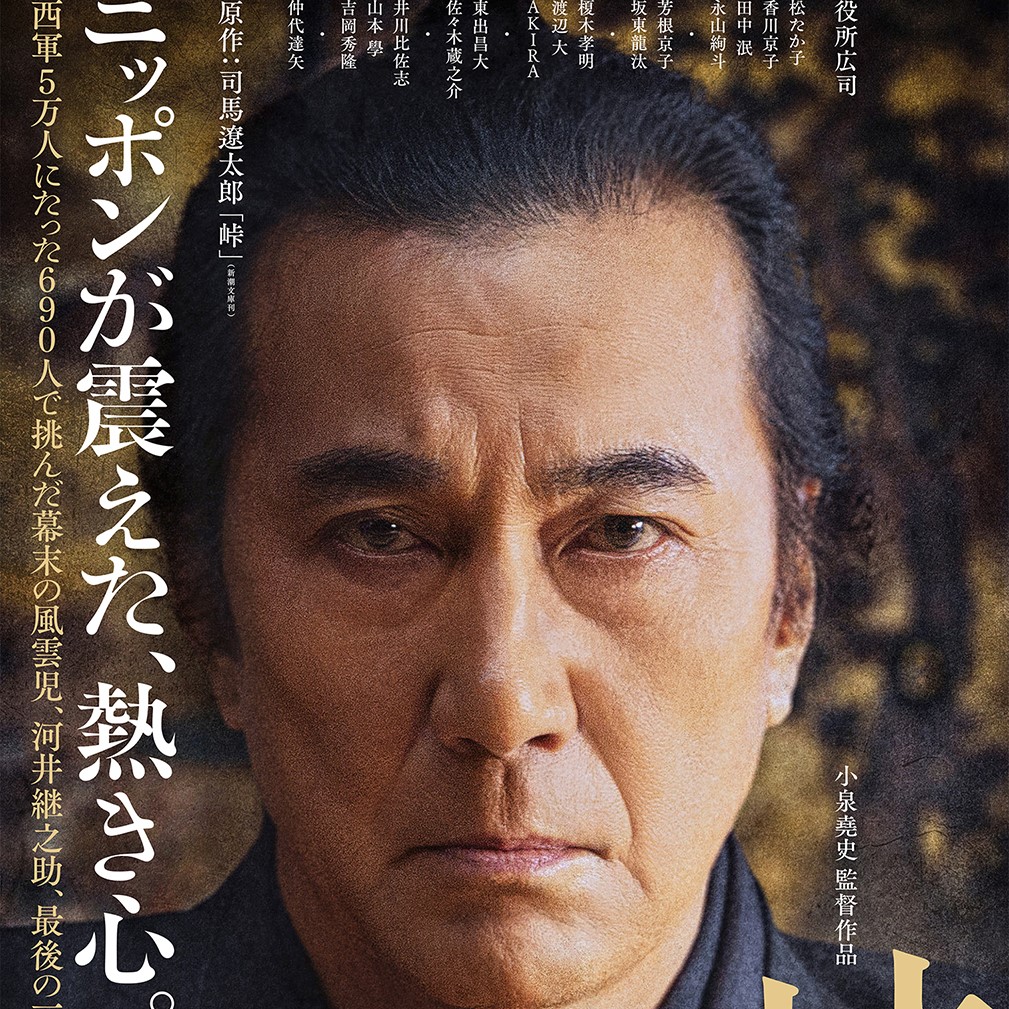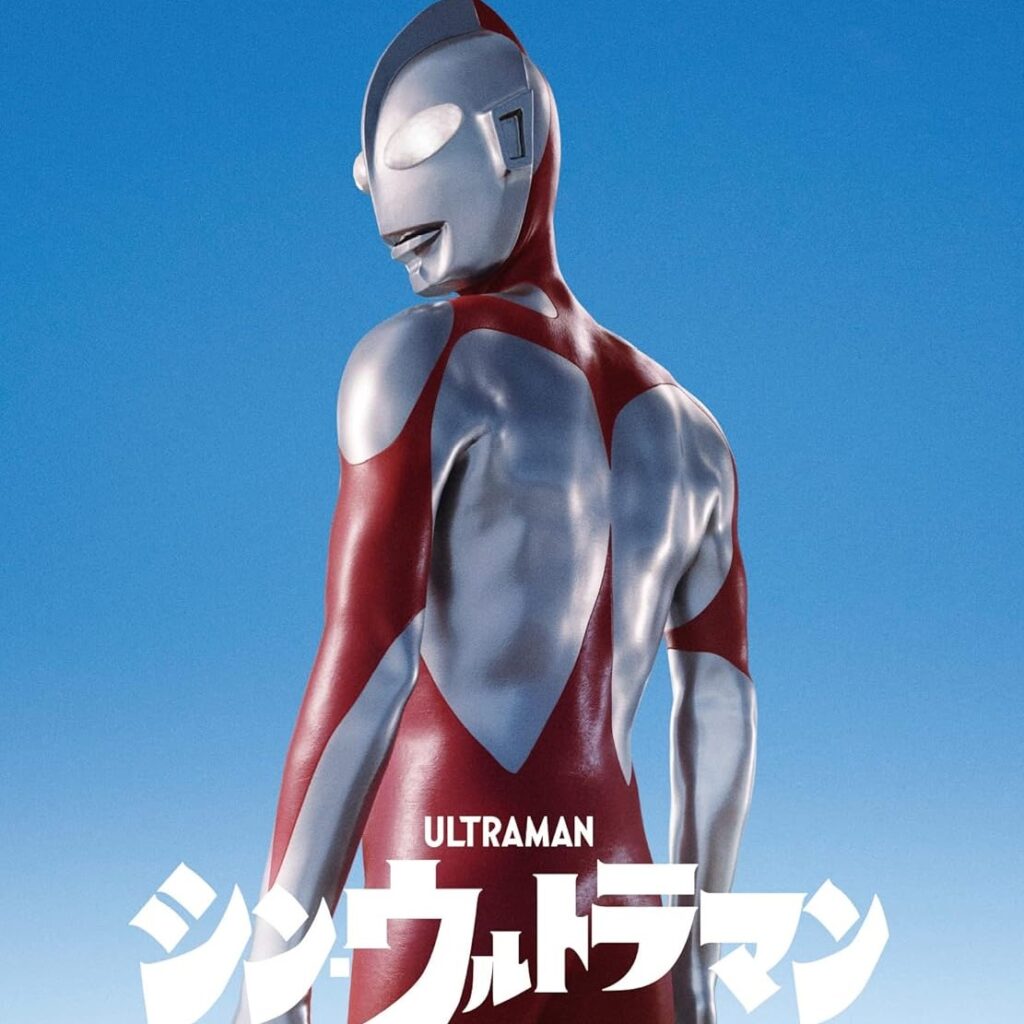映画「そばかす」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
三浦透子が単独主演を務めるこの作品は、恋愛感情や欲求を持てない女性が主人公である。タイトルにもある「そばかす」という響きからは一見ポップな雰囲気を連想するが、その内側には“当たり前”に埋もれがちな多様な価値観が詰まっている。主人公は30歳にして恋人いない歴=年齢を堂々更新中。普通に見られることへの抵抗や、家族の世話焼き攻撃に翻弄されながらも、自分の居場所を探す姿がじわりと胸を打つ。
さらに、前田敦子や伊藤万理華といった豪華キャストも物語を盛り上げ、地味なようでいて刺激にあふれた展開が続くのだ。新しいヒロイン像を提示するこの映画には、共感と驚きの連続が待ち受けている。ここでは、物語の核心に触れつつ本編の見どころやキャラクターの魅力を存分に語っていく。少しだけ肩の力を抜いて、ふと笑えるポイントを見つけながら読んでほしい。なにしろ、恋がすべてじゃないという主張は一見シンプルに見えて、じつはとびきり奥深いのだ。
チェロ演奏や斬新な紙芝居シーンなど、ユニークなエピソードも盛りだくさん。この作品を通して“自分らしく生きる”とは何なのか、一緒に考えていこう。
映画「そばかす」の個人的評価
評価:★★★★☆
映画「そばかす」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本編の冒頭から、主人公である佳純(三浦透子)の“恋愛に無頓着”っぷりが全開である。幼い頃からチェロの演奏に打ち込んできたものの挫折を経験し、地元の実家で淡々と暮らす彼女は、世間一般の「恋に落ちるのが当然」といわんばかりの風潮に若干の居心地の悪さを感じている。その背景には、「恋人ができなくて寂しいんじゃないか」という家族や周囲の過剰な気遣いがあるのだが、佳純からすれば「いやいや、特に必要性を感じないのだが…」というスタンスである。この温度差がなんとも絶妙で、開始早々に“わかる”人は大いにうなずき、“わからん”人は「そんな価値観もあるのか」と目を丸くすることだろう。
物語が本格的に動き始めるのは、母親(坂井真紀)の粘り強い“お見合いブートキャンプ”がきっかけだ。本人の意思とは無関係に、親子で婚活イベントに参加させられるという荒業が炸裂する。佳純としてはたまったものではないが、母親にとっては「娘が30歳過ぎても恋人の気配すらないなんて、どうにも落ち着かない」という思いが強いらしい。ここが笑いどころでもありつつ、ある意味では「結婚しないと不安」と思い込む家族の古風な一面を示している。本人が「自分は恋愛感情を抱けない」と言っても周囲に響かず、むしろ「本当はその気があるくせに」「理想が高いのでは」と勝手に決めつけられるのだ。いわゆるマジョリティーの常識が、佳純という存在をまるっと見落としている状況である。
そんな彼女の前に現れるのが、同級生や偶然の出会いを通して再接近する人々である。まずは見合い相手の木暮(伊島空)。彼も最初は「結婚なんか興味ない」と公言していたはずが、いつの間にか佳純に惹かれてしまう。そこがまた普通の恋愛映画っぽい展開なのだが、相手からすると自然な「好きになった」という感情も、佳純には「え、そういう風に変化するものなの?」とピンとこない。この齟齬が見事に描かれていて、そもそも両想い前提でないアプローチが彼女には理解不能なのだ。その結果、同じ“結婚興味なし”仲間だと思っていたのに「あれ、なんでキス未遂になってるんだ? その気はゼロだけど」となり、彼を怒らせてしまう。本人に悪気はまったくないが、恋愛を基本路線とする世間と“噛み合わない”苦しさがじわじわと浮き彫りになるわけだ。
さらに、保育士として働く同級生・八代(前原滉)との再会も大きなポイントである。彼はゲイであることを佳純に告白するが、佳純は「ふーん、そうなんだ」とごく自然に受け止める。ここが面白いのは、お互いに「少数派」であるがゆえに、普通なら引かれがちな告白にも「別に変ではない」とサラリと答えられる関係だということ。普通のラブストーリーなら「それが恋に発展するのか?」とドキドキする局面だが、佳純からしてみれば、ゲイだろうが何だろうが「自分には関係ない」というスタンス。むしろ“恋バナ”自体が自分には異世界のようで、改めて「あれ、恋愛ってそんな必然的なものなの?」と疑問が膨らむのだ。周囲からは「人を好きになれないなんて変わってる」と見られがちなところ、八代は「お前ならあんまり驚かないかなと思って言った」というしれっとした態度で、それがまた佳純を安心させる。いわゆるLGBTQ作品として描かれるケースでは、当事者の苦悩や差別との闘いがメインテーマになりがちだが、この作品では「みんな本質的にいろいろ抱えつつ生きている」という大枠に溶け込んでいるのが特徴だ。
しかし、それ以上に佳純の人生をかき回す存在がいる。それが前田敦子演じる世永真帆だ。彼女はかつてAV女優として名を馳せていたというバックグラウンドを持ち、地元に戻ってきたところで佳純と再会する。真帆は中学時代から“枠にとらわれない”闊達さを持っていて、教師に食ってかかるほどストレートに意見を言うタイプ。恋愛や性をめぐる価値観もオープンで、とことん「私はこう思う!」と発信していく。その姿は、恋愛感情を持たない佳純にとってまぶしいくらい奔放に映るのだが、不思議なことに二人はあっさり意気投合してしまう。真帆のありのままを受け入れる佳純と、佳純を一切否定しない真帆の関係性は、まるで気楽な同居人のようでもあり、一線を越えた特別な友情にも見える。周囲の誤解を招きそうな雰囲気満載であるが、それこそが本作の面白さでもある。
その後、佳純が保育園で“紙芝居”を披露する展開が訪れる。これがまた本作のハイライトとも言える場面で、童話の定番「シンデレラ」を佳純流に書き換えた紙芝居が炸裂するのだ。王子様と結婚してハッピーエンド…という筋書きを疑問視する佳純は、「そもそもシンデレラって何で結婚しなきゃいけないんだ?」と考え、真帆と協力してオリジナル版を作り上げる。しかし、本番で見守る保護者や真帆の父親(地元の政治家)から「そんなの子どもに見せていいのか?」と疑問や批判の視線が飛び始めると、佳純は一瞬で怖じ気づき、途中で上映を中断してしまう。子どもたちは「続きはどうなるの?」と目を輝かせているが、周囲の大人たちが「型から外れた価値観」を警戒しているように感じ取った佳純は、思わず退いてしまうのだ。自分の新しい世界観を大勢の前で堂々と主張するにはまだ勇気が足りない。この中断シーンこそが、恋愛感情をもたない佳純が社会の中で縮こまってしまう瞬間を象徴していると思われる。
そして真帆は、そんな状況に納得がいかず、怒りにまかせて父親の選挙演説に突撃する。父親に対しての不満は彼女自身が長年抱えてきたものでもあり、「私たち少数派を排除するな!」という痛快な叫びになっている。ただし、それで完全に解決するわけでもなく、真帆にもまた“自分なりの幸せ”を追い求める事情がある。物語後半で、真帆は東京にいる恋人と復縁し、結婚へ向かうことを決める。「じゃあ一緒に住もうよ!」とまで盛り上がっていた佳純は拍子抜けだが、真帆の幸せを否定する理由はない。そこに「誰でも恋愛するものだと思うなよ!」と啖呵を切ってきた佳純が、むしろ大切な存在の選択を後押ししている構図があるのだ。一瞬だけ「裏切られた?」と思う気持ちも滲みつつ、最終的に佳純は真帆を祝福し、自分は自分で踏ん張っていくことを決意する。
佳純の家族関係も見どころのひとつだ。恋愛体質の妹(伊藤万理華)は、結婚して妊娠中という“安定ルート”に乗っているようでいて、実は夫の浮気を疑い始めていたりする。祖母(田島令子)はバツ3という派手な経歴を持ち、母(坂井真紀)は佳純に無理やり見合いをさせるほど結婚を推進したがる。父(三宅弘城)はやや鬱気味で仕事を離れている。それぞれに抱える事情があり、食卓では時に大ゲンカに発展。妹に「本当はレズビアンなんじゃないの?」と疑いを投げかけられてカッとなる佳純だが、「好きになれない」という感情を説明するのはとても難しく、周りからは「自分でも気づいてないだけでしょ」と片付けられがち。家族同士だからこそ遠慮がなくぶつかり合うのだが、そのぶつかり合いが本当の理解に繋がるのかどうかは、見る人によって解釈が分かれるだろう。
ただ、後半のあるシーンで父が「自分も本当にやりたいことがあるから仕事を辞めようと思う」と言い出し、そこに家族全員が「急にどうした」と呆れつつ、最終的に笑ってしまう場面がある。これは佳純が「自分らしく生きたい」と訴えてもなかなか認めてもらえなかった家族関係が、少しだけ変化を遂げるきっかけとも言える。家族も結局「みんなそれぞれやりたいことをやればいいじゃん」と思い始める瞬間なのだろう。大きく劇的に何かが変わるわけではないが、人々が少しずつ“枠”を緩めていくプロセスが、この作品の醍醐味だと感じる。
また、終盤で北村匠海演じる天藤が登場し、佳純に「映画を観に行かないか」と声をかけるシーンも興味深い。いよいよ「新たな恋の予感か?」と思いきや、佳純は「自分は恋愛が無理なんだ」と即答する。ところが天藤は「いや、自分も似たようなものだから、そのシンデレラ紙芝居を見て嬉しくなったんだよ」と言う。この交流が示唆するのは、恋愛感情を持たない者同士が出会い、分かり合う可能性があるということだろう。しかも、そこに“恋愛”という要素はなくとも「分かる人がいる」というだけで前を向ける。王子とお姫様の結婚が必ずしもゴールではない新しい物語は、同じ悩みを抱える誰かにとって確かな希望になるのだ。
監督の玉田真也と脚本のアサダアツシは、これまでも多面的な恋愛観や人間模様を描くのが得意なコンビである。今回はさらに一歩踏み込んで、恋愛至上主義の外側にいる人間の視点を軸に据えた。一歩間違えると重苦しい社会派映画になりそうな題材だが、本作は軽やかな空気感を漂わせている。ここには三浦透子の存在感が大きい。小柄で儚げな印象を抱かせるが、芯の強そうな瞳で「自分は恋愛しない」ときっぱり言い切る潔さが何とも頼もしい。ともすれば周囲の人々が騒がしいだけに見えてしまう世界の中で、マイペースに淡々と生きる姿が、この作品の魅力を引き立てている。
また、タイトルの「そばかす」は、佳純の名字「蘇畑(そばた)」をもじって呼ばれる彼女のあだ名でもある。そばかすは肌にちらほら現れる小さな色素沈着だが、それをコンプレックスと捉える人がいる一方で、チャームポイントとして楽しむ人もいる。そういった「他人とはちょっと違うかもしれない部分」をどう捉えるか、本作のテーマを象徴するタイトルと言えよう。世間の常識からすれば“恋愛をしないなんて”と眉をひそめられるが、佳純にとっては「この生き方が自然」なのだ。そばかすを受け入れるように、自分の気持ちも否定せず大切に扱う姿は、多様性が叫ばれる時代のなかでもなお孤独を感じている人にとって救いになるはずだ。
物語は大きな事件が起こるわけではなく、佳純が少しずつ周囲と噛み合ったり衝突したりしながら、最後に一歩前へ進むところで終わる。真帆の結婚式でチェロを弾ききったあと、「もう音楽はやめようかな」と決断する佳純は、自分を縛っていた過去や周囲の期待を手放すように見える。そこには恋愛感情を持たない自分を受け入れ、認める覚悟が宿っているようだ。恋人を作るかどうかだけが人生のすべてではない。もっと言えば「恋人は要らない」という価値観だって立派な個性だ。そのメッセージを堂々と発信する作品は、ありそうでなかったのではないか。だからこそ、本作は新しいヒロイン像を提示するだけでなく、観る者に「自分はどう生きたいか」を問いかけているように感じる。
本作を観ていると「みんな違ってみんないい」などという言葉が陳腐に思えるほど、実際のところは違いを受け入れるのが簡単ではないと痛感させられる。佳純は家族の押しつけに悩まされ、見合い相手から激怒され、自分の大切に思う紙芝居を公衆の面前で止めてしまう。彼女のような価値観に“賛同”してくれる人は少なく、むしろ大多数からは「そんなんあり得ないでしょ」と敬遠されるのが現実だ。それでも、本作は暗さを前面に押し出すわけではなく、むしろ「それってちょっと不器用だけど面白い人生じゃないか」と言わんばかりの開き直りを感じさせる。恋愛しない=不幸というわけでもないし、恋にのめり込む=幸福とも限らない。それを軽妙に描いた点こそ、本作の妙味だ。
さて、最終的に佳純は天藤からの誘いで映画を観に行く。そこに恋愛ムードは皆無だが、何とも言えない連帯感が漂っている。自分と似た感覚を持つ人がこの世にいるだけで、少しだけ肩の力が抜けるものなのだ。その感覚を味わうラストシーンは、恋愛映画に慣れていると「え、そこで終わり!?」と驚くかもしれない。だが、佳純がこれからどんな道を歩むのかは、ある意味では我々観客に委ねられている。恋愛をしなくても人生は豊かだという主張を示しつつ、「でも、もしかして何か新しい形があるかもよ?」という希望の匂いを漂わせる絶妙な締め方が秀逸である。
振り返ると「そばかす」は、恋愛をテーマにした作品が飽和状態にある映画界で、一歩踏み出した存在と言える。物語自体は地味に見えるかもしれないが、そのメッセージは意外と強烈だ。恋愛感情を否定するつもりも、肯定するつもりもない。ただ「自分にとって何が一番しっくりくるか」を大事にしていいんじゃないか、とそっと背中を押してくれるのだ。だからこそ、最後に佳純が自然な笑みをこぼす姿は感慨深い。結局のところ、本作が掲げる新しいヒロイン像は、自分らしさを武器にどこまでも自由に生きる存在。その姿を見ていると、恋愛に興味があってもなくても、自分なりの生き方を改めて考えたくなるだろう。
映画「そばかす」はこんな人にオススメ!
本作は「恋愛が全てではない」という当たり前のようでいて、あまり語られてこなかったテーマを正面から描いている。したがって、いわゆる“恋バナ”で盛り上がるのが苦手な人や、「周りが恋愛至上主義っぽくてしんどい」と感じる人には絶対に刺さるだろう。「自分っておかしいのかな?」と悩み続けてきた人ほど、この作品の空気感にほっと肩を撫で下ろすに違いない。とはいえ、恋愛を否定しているわけではなく、「そういう生き方もアリだよね」と素直に広げていくスタンスなので、逆に恋愛が大好きな人にも新鮮な視点を与えてくれる。
加えて、「家族や周囲からのプレッシャーに悩む人」にもオススメである。独身でいるだけでやたら説教されるとか、「いい歳なんだから早く相手を見つけなきゃ」と急かされるとか、思い当たる節があるなら佳純の気持ちを深く共感できるはずだ。特に地方に住んでいると、親族や近所の目もあってプレッシャーが倍増するケースも多い。本作はそんな“お節介”な環境を笑いと緊張感を織り交ぜながら描いており、「こんなに気が合わないのになんで皆は当たり前みたいに結婚へ向かうのか?」という疑問を抱く人の背中を後押ししてくれるのだ。
さらに、多様性という言葉が急速に広がる昨今、「本当に受け入れられているのか?」と不安に思っている人もいるだろう。本作はAセクやゲイといった性的マイノリティの姿を、あくまで“普通の人間”として描いているのが魅力である。だからこそ、自分を隠しながら生きている人にも大きな共感が生まれるはずだ。作中では物事がすんなり解決するわけではないが、「こんなに多種多様な生き方があるんだ」と感じさせてくれるだけでもかなり救われる。
最後に、“ガッツリした劇的展開”を求めている人よりも、“淡々とした日常の中にじわじわと変化がにじむ物語”を好む人に合っている。派手なアクションや過剰なロマンスは少なめだが、そのぶん感情の変化や価値観のすれ違いが繊細に描かれているので味わい深い。笑いながら(あるいは呆れながら)観ていたら、いつの間にか佳純や真帆、そして家族の行動に引き込まれ、「自分だったらこうするかな」と想像を巡らせてしまうはずである。
要するに「恋愛至上主義に疲れた人」「自分なりの幸せって何だろうと考えたい人」「家族や社会との温度差に戸惑っている人」「静かにでも確かな変化を描く作品が好きな人」には全力で薦めたい一作だ。
まとめ
本作は、恋愛をしない主人公というインパクトある設定を軸に、多様な生き方とそのギャップを浮き彫りにする内容である。
佳純の「恋人がほしくない」という感覚は周りからは奇異の目で見られがちだが、その一方で「真っ当な道」とされる生き方にもほころびがあることが丁寧に描かれている。必ずしも明確な落としどころを示すわけではないが、だからこそ観る側は「恋愛って絶対必要なのか?」と自然に問い直したくなる。三浦透子の繊細な演技や、前田敦子の奔放でまっすぐなキャラクターが相まって、物語のリアリティを一層強く感じさせてくれるのも魅力だ。
大きな事件や大団円のハッピーエンドがあるわけではないが、それでも深い余韻を残していく作品である。恋愛が人を幸せにすることもあれば、縛り付けてしまうこともある。そんな当たり前のようで曖昧だった点をはっきり突き付けてくるのが「そばかす」だろう。自分の価値観にちょっとした風穴を開けたい人は、ぜひ一度体験してみてほしい。