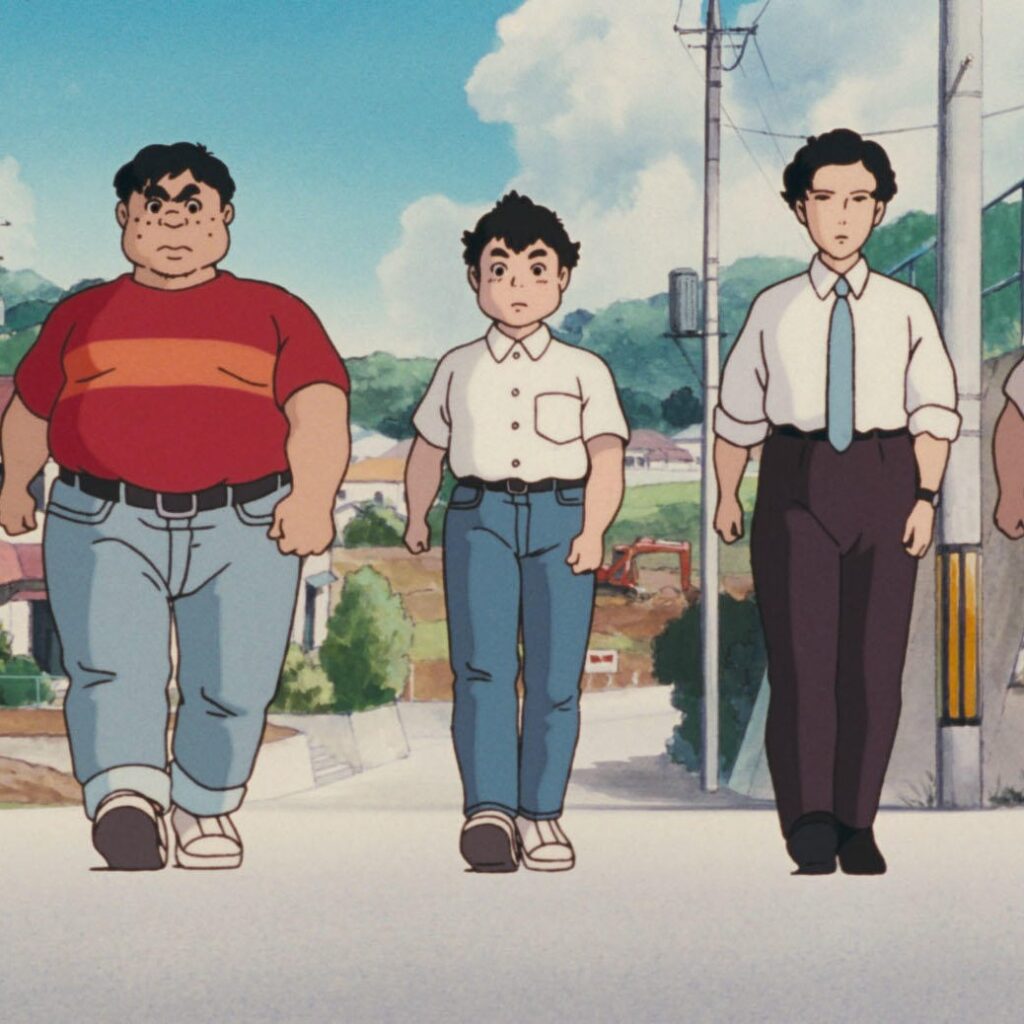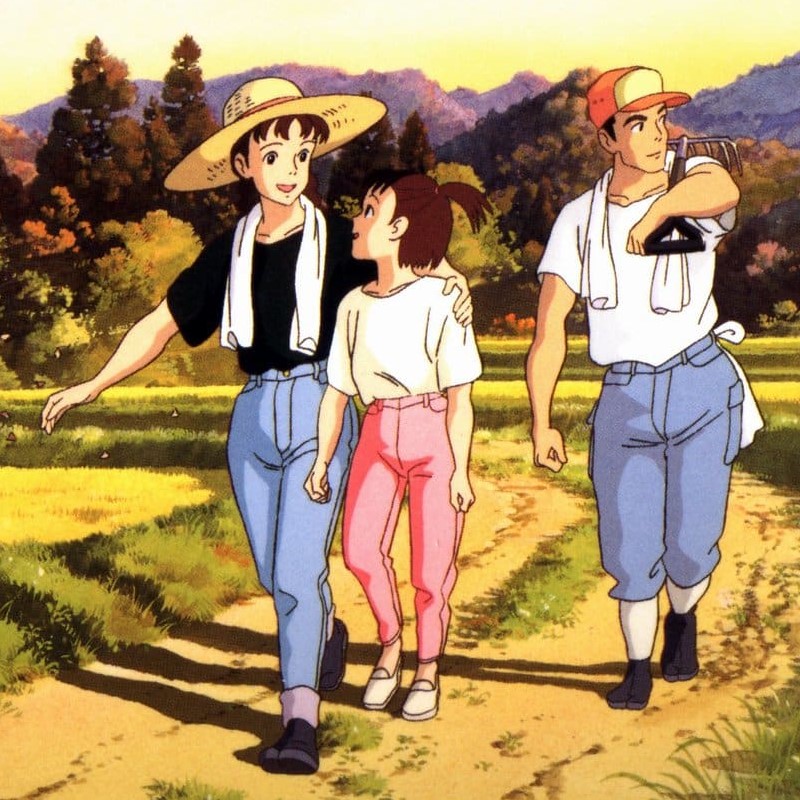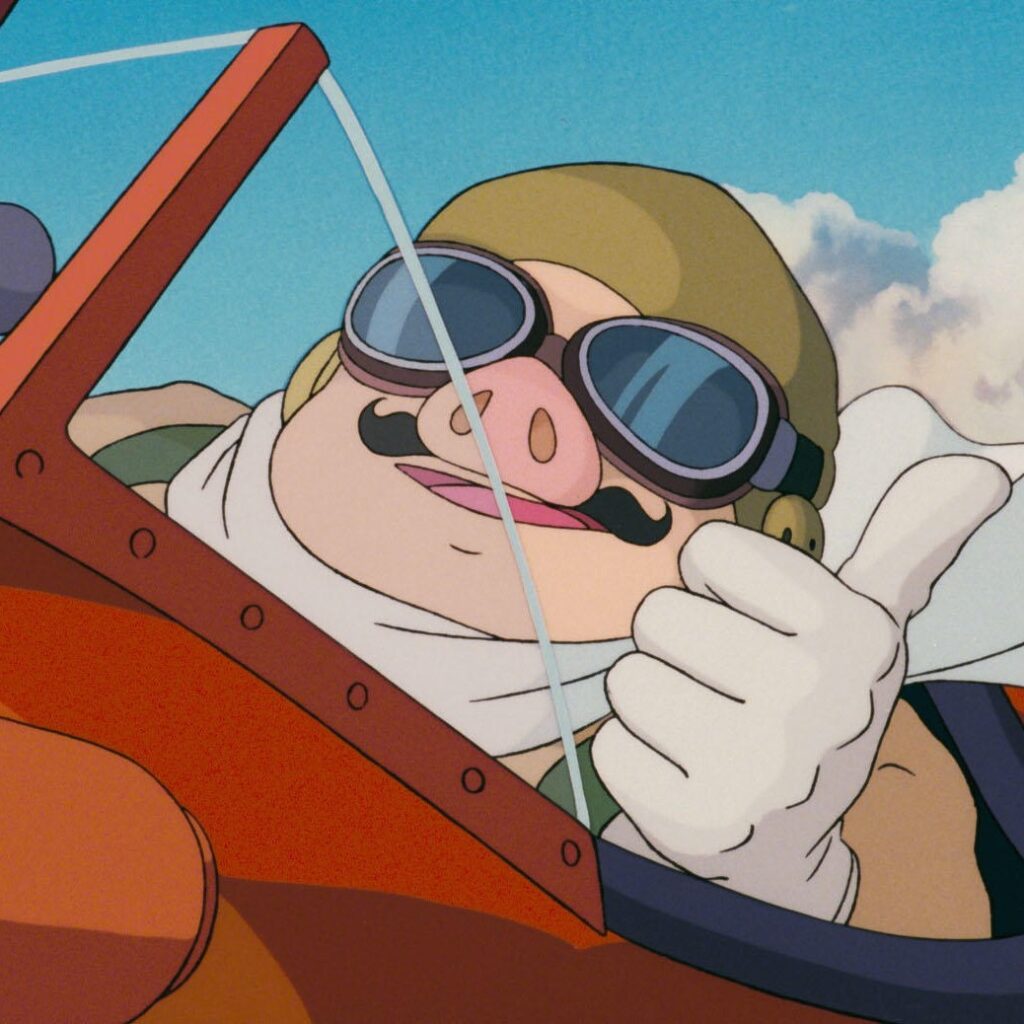映画「EM/エンバーミング」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
冷ややかな刃物みたいにスッと入り、抜いたあとに妙な疼きを残すタイプの作品だ。法医学や死化粧の現場を舞台にした邦画は少ないが、本作はその“少なさ”自体を武器に、観客の好奇心と恐れを同時に刺激してくる。観る前と観た後で、葬送という行為の意味が微妙にズレる——そんな体験を提供してくれる一本である。
EM/エンバーミングは1999年の日本映画で、監督は青山真治。主演は高島礼子。硬質なミステリーの骨格に、葬送技術という非日常のディテールを縫い合わせる手つきが鮮やかだ。淡々とした撮影と音設計が、物語の体温をわざと下げているのもポイント。
物語は、若い遺体の処置中に“あり得ない位置の針”が発見され、さらに頭部が盗まれるという、常識の外側から始まる。サスペンスとしてのフックは強力で、観る側は「これは事故か、事件か、儀式か」と疑いを乗り換え続ける羽目になる。
死を“保存する”とは何か、悲嘆に耐えるための手当てなのか、あるいは執着の延命なのか——本作はそこに薄い皮膜のような倫理を張り、静かにナイフでなぞっていく。笑うところは少ないのに、思わずニヤリとする乾いたセリフ運びもあり、全体のトーンは辛口の大人味だ。
映画「EM/エンバーミング」の個人的評価
評価: ★★★★☆
映画「EM/エンバーミング」の感想・レビュー(ネタバレあり)
主人公はエンバーマーの村上美弥子。EM/エンバーミングは、彼女の“仕事”の視線で世界を測る物語だ。遺体と向き合う姿勢は礼節に満ちるが、その礼節がときに生者の心を固め、真相から目を逸らせることもある。彼女が針の存在に気づいた瞬間、仕事は儀式から調査へ、弔いは追跡へと変質する。
EM/エンバーミングの優れている点は、“事件”と“手技”が対等に描かれるところだ。黒い市場だの、医師の越境だの、ジャンルとしては派手になりがちな素材を、カメラは近寄りすぎず遠ざかりすぎず、切開面の温度くらいの冷静さで見つめる。これが観客の想像を逆に刺激する。
針、頭部欠損、そして処置台——ミステリーの三種の神器が揃ってしまった以上、観客は「誰が」「なぜ」の連鎖から逃げられない。EM/エンバーミングは、犯人探しの快楽を否定しないが、同時に“死の由来”という根っこを掘らせ続ける。謎は解けても、解剖所見の行間は湿ったままだ。
青山真治の演出は、説明せず、決めポーズも取らない。そのかわり、作業の音、器具の光、ガウンの擦れで感情を運ぶ。EM/エンバーミングはBGMも控えめで、観客は自分の鼓動をBGMにして観ることになる。これが意外と効く。体が先に緊張し、頭が後から追いつく。
美弥子と刑事の距離感もいい。職業倫理と捜査倫理がゆるく噛み合い、時に外れる。EM/エンバーミングは、恋愛フラグの安易な点火を避け、職能同士の敬意を育てる。その関係が、終盤の判断の重さに説得力を与えるのだ。安売りの感傷はないが、乾いた熱はある。
ドクター・フジの存在は、本作の“影”だ。正義の裏庭で芽吹く知識の好奇心は、いつだって危うい。EM/エンバーミングは、彼を善悪のラベルに回収しない。科学の倫理と市場の倫理、そこに国家や家族の体面が絡むとき、人は何を切り捨て、何を保存するのか——問いは観客の膝上に置かれる。
遺体の保存が主流ではない文化圏で、この題材をやる意味は大きい。死を“燃やして還す”社会で、あえて“留める”行為は、記憶の扱いを可視化する。EM/エンバーミングは、喪のプロセスを科学的に延命することの光と影を、感傷抜きで並べてみせる。
手技の描写は、過剰にグロテスクではないが、生々しさはある。EM/エンバーミングは、その手際の美しさに一瞬うっとりさせ、次の瞬間に倫理の段差でつまずかせる。映像は清潔、テーマは不潔——この反転が心地よい違和感を生む。
被害者家族の“体面”の描き方も鋭い。権力と悲嘆が同居すると、真相は見えにくくなる。EM/エンバーミングは、社会的な肩書きが遺体処置の現場にどう影を落とすかを、決して大声では語らない。小さな視線のズレで、観客に察させる。
針の意味がわかったとき、ここでいう“保存”は肉体だけの話ではないと知れる。EM/エンバーミングは、欲望、記憶、制度、名誉——さまざまな“保ちたいもの”の衝突を見せる。肉体は器であり、器は通貨にもなる。悲しいが現実的な比喩だ。
音と静寂の使い分けも、体感を支配する。処置室の空気は薄く、廊下の蛍光灯は冷たい。EM/エンバーミングのカット割りは平熱で、だからこそ血の気の引く発見が刺さる。意図的に平坦な路面を敷き、段差で転ばせる設計である。
中盤、頭部欠損の真相に近づく過程で、物語はスリラーの推進力を得るが、終盤は倫理の沼へ下りる。EM/エンバーミングは、加害と被害、治療と搾取の境目を曖昧にする。その曖昧さが、現実に近い。白黒で割り切れる話なら、そもそも“保存”は必要ない。
役者陣も良い。とりわけ主人公の“職業人”としての佇まいに嘘がない。EM/エンバーミングは、彼女の判断が常に正しいとは言わないが、誠実であることは伝える。誠実さは時に人を傷つける——その痛みまで見せるのが誠実だ、という逆説。
美術と小道具の説得力は、作品の土台を固める。ステンレスの冷え、器具の重量、ラベルの筆記——ディテールは喋る。EM/エンバーミングは、そこに“物語の嘘”を置かない。嘘は人間の側にだけ許されている。その配置がミステリーとしての信頼感を生む。
結末は過度に派手ではないが、後味は長く残る。真相は解けても、癒えない感情が台に置きっぱなしだ。EM/エンバーミングは、カーテンをそっと戻した後、観客の肩に軽く手を置く。あなたは何を保存し、何を見送るのか——と。
総じて、本作は“静かな過激さ”でできている。血は飛ばないが、価値観に小さな裂け目が入る。EM/エンバーミングは、ジャンルの枠を固めるより、視野の焦点をずらす方向を選んだ。だから古びにくい。見返すたびに、別の場所でつまずける。
映画「EM/エンバーミング」はこんな人にオススメ!
死を“手当て”として見つめたい人に向く。感傷の厚化粧ではなく、現場の温度で向き合いたいタイプだ。表面的な恐怖では満足できず、余韻でじわじわ来るほうが好きなら、EM/エンバーミングは相性がいい。
ミステリーの筋と職能ドラマの両方を味わいたい人にも推したい。真相を追いながら、手技の説得力でうなりたい——そんな欲張りにも応える。EM/エンバーミングは、事件と作業が二輪駆動で走る。
派手な演出より、空気と音で緊張したい人にも合う。環境音で胃が固くなるタイプには最高の教材だ。EM/エンバーミングは、音量よりも“間”で攻める。
倫理のグレーゾーンに耐性がある人にも勧める。誰かを単純に断罪してスッキリ終わりたい向きには向かないかもしれないが、曖昧さの中にこそ現実があると感じる人なら、EM/エンバーミングの価値がよくわかる。
最後に、職業人の矜持に弱い人。淡々と“やるべきこと”をやる姿に胸が熱くなるタイプは、きっと何度か喉が鳴る。冷たい画の中で、熱はちゃんと保たれている。
まとめ
事件の謎と、葬送のリアリティが互いを磨き合う稀有な一本だ。過激な見せ場に頼らず、体感的な緊張で引っ張る設計が気持ちいい。
“保存すること”の是非を、観客にそっと返す終わり方も上品。見終えると、自分の中の何かをどこに置いておくか、少しだけ考えたくなる。
細部の説得力が全体を支えているので、二回目の視聴で新しい傷跡を見つける楽しみがある。作り手の眼差しが信用できるからこそ、曖昧さも受け入れられる。
結論、EM/エンバーミングは“静かに効く”サスペンス。辛口が好きな人ほど、後味にうなる。保存すべきは、この体験そのものだ。