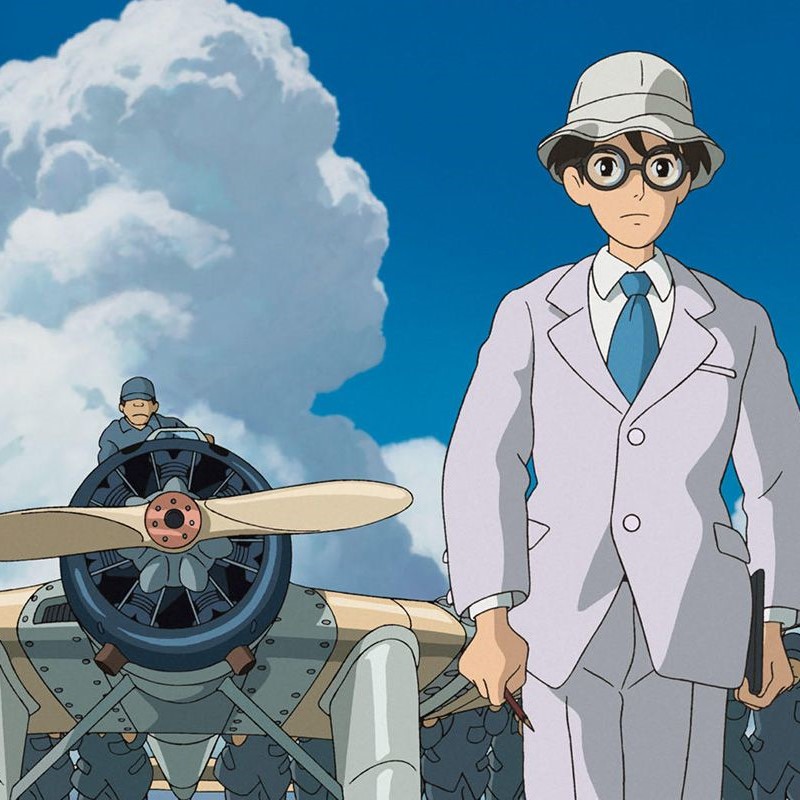映画「アルカナ」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
土屋太鳳が二つの顔を演じ分けるサイコスリラー「アルカナ」。連続大量殺人、分身という設定、そして霊が聞こえる少女――この取り合わせだけで、深夜のB級好きの血が騒ぐやつだ。肩の力を抜いてもいいが、物語は意外と真っ向勝負で、アイデンティティの揺らぎに踏み込む。ここが本作の骨格であり、見どころでもある。
舞台に現れるのは、被害者の心臓だけが抜き取られる連続事件。刑事・村上の前に記憶喪失の少女マキが現れ、死者の声が聞こえると語る。この「聞こえる/見える」能力は便利道具ではなく、彼女の存在理由そのものに関わってくる。そこに“分身”というルールが投入され、世界は一気に不穏な相対性を帯びる。
「アルカナ」は、土屋太鳳の若さと荒々しさをそのままスクリーンに刻みつける。理屈で積むより体当たりで突破するタイプの映画で、粗もあるが突進力がある。だからこちらも、批評の前にまず受け止めてやるべきだ――そう思わせるだけの勢いがある。
映画「アルカナ」の個人的評価
評価: ★★★☆☆
映画「アルカナ」の感想・レビュー(ネタバレあり)
第一に、設定の切り口がいい。分身が本体から“剥がれて”世に出てくるという発想は新奇さと寓意を両立している。分身と本体のどちらが“ほんとうの自分”か、という古典的問いを、連続殺人のサスペンスに落とし込んだ点は素直に評価したい。しかも「アルカナ」は、この設定を説明台詞で潰すのではなく、追跡劇の中に投げ込んで、観客に泳がせる。
第二に、導入の運びが手際よい。連続事件、現場に立つ刑事・村上、そして不可解な少女マキ――この三点セットで物語はすぐに転がり始める。89分というタイトな器の中で、余計な前置きを削り、要件のみを積む潔さがある。ここまでは実に好調だ。
第三に、「アルカナ」は土屋太鳳の一人二役を軸に観るべき映画である。マキの柔らかい眼差しと、もう一人のサツキの刺すような視線。この違いを顔の角度、歩幅、呼吸の浅深で描き分ける。若さゆえの粗さもあるが、役の輪郭を身体で掴みにいく気概が映っている。そこに、分身が“感情の増幅体”として暴走する危うさが宿る。
一方で、脚本の接合部が甘いところもある。分身現象の社会的広がりを示唆する台詞や部署の存在が提示されるが、制度やルールの掘り下げは最低限にとどまる。設定が強いだけに、世界の厚みがもう一段ほしかった。説明を増やせと言っているのではなく、具体的な事例や因果を一つ二つ見せるだけで信憑性が跳ね上がったはずだ。
サスペンスの見せ場は、被害者の“声”に導かれる聞き込みと、分身の痕跡を追うチェイスに置かれている。ここは編集のリズムが効いており、低予算めの現場感がむしろ臨場感を生む。特に雑踏を割って走るショット群は、画の荒さを推進力に変えるタイプの快走だ。ただし、状況説明が走りに置いていかれる場面もある。
ホラー要素は、血の造形や暗がりの空気よりも“音”に寄せている。死者の呻き、心臓の鼓動、短く鋭い環境音。大袈裟に盛らない分、耳に残る。視覚より聴覚で不安を育てるやり方は、本作のスケールに合っている。観客の想像を使う演出だ。
「アルカナ」が抱える最大の課題は、謎と解決の配分だ。中盤にかけて謎が勢いよく積まれるのに対し、終盤の回収はやや駆け足。分身と本体の位相が交錯するクライマックスは、テーマとしては正しい着地点なのに、手順の省略が多く、感情の波が一段弱い。あと5分、二人の関係に呼吸を与えられたら印象は変わったはず。
それでも、タイトルが示す“秘儀”の気配は終始流れている。分身はただの悪ではなく、抑圧やトラウマの“外在化”だという視点。これを個と社会の摩擦の中で描こうとする態度には誠実さがある。物語の端々に「人は自分で自分を作り替える」という切ない欲望が滲む。そこが引っかかるから、ラストの苦味も残る。
キャラクターの相性も見どころだ。がむしゃらな村上と、感覚で世界に触れるマキ。互いの足りなさを埋めるバディの呼吸が時折きらめく。特に、マキが“聞いたもの”を言葉にできず戸惑うとき、村上がそれを行動に翻訳してやる瞬間が良い。言語と身体の分業が、分身テーマと地続きになっている。
脇を固める面々の存在感も効いている。理詰めの上司格が現実側の重しとなり、世界が飛び過ぎないようバランスをとる。岸谷五朗らの“地の重さ”は、作品の軽量感を救う錘だ。キャスティングで世界の密度を補っている。
爆発物の線や、連続事件の手口が示す“意匠”も面白い。犯人像の輪郭は薄いが、都市のはざまに生まれた“影のネットワーク”として描かれ、分身の集合体というイメージに接続する。ミステリとしてのロジックより、サスペンスとしての勢いを優先した判断だ。これは賛否が割れるところだろう。
ロケーションの冷たさも「アルカナ」の味だ。川沿いの風、灰色の空、人気のない施設。土地の湿り気が画面に移り、人物の体温との差でドラマが立ち上がる。常総市の全面協力でオールロケという話は頷けるし、地域の質感を取り込む姿勢は好ましい。
原作は小手川ゆあの漫画。連載の尺を一本の映画に畳み込む以上、設定のダウンサイジングは避けられない。本作もその圧縮の痕が随所に見える。だが、翻案の方向は明確で、人物関係を絞って“二人の寓話”にする選択は筋が通っている。広げない勇気を取ったのだ。
アクションの見せ方は実直だ。派手なワイヤーや大スケールの爆破で驚かすのではなく、走る、掴む、倒れる――物理的な接触を積み上げる。だから時に野暮ったく見えるが、現実に足がついた痛覚がある。分身という観念を“肉体”に引き戻す効果がある。
総じて、「アルカナ」はアイデア先行で突っ切るタイプの快作だ。欠点ははっきりしているし、完成度で言えば平均点前後。それでも、“自分が自分を乗りこなせない”という人間の難題に正面からぶつかっている。観終えてからふと、自分の中の“もう一人”の息遣いに耳を澄ましたくなる。そういう小さな余韻を残す。
そして何より、土屋太鳳の存在が映画を前に押す。若さと気迫、未整理の粗さ、そこから立ち上がるリアル。整ってはいないが、生きている。その生きの良さが、分身の凶暴さと本体のかすかな希望を同時に感じさせる。これこそ「アルカナ」でしか味わえない体温だ。
最後にもう一度。「アルカナ」は、設定に惹かれた人ならまず楽しめる。細部で首をかしげる瞬間もあるが、勢いと気配で走り切る。ラストの選択も含めて、作品はちゃんと“問い”を投げてくる。それにどう応えるかは、こちらの中にいる“もう一人”次第だ。
映画「アルカナ」はこんな人にオススメ!
まず、土屋太鳳の初期キャリアを追っている人。若さまるごとの表現に触れたいなら「アルカナ」は外せない。同じ役者の別の表情を一度に見られるという意味でも、俳優映画として楽しめる。
次に、分身モチーフやドッペルゲンガー譚が好きな人。概念そのものにゾクッとくるタイプなら、「アルカナ」が用意するルールと逆襲はきっと刺さる。設定の粗も、むしろ想像の余白として働くはずだ。
さらに、90分前後でさくっと味わえるサスペンスを探している人。長編ドラマのように細部を積み上げる手触りではないが、「アルカナ」は勢いで走り抜ける。平日の夜に“もう一本”いっとく感覚でちょうどいい。
また、都市の陰影やロケ地の空気が好きな人にも推したい。無機質な施設、川風、灰色の空――「アルカナ」は画面から肌寒さが立ち上がるタイプの映画で、季節の変わり目に観ると体感が増す。
最後に、邦画の“実験”に付き合うのが好きな人。完璧ではないが、ここでしか見られないトーンと執念がある。「アルカナ」はそんな一本だ。刺さる人には深く刺さる。
まとめ
「アルカナ」は、分身×連続殺人×霊聴という強いカードを、若い熱量で切っていく映画だ。荒いところは多々あるが、駆け抜ける力がある。
土屋太鳳の二役は、物語の推進力でありテーマの核心だ。身体の差異で人物を立たせる姿勢が、作品の野心と重なる。
世界設定の薄さや終盤の駆け足は減点材料。ただ、短尺の制約下で選び抜いた見せ場と音の設計が、体験の輪郭を保っている。
結局のところ、“もう一人の自分”に心当たりのある人なら刺さる。そういう観客に向けて、「アルカナ」は小さくも確かな刃を差し出す。