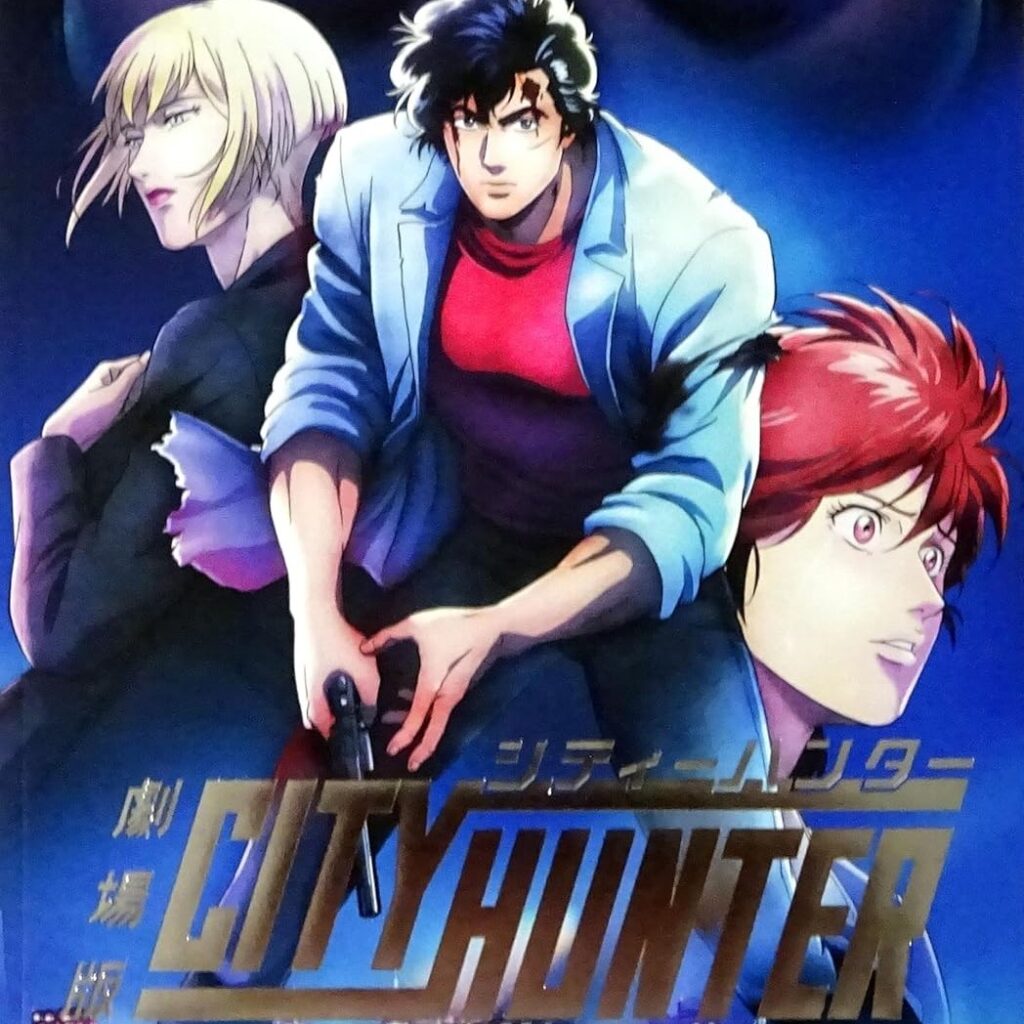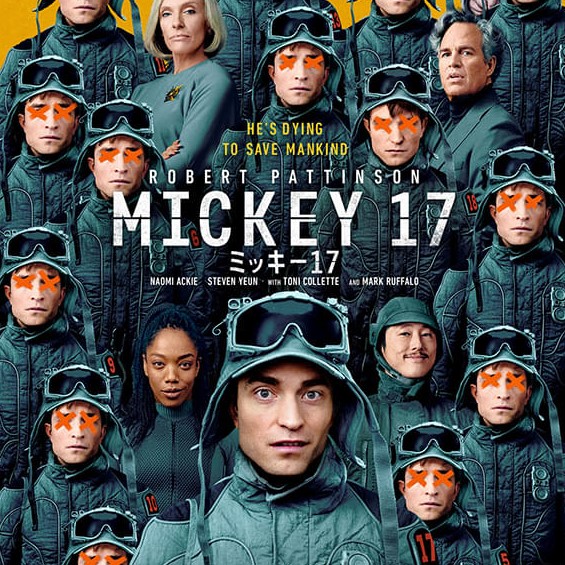映画「忌怪島(きかいじま)」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
生駒里奈がメインキャストを務めると聞けば、まずはアイドル出身の演技力に注目する人も多いだろう。しかし、本作はそんな先入観を軽々と超えてくる仕上がりになっていると感じた。ホラーの舞台としては一見美しい南の島が中心だが、気がつくと不気味な影がぬるりとこちらをのぞき込んでくるような独特の不安感に襲われるのが特徴的である。しかもVRや脳波解析などの先端技術と呪いという古来の恐怖が混ざり合うため、単純な怪談にとどまらない妙な説得力があるのが面白いところだ。
監督は『呪怨』で知られる清水崇。すでに日本のホラー界を代表する存在だけに、じっとりとした恐怖表現や、水気を帯びたおどろおどろしさを盛り上げるのが得意分野だと再確認させられた。とはいえ本作は、海に浮かぶ鳥居や仮想空間のループなど、今までのホラーとはひと味違う構造的な仕掛けを搭載している。観客は現実と虚構の狭間を行き来させられ、どこからが夢でどこまでが真実か分からない恐怖を感じるはずだ。
とはいえ、登場人物同士の掛け合いや、思わぬ場面での軽妙な会話もあり、ただひたすら怖がらせるだけの作品でもない。生駒里奈演じるヒロインの笑顔と、謎に満ちた島の環境が絶妙にコントラストを成し、観ているこちらの心を翻弄してくる。そうした緩急のバランスがうまく働いているからこそ、クライマックスの恐怖が一段と強まるのだろう。
一方で、特撮やVFXの使い方に少し荒削りな印象があるのは否めない。しかし、その少々ざらついた描写も清水監督の特徴といえる。美しく整合性が取れ過ぎた映像よりも、ある種の荒っぽさが存在するからこそ、ホラー的なリアリティを生み出しているとも言える。実際、絶妙なタイミングで響く鎖の音や、フッと湧き出す水の描写は妙に生々しく、背筋を凍らせる効果が抜群だ。
映画「忌怪島(きかいじま)」の個人的評価
評価:★★★☆☆
映画「忌怪島(きかいじま)」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本編をじっくりと観てみると、まず目を引くのはVRやメタバースといった現代ならではの技術と、古くから語り継がれる呪いの伝承が同居している点だ。離島特有の閉鎖性や土着の信仰心は、日本のホラーにとって伝統的なシチュエーションといえる。そこへ最先端のVR研究が結びついているのだから、少しばかり奇妙な相乗効果が生まれている。
あらすじを追うと、物語の主人公たちは島をそっくりそのままスキャンして仮想空間を構築する「シンセカイ」という研究プロジェクトに携わっている。その研究の最中、脳波データを介して不可解な現象が起こり始めるわけだが、ここで重要なのは「脳のデータ」そのものが持つ危うさだ。デジタル技術で脳の情報を取り出す行為は、単なる映像や音声を再現するだけにとどまらず、感情や意識、さらに“呪い”までも再生し得るかもしれないという恐ろしさを孕んでいる。
実際、本作では島に伝わる「イマジョ」という伝説の女が現代の技術を通じて再び甦る。生前の悲惨な境遇からくる怨念が、メタバースの世界でも容赦なく人々を追いつめていく筋書きは、バーチャルとリアルを一括りに呑み込むようなインパクトがある。「あちらの世界とこちらの世界」「生者と死者」「昔と今」……これらが交錯する空間でキャラクターたちは翻弄されていくのだ。
主人公たちの中には、純粋にVR技術を発展させたい者だけでなく、研究をビジネスに転用しようと企む者や、封じられた島の呪縛を解き放とうとする者までいて、それぞれの思惑が錯綜しているのも見どころである。シンセカイの仲間たちが次々に謎の死や失踪に巻き込まれていく展開はホラーとしての緊迫感を高める一方、そもそも自分たちの立ち位置が現実なのか仮想空間なのか怪しくなってくるあたりも厄介だ。
例えば、本編中で人物が突然いなくなるシーンや、足元が水浸しになる場面がいきなり発生するのは、もしかすると全てが既にメタバースなのではないかと疑わせる。島の住民とすれ違わない光景も意味深で、どの時点でVRに入っているのか分からないという仕掛けがずっと付きまとってくる。これは観客の頭を混乱させるための演出とも思えるし、現実と仮想の境目を根底から揺さぶる本作の核心部分とも言えそうだ。
加えて、生駒里奈演じる未央(作中では島の研究チームの一員)が見せる明るさと、陰鬱な島の空気が対比されることで、ただ暗いだけの映像にならないバランスを保っている点も評価したい。彼女が画面に登場すると、島の憂鬱な雰囲気がいったん柔らかくなるのだが、そこにこそ本作の“油断できない”怖さが潜んでいる気がした。笑顔の裏でじわりと迫りくる恐怖があるため、観客としてはどこで落とし穴に落とされるか分からない緊張感を味わうことになる。
もちろん、監督の清水崇らしい濡れた質感や、生理的にくる映像表現も随所に散りばめられている。水辺のシーンで人の顔が歪んで見えたり、鳥居が崩れ落ちるときの不気味な音が耳元に残ったりする感覚は、ザワリとした不安を生々しく引き起こす。これは舞台が南国の島であることとも妙に噛み合っていて、日差しの明るさと黒い闇の対立が一層際立つようになっているのだ。
後半になると、仮想空間内の鳥居を焼き払うシーンや、現実の鳥居を破壊しようとするキャラクターの必死の行動が描かれる。しかし、それらが本当に効果をもたらすのかどうか、作品中でもはっきり答えが提示されているわけではない。燃え尽きたはずの鳥居がいつの間にか残っていたり、登場人物の腕に謎のコードが浮かび上がったりする演出は、結局のところ呪いは途切れずに続いていくのではないかと思わせる。
個人的に興味深いのは、作品のラストで島を離れたはずの人物が、まだどこかでこの仮想と現実のループに囚われているかもしれないという絶望感を仄めかしている点だ。ホラーとしてはお決まりの「実は解決していない」というオチだが、ここではVRという設定が絡むことで、もしかするとずっと仮想空間にいたのかもしれないという重層的な恐怖が生まれている。
特筆すべきはイマジョ伝説の持つ凄まじい怨念だ。島の男性たちから酷い仕打ちを受け、その復讐心が長い時を経ても途切れない。そもそも“恨み”という感情はデジタルにもアナログにも分け隔てなく伝播し得るのだ、と言わんばかりの描写には考えさせられるところがある。
一方で、本作にはミステリー仕立ての要素もあり、島に何が起きてきたかを少しずつ解き明かしていくプロセスがある程度用意されている。人々が抱える過去のトラウマや、研究者たちの裏の思惑などを追うことで、やがてイマジョだけではない“人間”の恐ろしさに行きつくという二重の意味でのホラーだ。真の闇は人間の心の中にも隠されているのだろう。
ただし、演出や脚本に多少粗い部分もあるため、非常に鋭い視点で観ると「もうひと押し欲しかった」と感じるかもしれない。とはいえ、そこを補って余りあるほどに現代的なテーマが盛り込まれていて、想像以上に議論の余地を残す作品であることは間違いない。
全体としては、南国の風景を舞台にしたホラーらしさと、最先端のテクノロジーが絡む独特な恐怖感をあわせ持つ刺激的な一作だといえよう。実際に体験したかのように錯覚させる水音や、視点がぐらりとぶれるシーンなどは劇場のスクリーンで観ると迫力満点。生駒里奈の存在感も、単なるヒロインを超える意味を持っているので、彼女の新境地を観たいファンなら必見だ。
最終的に、映画の中で解釈される“あの世”と“仮想空間”との近似性は、技術が進歩すればするほど人間の境界が曖昧になっていく怖さを暗示しているかのようでもある。「ひとたび入り込めば、そこが現実かどうかさえ分からなくなる」――そんな未来への警告めいたメッセージと、島の呪いが混然一体となって観る者を脅かす体験こそが、この作品の真骨頂だと感じた。
映画「忌怪島(きかいじま)」はこんな人にオススメ!
「南国の離島を舞台にしたホラーに興味がある人」にはドンピシャだと思う。明るい太陽が照りつける楽園のはずが、いつの間にか背後からじとっとした恐怖が忍び寄る感覚は独特である。また、「VRやメタバースなどの最新技術にまつわる物語が好きな人」にも響く要素が多い。情報をスキャンして仮想空間を構築するというアイデアが、ホラーの題材になるという発想自体が斬新だと言えるだろう。
さらに、「伝承や因習に根ざす日本の怪談らしさを味わいたい人」にとっても満足度は高いはずだ。島固有の言い伝えや祈祷師の存在など、民族学的な香りが漂うシーンが多いので、そういう土着文化に興味がある人にはたまらない空気感がある。一方で、「生駒里奈の新たな姿を見たいファン」にとっても魅力的で、アイドル時代とは違う演技への挑戦を楽しむきっかけになるだろう。
ミステリー的な要素や人間関係の裏側を探る展開が混ざっているので、「一本筋の通ったホラーだけでなく、人間ドラマも味わいたい人」にもうってつけだ。物語が進むにつれ、島の闇や研究プロジェクトの秘密が徐々に解き明かされる過程はなかなか刺激的である。
とはいえ、ホラー描写が苦手な人や、残酷なシーンがまったくダメという人には少々ハードかもしれない。水の中に沈んでいく描写や呪われた鳥居の映像など、観る者によってはなかなかヘビーな印象を受けるだろう。逆に言えば、「ちょっと背筋が凍る感覚を味わいたい」「さっぱり寝つけないくらい刺激的な作品を見たい」という人にはまさにピッタリである。
まとめ
映画「忌怪島(きかいじま)」は、離島の因習と最新鋭のVR技術がぶつかり合うという異色のホラー作品だ。しっとりと湿った恐怖描写で知られる清水崇監督らしく、画面に漂う空気が肌にまとわりつくような不安感を生み出しており、水辺を中心とした演出は本作の大きな特徴といえる。
一方で、物語の構造は意外にも入り組んでおり、「現実と仮想空間がどこで切り替わるか」を探りながら観る楽しさがある。何度もバグのように挟まれる黒い影や、水で満たされる空間のイメージは、単なるホラー的要素にとどまらず、観客をメタ的な恐怖へといざなう仕掛けかもしれない。
生駒里奈の存在感は鮮烈で、アイドルらしさとは違う強さを感じさせ、作品世界の説得力を上げることに貢献している。もちろん、いくつか粗削りな部分はあるが、そこも含めて本作らしい味わいになっていると思う。最新技術や仮想空間という素材をどうホラーに落とし込んだのか、その答えが気になる方はぜひ手に取って確認してもらいたい。