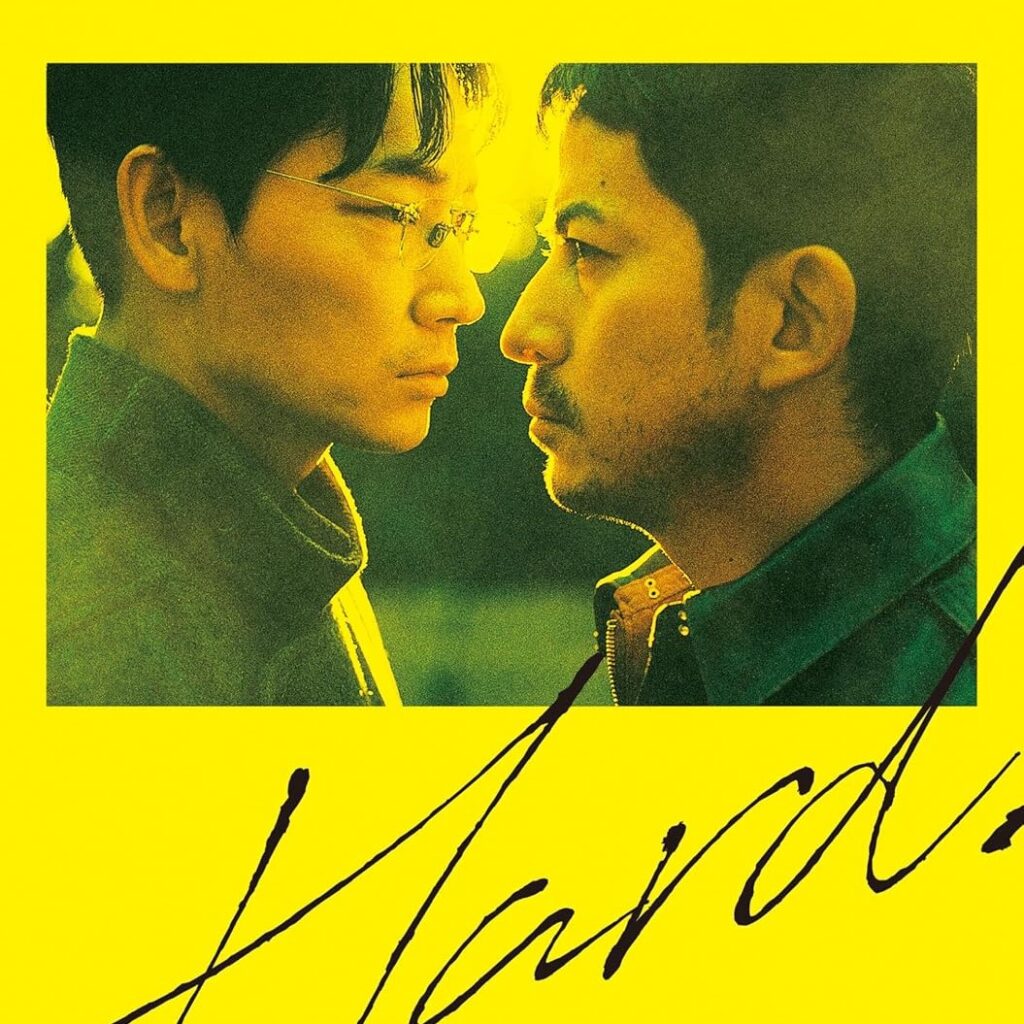映画「禁じられた遊び」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
橋本環奈が出演しているとあって、話題性は十分。しかも監督はあの『リング』でJホラーを一躍メジャーに押し上げた中田秀夫である。本作は「尻尾を埋めたら命が芽生える」といった奇妙な言い伝えが軸になっており、一見オカルトファンタジーかと思いきや、後半になるにつれ恐怖のどん底へ叩き落とされる作品であった。序盤は家族愛が描かれ、平穏な日常が“ある出来事”をきっかけにして一変する。その変貌ぶりに背筋がじわじわと冷たくなり、つい息をのんでしまうところが恐ろしい。
さらに、そこに本人が意図せず嘘をついたことが大きく絡んでくるのだから救いようがない。まるで「子どもならではの純粋さ」が“とんでもない方向”へブーストしてしまったかのようだ。ホラーに加えて人間ドラマの妙味も堪能できる刺激的な一本である。
映画「禁じられた遊び」の個人的評価
評価:★★☆☆☆
映画「禁じられた遊び」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本作を語るうえで外せないのは、子どもという存在が引き金を握っている点である。「家族が一番大切」「ウソはよくない」など、道徳の教科書に出てきそうなメッセージが、恐怖と隣り合わせの状況下で歪んだ形を伴いながら描かれているのが印象的だ。しかも、ただの怪奇現象に怯える話ではなく、「人間の願い」がとてつもなく恐ろしい形で叶ってしまったら……という想像を強烈に刺激してくる。ここでは、本作の要所を振り返りながら、その底知れない“こわさ”を掘り下げてみたい。
主人公となる一家の父・伊原直人は、妻・美雪と息子・春翔とともに新居で幸せな日々を送っていた。ところが、ある日を境に、この温かい家庭に破滅への兆しが忍び寄ってくる。最初に見せ場を作るのは、何でも信じてしまう幼い春翔の存在だ。庭でトカゲを捕まえようとして尻尾が切れた際、直人は軽い気持ちで「埋めれば復活する」という冗談を口にする。それを純粋な子どもは額面通りに受け取り、毎日のように土に向かい呪文を唱え始める。すると、まさかの奇跡なのか呪いなのか、トカゲは本当に“戻って”きてしまった。
この不気味な出来事の後、一家を大きな悲劇が襲う。美雪と春翔が交通事故に遭い、病院で春翔は一度息を引き取ったが、雷の落雷と同時に奇跡的に蘇生。それ自体は“幸い”に見えるが、後に判明する事実を考えると、この出来事は悪夢の序章でしかなかったと言える。なぜなら、この“いったん死んで生き返った”という部分が本作で最大の要素になるからだ。
本作は霊能力者が登場し「死者の霊はいない」と語るくだりがとりわけ衝撃的だ。普通なら「ホラー=死者の怨念」が王道だが、本作はそれを覆す。「本当に恐ろしいのは、一度死から戻った生き者の呪いだ」という解説が示すように、悲劇の根源は“蘇った春翔”にある。しかも、美雪自身にも“特殊な力”があったことが示唆される。彼女の母親も宗教団体の教祖であり、不思議な力を遺伝で受け継いだらしいのだ。つまり、母の力と自分自身の“蘇生”による異質な何かが、春翔の中で結びついてしまっている。
そもそも妻・美雪に関しても、不穏な部分があった。夫の会社の元同僚・倉沢比呂子(橋本環奈)が「直人を好きになった」だけで、美雪の生霊が執拗に警告を送り続けていた。手のこんだ方法で脅し、彼女が会社を辞めるまで追いつめるというのだから、その強烈さは薄気味悪い。しかも、そんな美雪が死んだらそれで終わり…ではなく、家に埋められた“指”をきっかけに、さらに恐怖が増幅される。ところが真相を知れば知るほど、“美雪の怨霊”だと思われた現象が実は“生きた子どもの力”によるものだとわかってくるのだから、背筋が凍る。
中盤以降、春翔が必死で唱え続ける「エロイムエッサイム」の呪文は、よくオカルト系の物語に登場するフレーズである。土から“何か”が生え出そうとする光景と、「ママに早く会いたい」という春翔の純粋な願いが結びつき、不吉な現象が止まらなくなる。視点を変えれば、これは「小さな嘘で子どもの想像を増幅させたらどうなるか」という教訓話でもあるだろう。悪ふざけ半分の嘘を、大人の想像を超えるやり方で具現化してしまう……ここに生々しい恐怖がある。
やがて、庭の土から“母”の肉片が再生しはじめる映像はかなりグロテスクだ。まるで粘土細工のように蠢く“肉”が、次第に輪郭を持ち“人の形”へと近づいていく。その描写は一見SFか怪獣映画かと思うほど怪異じみており、しかも再生速度が早いわけでもないため、じわじわ侵食される恐怖が味わえる。直人も最初は「こんなことはあってはならない」と戦慄するが、物理的に壊そうとしても、どこかで“妻への未練”を断ち切れない気配があるのがやるせない。この揺れる心情が彼を深みへ誘い、さらに状況を悪化させていくのだ。
一方、比呂子にも災難が降りかかる。かつて美雪の生霊に狙われたトラウマを再度思い出させるような現象が立て続けに起こり、彼女の周囲の人間が次々に犠牲になっていく。恐ろしいのは、誰がいつ“力”に呑まれて襲ってくるかわからない点である。とあるシーンでは、霊能力者が取り憑かれ、その助手までが意識を乗っ取られ命を断つ展開が登場する。従来の「死んだ怨霊が人々を襲う」というパターンとはひと味違うだけに、予想を裏切るかたちで人が死んでいく緊張感が凄まじい。
そして、後半のクライマックスでは、美雪“らしき存在”がいったん完全な姿に戻って直人や比呂子の目の前に現れる。まるで白い人型が土からむくむくと現れたかと思うと、今度はあちこちが鱗や枝葉のような肌を伴い、まったく違う生命体へと変貌していく。言葉で表すなら、グロテスクさと悲しさの入り混じった地獄絵図だ。もはやそこには生前の美雪らしき人格は残っていないかのようで、「妻」というよりは「化物」と化している。その暴走をどう止めるのか、しかも春翔の“力”はまだ残っており、直人も罪悪感や後悔に苛まれる……と、最終盤は怒涛の混沌が渦を巻く。
最終的には、かなり乱暴な決着の仕方で「母」と「息子」は散っていく。雷がトドメを刺す形で、蘇りかけの怪物(美雪)もろとも春翔が命を落としてしまうのだ。ここに確たる救いはあまりない。悲しみに打ちひしがれる直人の姿は、見ていて痛ましい。ただし、「もうこれで全てが終わった」と思いきや、ラストで彼が取った行動がとどめの恐怖を突きつける。春翔の指を埋めているのだ。つい先日の地獄を経験しながら、なお「大切な人を蘇らせたい」と願ってしまう。こうした“人間の業深さ”が、最終シーンで露わになるのはゾッとするポイントだ。つまり、すべてが再び繰り返される可能性を示唆しているというわけである。
振り返れば、タイトルの「禁じられた遊び」はフランス映画からの引用だとされるが、この日本版では「死者を冒涜する行為」や「純粋な願いが破滅をもたらす様」を強烈に打ち出している。単に死の怖さを描くのではなく、“願う”こと自体がどれほど危ういかを突きつけてくるのだ。特に「子どもは大人の何気ない言葉を絶対の真実として受け取りがち」という点が突き刺さる。大人が発するちょっとしたジョークが、想像力旺盛な子どもの頭の中で限界なく肥大化し、結果として最悪の惨劇に結びつく……あまりにも恐ろしい展開である。
さらに脚本上、「母の力を受け継いだ息子」という構造も巧みに働いており、子どもの無垢な純粋性と、遺伝的に持っている特殊な力が合わさってしまうのが最悪のシナジーを生む。「ママに会いたいから、トカゲが再生するようにママの体を土から生やそう」という発想は、おとぎ話じみて聞こえるが、いざそれが実際に起きたらどうなるのか、というリアリティが恐怖を増幅させる。どこか愛すべき要素すらある子どもが、怪異の根源になる点が人間の恐怖心をいっそう煽るわけだ。
また本作は、その凶悪さばかりを強調するわけではない。親子や夫婦の愛情がもともとしっかり描かれているため、その絆が歪んでいくさまが容赦なく胸に刺さる。直人も本来は家族想いのいい父親なのだ。あの嘘さえつかなければ、あるいは美雪の死を受け止める覚悟ができていれば、悲劇は避けられたのかもしれない。しかし、後戻りのできない道を歩み始めてしまうと止められないのが人間の怖さでもある。
こうして本作を通して感じるのは、想像力の暴走と“愛”や“欲望”のせめぎ合いである。普通ならそんなことは起こり得ないという常識を、霊的な力や子どもの信念がぐいぐいと打ち破り、しまいにはトカゲすら再生してしまう。しかも、戻ってくるのは必ずしも元の姿ではない。直人たちが目の当たりにした“再生した者”は、かつての愛する人に“似た何か”であって、最終的には恐るべき怪物と化していた。だからこそ余計にやるせないのだ。「蘇ったら幸せになれるはず」という淡い希望が、皮肉にも周りを地獄へと叩き落とす。その構造が、視聴後もしばらく胸に重くのしかかる。
結局のところ、本作では救済と呼べるものがほぼ提示されない。ラストは雷の力で強制的に決着がついたように見えて、直人が再び“指”を埋める光景で幕を下ろすのだから、本当に絶望的である。死者は蘇らせてはいけない、という古典的なホラーテーマを、現代らしい映像表現と社会観を混ぜ込んで説得力あるものに仕上げた印象だ。昔ながらの恐怖だけでなく、人々の行動原理や愛憎劇がしっかり描かれているのが大きいのではないか。橋本環奈の迫真の演技も相まって、清らかさと暗黒面の落差が鮮烈に印象に残る。
この映画は、表面上は呪いのホラーでありながら、「家族の愛情と子どもの想像力が悪夢と化す瞬間」を見せつけてくる物語だ。ある意味、夫婦や親子の結びつきは純粋であればあるほど怖いとも言える。何気ない言葉一つで招かれる悲劇に、思わず身震いしてしまう。もし「死者を生き返らせたい」と願うなら、本作を観た後には二度とそんな行為に手を染めようとは思わなくなるに違いない。
映画「禁じられた遊び」はこんな人にオススメ!
本作は、家族愛を描いた作品に興味を持つ方に勧めたいが、単なる感動話を期待すると痛い目を見るかもしれない。むしろ、「身近な存在がふとした誤解や嘘で恐怖に変わる瞬間」を味わってみたい人向けである。子どもの純粋さと残酷さは表裏一体だが、本作はその両面を深く描き出しているので、ホラー好きのみならず心理ドラマ好きにも刺さるだろう。
加えて、オカルトや呪術の題材が気になる方にも適している。土に埋めたものが再生するという発想はどこか悪魔的な香りを放ちながら、同時にファンタジーめいたロマンが混在しているからだ。作品内では、霊能力者の登場や生霊の存在も描かれており、いわゆる“幽霊”よりも始末に負えない現象が次々と現れる。普通のホラー映画とは一線を画した「一度死んで蘇った者が最悪」という設定は新鮮なので、定番の怪談を見慣れた人にも十分楽しめるはずである。
一方、血みどろの描写や再生中の肉体表現などグロテスクなシーンも多いので、そういう要素が苦手な人にはややハードかもしれない。ただ、そこには無闇な残酷さではなく、家族を取り戻そうとする切実な思いが色濃く混じっているので、単なるスプラッターではない。この複雑な“人間模様の絡まり”を胸に受け止められる人にとっては、一生記憶に残る作品になるだろう。どうしようもなく怖いが、妙な引力を放つ映画を探している方にはぜひおすすめしたい。
まとめ
本作は「死者を蘇らせる」という禁断のテーマを扱いながら、単にホラー的な怪奇演出だけを強調するのではなく、人間の深い愛情や嘘がもたらす悲劇を丁寧に描いているところが特筆すべき点である。特に、主人公が悪気なくついた嘘が子どもの無垢な願いと交差し、次第に取り返しのつかない破滅を呼び寄せる構造は見応えがある。冒頭で感じた「家族の幸せ」が、いつの間にか地獄へ堕ちていく展開は、観る者の心を容赦なく抉るだろう。
さらに、作中で提示される「一度死んで生き返った者の力が最も恐ろしい」という概念が従来の“幽霊譚”とは異なる新鮮さを生む。蘇った存在は、生前のままの愛しい姿ではなく、得体の知れない怪物と化して周囲に襲いかかる。だからこそ、登場人物たちは最後まで翻弄され続けるわけだ。最後に待つ結末は決して明るくないが、そこにこそ本作の本質が詰まっているのではないか。観終わった後でもゾクリとする余韻が残る、硬派なホラーであった。