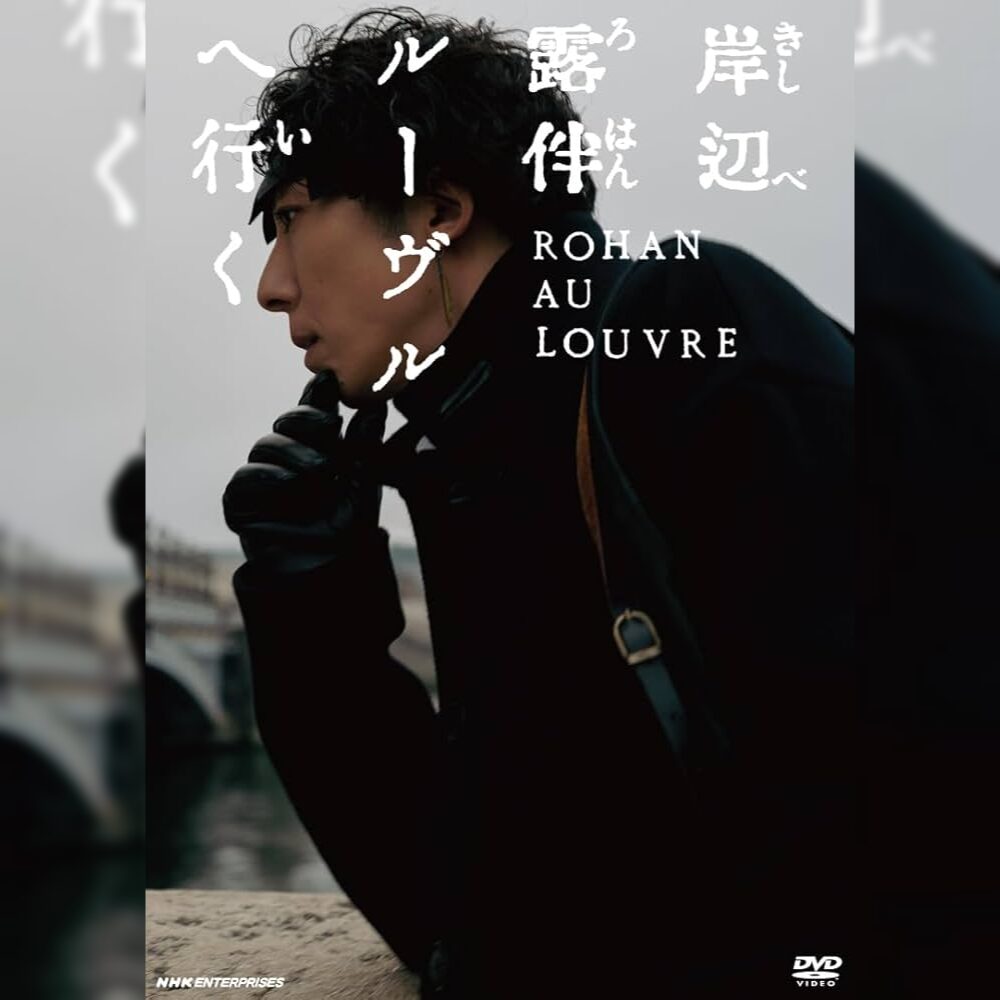映画「片思い世界」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
広瀬すずが出演していると聞いただけで足を運ぶ人も多いだろうが、この作品は単なる青春ものとはひと味違う。坂元裕二らしい繊細さに加え、観る者を不思議な空間へといざなう独特の展開が待ち受けている。最初は「どこかで聞いたことのある話かも?」と油断していると、次々に登場人物たちの運命が狂い始め、気づけばいつの間にか引き込まれているはずだ。しかも序盤から終盤まで謎や真実が小出しにされる展開ゆえ、観客それぞれが必死に“答え”を探ろうとしてしまう。ところが結末を迎えたあと、自分なりの解釈を固めたとしても、心にじわりと残る妙な感覚が消えない。まるで、遠い日の片想いがふと甦ったかのように懐かしさや切なさが同居し、独特の余韻が心を離さないのだ。
この映画の大きな魅力は、広瀬すずをはじめとするキャストたちの自然体の演技と、脚本からにじみ出る“優しさ”と“ほろ苦さ”の両立にある。そう聞くと「お涙ちょうだいなのか」と早合点しそうだが、むしろ残酷さや無力さを否応なく突きつけられる場面も多く、それが物語に奥行きを与えているのだと思う。人生の不条理に抗いながらも笑って前を向こうとする若い魂が躍動するからこそ、観終わったあと自分の生活にもどこか新しい風を吹き込んでくれるような、そんな作品であると感じた。
映画「片思い世界」の個人的評価
評価: ★★★★☆
映画「片思い世界」の感想・レビュー(ネタバレあり)
ここからは物語の核心に触れる部分があるので、未鑑賞の人には刺激が強いかもしれない。だが、あらためてこの作品を深く味わいたい人にはぜひ読んでもらいたい。自分の感じたことや考えたことを、かなり率直にまとめてみた。
まず、あえて先に結論めいたことを述べると、「死と生」「届かない思い」「それでも微かに繋がる人々」といったテーマが見事に融合していたのが、この映画の最大の特長だと思う。実際、本作では広瀬すず演じる美咲、杉咲花演じる優花、清原果耶演じるさくらの三人が12年前のある事件をきっかけに、独特の“世界”を生きている。彼女たちは一見、社会に溶け込みながら普通の大学生活や就職活動を送っているように見えるが、実際には生者の世界の人々と交わることができない。しかも大人に成長しているようでいて、その成長すらも“あの世的”な目線から見ると不思議な状態なのだ。
三人の暮らしぶりがなんとも明るいのに、その内側には大きな哀しみが潜んでいる。観客は彼女たちの「本当はこうだったらよかったのに」という願いを否応なく察してしまうだろう。彼女たちが住む家は、外から見ると荒れ果てた空き家同然らしいが、三人の視点では清潔感ある部屋に家具がそろい、楽しげな生活空間が広がっている。ここにすでに、彼女たちが物理的には現実に干渉できていないことの暗示がある。何かを買うときにお金を払う描写もなければ、周囲の人々と普通に会話しているふしもない。それでも三人が朝起きて、学校やバイト(のつもり)に通い、帰ってきて晩ご飯を食べる光景が描かれる。こうした日常シーンは実に可愛らしく、思わずこちらまでにこっとしてしまうが、それゆえに切なさが増幅するという仕組みだ。
そもそも三人がなぜそうなってしまったのか。劇中では12年前の悲惨な殺人事件が背景にあると語られる。しかし本作が普通のサスペンスや社会派ドラマと一線を画しているのは、加害者を完全な悪として断罪するストーリーにはなっていない点だ。もちろん、観ている側からすれば「こんな理不尽な行為を許していいのか?」という気持ちになる。けれども三人は、あるとき加害者の少年(現在は青年)とその周辺に接近し、たとえ声が届かずとも行動をともにする。母親の復讐心や、加害者の中にうずまく不可解な感情も垣間見えるが、当の三人は相手の表情すらまともに見つめ合えない。それでも、見えない壁越しに何とかして届きたい、問いかけたい、その一心で必死に走る姿が痛々しくも愛おしい。
さらに巧妙なのは、彼女たちが「もしかしたら自分たちでも生き返れるかもしれない」と淡い期待を抱く展開だ。ラジオから流れる不可思議な声、量子力学や素粒子の話が持ち上がり、いかにもファンタジックな希望が漂いはじめる。しかし、その希望はどうも確たる根拠に乏しい。彼女たちが認識するいくつかの“サイン”は、現実世界からすればただの偶然だったり、無関係な出来事かもしれない。そのあたりの曖昧さが本作を特別な作品に押し上げているのだろう。要するに、完全に断定しようとするとどこかで辻褄が合わなくなるよう仕掛けられている。この絶妙な“ずれ”が、登場人物も観客も「もしかしたら……」と期待する余白につながり、同時に「やはり無理かもしれない」という諦念にも通じている。
この物語の大きな山場は、三人が事件の加害者と母親の対峙の場面に立ち会うところだ。母親は娘の命を奪われた悲しみにとらわれ、感情をぶつけるが、相手はまるで空っぽの人形のように見える。その後、予期せぬアクシデントで加害者は車にひかれるが、これだって結局は“偶然”という形で片付いてしまう。まるで「行き場のない怒りや悲しみは、奇跡的な介入によって晴れるわけではない」という冷厳なメッセージのようでもある。三人も走り寄って助けようと呼びかけるが、生者にはその声は届かない。こうした場面を通して、本作がなまはんかな“感動もの”に回収されない骨太さを感じさせられた。
ただ、それでも「生きている人が少しだけでも前を向けたら」という温かな視線が隅々に感じられるのは、脚本・坂元裕二の真骨頂だ。美咲がこっそり想いを寄せていた青年(横浜流星)が再びピアノを弾く気持ちになれたことなど、多少なりとも前向きな変化が描かれる点は救いになっている。死んでしまった側には何の救済もないように思えてしまうが、そこにも「あなたたちがこの世に生きた証はきっと消えない」という温もりが込められているように感じた。
しかも三人は「灯台で飛べば元の世界に戻れる」と信じ、早朝の光の中でトライする。けれども当然ながら何も起こらない。正直、観ながら「やっぱりダメか」と落胆する一方、それならそれでいいのだとも思った。なぜなら彼女たちは日々を楽しくやり過ごし、ときには失望しながらも、ともに笑い合うかけがえのない時間を得ているからだ。そこであらためてタイトルの意味に気づく。「片思い世界」とは、まさに“届かない愛情”の比喩にとどまらず、“誰かを想う力は決して無駄にならない”というメッセージでもあるように感じる。三人の姿が説得力を持って伝えていたのは、見返りを求めなくても思い続けることにこそ価値がある、という普遍的なテーマではないだろうか。
広瀬すず、杉咲花、清原果耶の三人が寄り添いながら暮らす様子は軽妙で、何気ない会話だけでも心が弾むような楽しさがある。と同時に、突然ふとしたときに挟まれる「なんで私たちはこうなっちゃったんだろうね」というつぶやきが観る者の胸を締めつける。キャストの演技力や存在感があってこそ成り立つ描写だと思う。彼女たちのリアルな呼吸がスクリーン越しに伝わり、作り物ではない強度を帯びるからこそ、この悲しくも明るい設定に説得力が宿る。
脚本の構成はかなり挑戦的だが、監督・土井裕泰の演出がその危ういバランスを支えている印象を受けた。笑う場面と悲しい場面を行き来しつつ、あまりにも苛酷な真相を直視させる。かといって視聴者に完全な絶望を残すわけでもなく、ほんの小さな光を残してくれる。その匙加減が何とも絶妙なのだ。この手の作品は下手をすると筋が破綻したり、変に説明的な箇所が増えたりしがちだが、本作は最後まで独特の余白を保ちつつ走り切った。そこに監督の手腕が光っていると思う。
何よりも大きいのは、本作で描かれる死者と生者の境界が悲劇一色では終わらないところだ。物語上、三人は確かに戻ってこられない世界にいる。けれども死んだからこそ逆説的に「生きることってやっぱり素晴らしいんじゃないか」と感じさせてくれる。観る側としては「ああ、自分も誰かへの想いを大事にしよう」とか、「いつか大切な人があちら側へ行ってしまっても、きっとどこかで見守ってくれるのかもしれない」と思える。決して押しつけがましくなく、ただ希望の芽が息づいているという演出が、この映画をより深いものにしているのではないだろうか。
ラスト近く、合唱団で子供たちが歌うシーンでは、三人も並んで歌っている。実際には生きている子供たちからすれば三人は見えない存在なのかもしれないが、画面のこちら側では確かに同じスペースに立っている。その空気感こそが、死後の彼女たちが生きる“もうひとつの世界”を見せてくれる大切な鍵になっていると思う。こうして見ると、あまり大きな奇跡が起きないところもむしろリアルだ。そもそも理不尽な事件に巻き込まれたままの事実は変わらない。加害者がどう反省しようと、あるいは反省しなかろうと、失われた命は戻らない。それでも三人は前を向いて生き続ける(?)のだ。そう思うと胸の奥がキュッと締めつけられつつも、こころのどこかに温かさが宿る。
多くのことを考えさせられる作品だったが、あえてまとめるなら以下のような点に尽きると思う。
- 死んだ人々と生きている人々の世界が並行して描かれることで、人を想う尊さが逆説的に浮かび上がる。
- 加害者への怒りや復讐心、母の喪失感など重いテーマがある一方、三人の暮らしには不思議な明るさと温かさがある。
- “灯台から飛べば戻れる”と信じる彼女たちの姿は、一見儚いが、実は強い意志の象徴でもある。
- 事件の理不尽さは最後まで晴れないが、それでも自分にできることを探り続ける三人の姿がしみじみ胸を打つ。
結局、片思いのままであっても、誰かを想う気持ちに意味はある、という真理を本作は説いているのではないか。わずかでも過去の幸せを思い返し、いまここにいない人を想う行為は、残された側の生きる力にもなる。あるいは“そちら側”にいる人たちにとっても、心を保つ術になっているのかもしれない。
こうした重層的な意味合いをぎゅっと詰め込んだ「片思い世界」は、観終わったあとも、しばらく心の内側で息づいていて、ふとした瞬間に思い出す。きっとあなたも誰かを思い出すはずだ。そのときの切なさとほのかな温もりが、本作を素晴らしい体験へと導いてくれるのではないかと感じた。
映画「片思い世界」はこんな人にオススメ!
ここからは、自分の感覚をもとに、この作品をどんなタイプの人におすすめしたいかを書いてみる。かなり個人的な見解だが、参考にしてもらえれば幸いだ。
まず、いわゆる派手な展開や大がかりな仕掛けを期待する人よりは、余韻や感情の微妙な機微を味わいたい人向きだと思う。特に人生の中で大切な人を失った経験がある人や、「あのとき、もっと素直になれたらよかった」と後悔したことのある人には刺さるはずだ。劇中でも「もしあのとき、もう少しだけ声をかけていれば」という空気が漂っており、その後悔や懐かしさといった感情は誰の胸にも潜んでいるのではないだろうか。
また、坂元裕二の脚本が好きな人なら絶対に観るべきだ。日常会話に潜む詩的なセリフ回しや、ほんの少しの皮肉っぽさ、そして人物同士がどうにも噛み合わないのにどこかで通じ合っている妙な空気感など、“らしさ”が満載だ。前向きなメッセージを押し出しつつも、甘すぎない。そのバランス感覚が合う人にはしっくり来るだろうし、ひたすら涙を流すよりも、「なるほど、そう来たか」としみじみ味わえるところが魅力になっている。
さらに、“もうひとつの世界”をファンタジーとして楽しみたい人にも向いている。幽霊という設定ながら、彼女たちは笑って食事をしたり、ケンカもする。その様子を眺めていると、どうしても「本当に存在するかもしれない」と思えてくる。その軽やかさと切なさの組み合わせが好きな人なら、きっと心を奪われるに違いない。
反対に、明快な説明や完全なカタルシスを求める人には少しモヤモヤするかもしれない。加害者がなぜそうなったのか、なぜ彼女たちがこうして存在を続けていられるのかなど、すっきりとした理屈を提示しないからだ。ただ、“そういうもの”と受け止めれば、その先にある独特の感動を味わうことができるだろう。些細な日常の幸福感が好きな人、そしてじんわりくる心模様に惹かれる人にこそ、この映画はおすすめだ。
まとめ
本作は、広瀬すず・杉咲花・清原果耶の三人が一緒に暮らす姿だけ見れば穏やかで楽しげなのに、その背景にはどうしようもない運命の残酷さがある。だが、観終わってみると不思議と前向きな気持ちになれた。人と人とが通じ合うことの難しさや、そもそも生と死の境界を越えることの不可能性など重たい題材を扱っているのに、どこかで「それでも明日は来るし、私たちは私たちなりに生きていくんだ」という強さを見せてくれるからだと思う。
観客の側も「なんでこんな理不尽なことが起こるんだろう」と腹立たしく思う一方で、彼女たちが笑顔で過ごす日常を見ていると、ただ哀れむだけでは済ませられない感情が沸き起こる。人を想う行為に意味があるのかどうか、一見、答えが出ないようでも、やはり「想わずにはいられない」という事実そのものが尊いのではないだろうか。そうした気づきを与えてくれる映画である。
ふと「あの人は、いまどうしているだろう」とか、「もし自分が明日突然消えてしまったら、あの人はどんな顔をするんだろう」なんてことを考えたりする。その想像こそ、私たちの生きる証なのだと、本作を観ていると感じられる。恋愛映画ともホラーとも言い切れない不思議な魅力があるのに、妙に説得力がある。複雑な余韻が好きな人なら、きっとたまらないだろう。