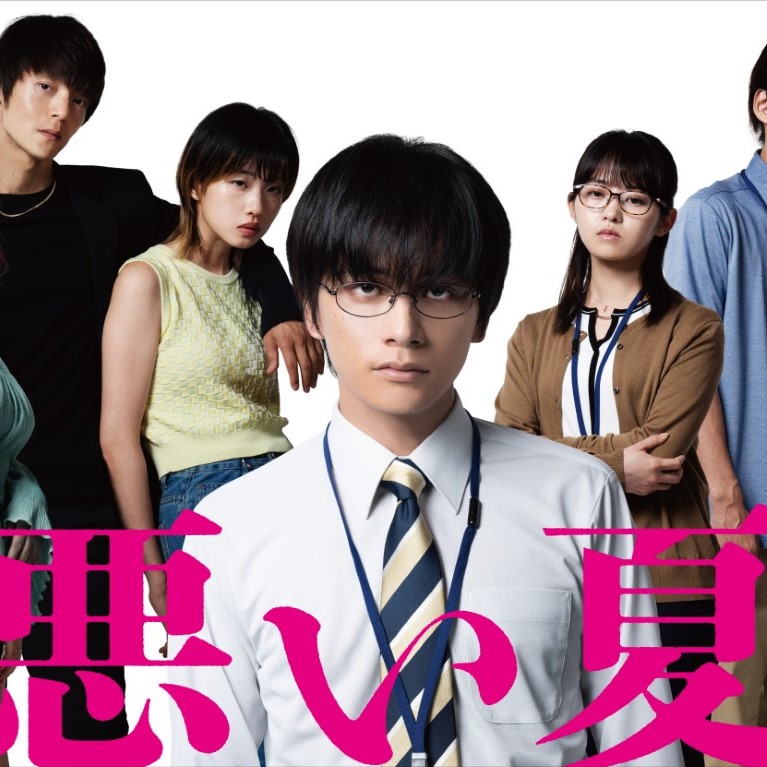映画「スオミの話をしよう」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
個性的な登場人物たちが繰り広げる騒ぎが見どころの本作は、結婚と離婚を繰り返す女性・スオミをめぐり、五人の夫たちが右往左往するという少々風変わりなストーリーである。詩人や警官、動画配信者など多彩な夫たちのやりとりが、笑いと皮肉を織り交ぜながらテンポ良く展開される。長澤まさみ演じるスオミがどんな人物か、表面上の姿と真意がどう異なるかを追っていくと、一筋縄ではいかない人間模様が浮かび上がる。大人も子どもも立場や思惑によって相手をどう見るかが変わるのが面白いところだ。さらに、ちょっとした仕掛けやサプライズも仕込まれているため、最後まで気が抜けない。まさに、笑いと驚きが同居した作品といえよう。
今回は、本編を鑑賞済みの人が思わず語りたくなるような内容を余すところなく語り尽くしていく。果たしてスオミの誘拐事件の行方はどうなるのか、フィンランドとの意外なつながりは何を示唆しているのか。そんな気になる部分を交えながら、ポイントを深堀りしていこうと思う。
映画「スオミの話をしよう」の個人的評価
評価: ★★☆☆☆
映画「スオミの話をしよう」の感想・レビュー(ネタバレあり)
本作は、五人の夫を持つ女性・スオミが突如行方不明になるという騒動から幕を開ける。現夫である寒川しずおは名の知れた詩人だが、いざ妻が消えたとなっても警察沙汰にしたくないなどと妙に世間体を気にするあたりが面白い。一方で、スオミの元夫たちも次々と姿を現し、それぞれが「自分こそが本当にスオミを理解している」とばかりに鼻息を荒くするため、屋敷内は一種の混沌状態と化す。
そもそもスオミは、見る人によって全く異なるイメージを抱かせる謎多き人物である。料理が得意だと言う者もいれば、まったくダメだという者もいる。中には彼女は外国語しか話せないと思い込んでいた元夫までいて、いったいどれが真実なのか分からなくなるのが本作の妙だ。こうしたズレが生むおかしさも見どころの一つである。
話が進むにつれ、実はスオミが相手によって態度や能力を使い分け、まるでカメレオンのように振る舞っていたことが判明する。なぜそんなことをするのかといえば、それぞれの夫たちが自分の理想像をスオミに押し付けているからだ。彼女はその窮屈な状況の中で、己を偽る術を身につけてしまったのだろう。相手の要望に応えることで短期的には平穏を得られたかもしれないが、そこには本当の自分というものが見えにくくなる危うさが潜んでいる。
そんなスオミの行方不明事件だが、ストーリー中盤で「誘拐犯」を名乗る者から電話が入り、一気にサスペンス色が強まる。要求額は3億円というとてつもない金額で、詩人でありながら守銭奴と化している寒川は渋々払おうとするが、いかにもケチくさい態度を拭えない。しかも、誘拐犯との受け渡しにはセスナ機が必要など、現実離れした手口が提示されるため、その時点で「いったい誰がこんな大掛かりな計画を?」と観客は首をかしげるに違いない。
さらに五人の夫たちは、いかに自分がスオミにとって一番の存在であるかを誇示しようとして騒動に拍車をかける。ああでもないこうでもないと自己アピール合戦を繰り広げる様子は、事態が深刻なはずなのにどこか滑稽であり、「男らしさとは何か」を問いかける風刺のようでもある。いざというときに力を発揮するのが男の美学、という古い発想が空回りし、結果的にスオミの安否よりも自分のプライドを優先してしまうから厄介だ。
だが、肝心の誘拐劇は実のところスオミ自身が仕組んだものだと明かされる。彼女は幼なじみの薊と手を組み、さらには寒川家の使用人である乙骨を巻き込んで、まるで大がかりな芝居を打っていたのである。ここで驚くのは、それまでスオミを支配してきたつもりの夫たちが、実際にはスオミの手のひらで転がされていたという逆転構図である。本作は、支配する者と支配される者の関係が根底から覆される瞬間をコミカルに描き出している。
スオミは幼少期から母親の再婚相手に合わせて性格を変えてきたという過去を抱えており、常に周囲の求める「理想の女性像」を演じ続ける習慣が染みついていた。彼女が一度は五人の夫に振り回されているように見えながら、最終的にすべてを手玉に取る展開は、彼女自身のしたたかさと自由への欲求を象徴しているといえよう。人は誰しも他者のイメージに合わせて自分を偽ってしまう瞬間があるが、スオミはそれを徹底的に行うことで限界を迎え、今回の誘拐騒動に至ったとも考えられる。
男たちのほうも悪いところばかりではない。各々がスオミを本気で好きだった部分があるし、ときには優しさも見せる。ただ問題は、皆が「自分の望む女性像」にこだわっていたことだ。夫たちの言動を笑いつつ眺めていると、「もしかして自分も誰かを型にはめようとしていないだろうか?」と考えさせられる。そうした客観的視点を持ちながら鑑賞すると、本作がただのコメディで終わらない理由がよりクリアになるはずだ。
クライマックスでは、スオミがフィンランドへ高飛びしようとしていた事実、そして彼女の名前「スオミ」が「フィンランド」を意味する言葉だったというエピソードが大きな意味を持っている。自由を求める象徴としてのフィンランドは、ジェンダーギャップ指数が高い国としても知られ、日本の男性優位社会との対比が作品の根底にあるのだろう。その背景を踏まえると、誘拐劇の真相と合わせて本作が描くテーマはなかなか奥深い。
結末で、スオミは夫たちへの感謝(と少々のあきれ)を込めて彼らの前から去るが、何やら新たな相手に照準を定めたかのようなそぶりを見せる。彼女はこれからも他人の望む女性像を演じ続けるのか、それとも真に自立した道を見いだすのか。観客としてはその先行きが気になるところだが、そこに明確な答えは用意されない。すっきり完結しないからこそ、観終わったあとにいろいろな想像が膨らむのだろう。
本作は可笑しみの中に辛辣な社会批評を織り交ぜた一作となっている。誘拐という深刻な題材を扱いながらも、夫たちの張り合いによって場面がコミカルに盛り上がるため、観る側は浮き沈みの激しいドラマを飽きずに追いかけられる。俳優陣の演技力も見どころで、それぞれのキャラクターが抱える“こじらせ”具合が絶妙な形で噛み合っているのがポイントだ。
物語終盤で披露されるミュージカル仕立ての場面も、本作を語るうえで外せない。夫たちが舞台さながらに、自分が見てきたスオミの姿を歌い上げるシーンは、誇張された演出ながらもどこかしみじみとした情感を誘う。スオミという女性が彼らの人生に与えたインパクトの大きさを、笑いとともにしっかりと感じ取ることができる。
また、最初の夫である魚山から、動画配信者の十勝、警官の草野、さらには寒川しずおに至るまで、それぞれがまったく違ったスオミ像を持っている点も興味深い。性格や趣味、得意分野までもが食い違うほどにバラバラなのは、スオミが常に相手に合わせて行動していた証拠だろう。人によっては「そんなに器用に自分を変えられるのか」と半ばあきれてしまうかもしれないが、そこに本作の面白みが詰まっているのは確かである。
要するに、「スオミの話をしよう」は、軽妙な会話劇と奇想天外なプロットで楽しませつつ、観る者に人間関係や社会的役割についての問いをひそかに投げかける作品だ。終盤のどたばたが収束したあとに残る余韻は想像以上に重く、「自分らしく生きる」とは一体どういうことなのかをじわりと考えさせられる。笑いとともに、心の奥に静かな問題意識を呼び起こしてくれる点こそ、本作の最大の魅力ではないだろうか。
映画「スオミの話をしよう」はこんな人にオススメ!
人間ドラマの奥深さを笑いながら味わいたい人にはピッタリである。たとえば、人間関係において「自分が本当に相手を理解している」と思い込んでいる人、あるいは「相手に無理に合わせすぎて疲れている」という人なら、本作を観れば思わず身につまされる部分があるだろう。社会風刺がこっそり盛り込まれた騒動劇が好きな人にも刺さるはずだ。男同士の張り合いが笑えると同時に、男性優位社会の矛盾を浮き彫りにする描写も見逃せない。
さらに、長澤まさみが一人何役もの顔を見せる演技に注目したいファンにもおすすめである。相手次第で印象がガラリと変わる姿は、女優の表現力を堪能するうえで絶好の機会といえよう。各夫のリアクションも多彩で、それぞれのキャラクターが抱える“こじらせ”具合を笑いに変えてくれる。結婚や離婚、家族のかたちに興味がある人も、本作を通して「他人と暮らす」ことの複雑さと面白みを改めて感じるのではないか。仕事や人間関係でちょっと息苦しさを覚えている人や、先の読めない展開を楽しみたい人には、存分に刺激を与えてくれる作品だと思う。
加えて、男女問わず「自分らしく生きる」とはどういうことかを考えたい人にとっても有意義な内容である。主人公の奔放ぶりを笑いとともに見つめていると、いつの間にか自分自身の生き方に照らし合わせて考えたくなる瞬間が訪れるから不思議だ。息苦しい日常を少しでも吹き飛ばしたい、または新しい刺激が欲しいと思っているなら、ぜひこの作品に触れてみてほしい。
まとめ
「スオミの話をしよう」は、五人の元夫と一人の女性が巻き起こす大騒動を軸にしながら、実は社会の歪みや人間の本音を鋭く突きつける作品である。誰もが少なからず抱えている“他者からの期待に応える”という行為の息苦しさを、思い切り笑いの形で表現している点が見事だ。
表面上はコメディらしい軽やかさに満ちているが、見終わったあとには「自分自身が本当に求めるものは何か」を問われるような感覚が残る。そこにこそ本作の大きな価値があるといえよう。結婚や家族、そして“自分らしさ”に悩むすべての人へ、ある種のエールを送る作品である。