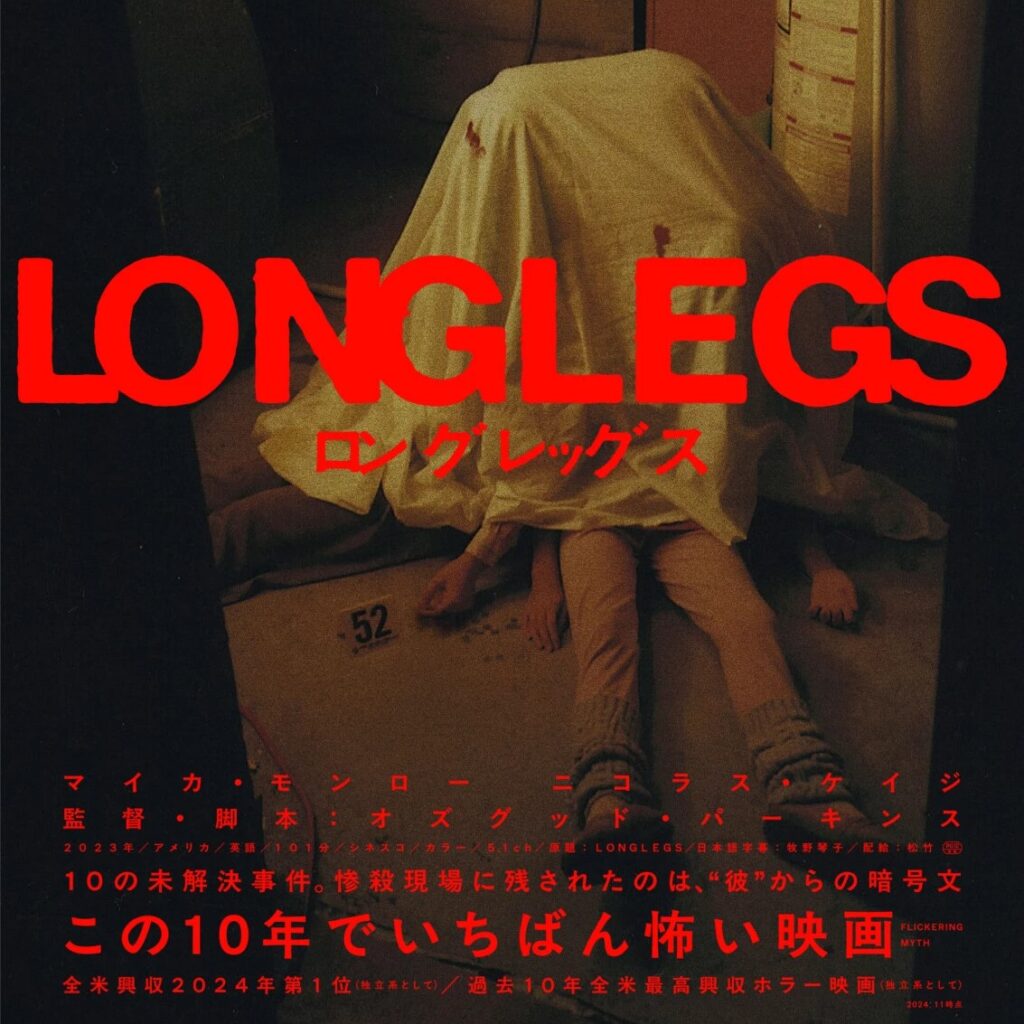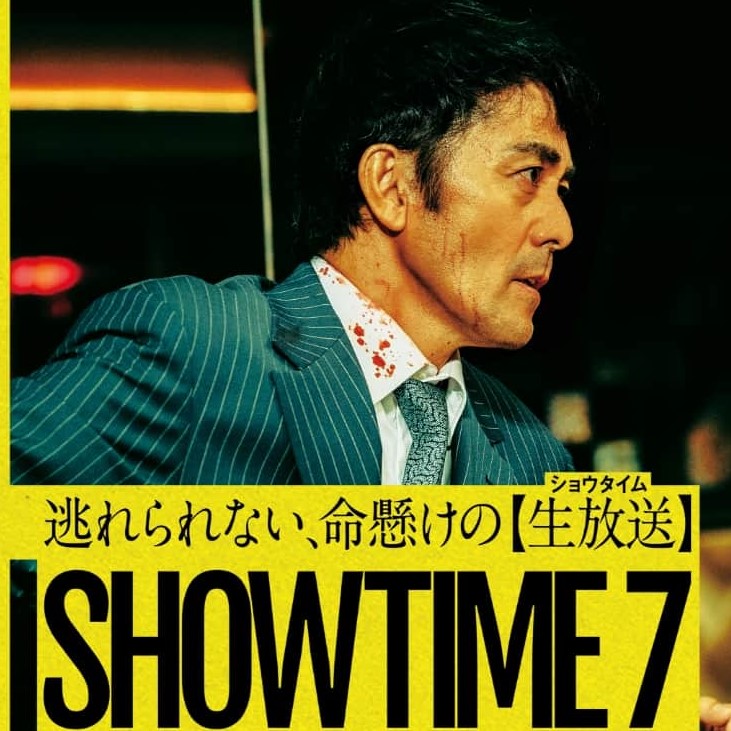映画「近畿地方のある場所について」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!
ネット発の超人気ホラー小説がついに実写化。監督は、あの白石晃士である。この報を聞いたとき、Jホラー好きなら誰もが確信したはずだ。「この監督以外にあり得ない」と。原作者の背筋氏自身が白石作品の熱烈なファンであり、その恐怖を自ら再現しようとして生まれたのが原作小説だというのだから、これはもう運命である。
本作は単なる映画化ではない。白石晃士というジャンルそのものが、自らの影響下に生まれた傑作と邂逅する、いわば究極の「白石祭」なのだ。本稿では、その混沌とした魅力と、観る者の正気を揺さぶる禁断の領域に、一切の忖度なく踏み込んでいく。
映画「近畿地方のある場所について」の個人的評価
評価: ★★★★☆
映画「近畿地方のある場所について」の感想・レビュー(ネタバレあり)
断片が恐怖を紡ぐ――モキュメンタリー手法の極致
本作の序盤から中盤にかけては、まさに白石晃士監督の真骨頂が炸裂している。物語は、失踪したオカルト雑誌の編集者が遺した大量の取材資料を、同僚の小沢(赤楚衛二)とオカルトライターの千紘(菅野美穂)が読み解いていく形で進行する。観客が目にするのは、林間学校で起きた「集団ヒステリー事件」の記録映像、心霊スポットに凸撃した「動画配信者の狂乱」、ベランダで異様な動きを繰り返す「赤い服の女」、そして「未解決の幼女失踪事件」といった、おぞましい断片の数々だ。
これらの映像は、わざと画質を落としたビデオテープの質感や、不快なノイズ、唐突なカットといった演出によって、まるで本物の呪われた記録を覗き見しているかのような生々しい恐怖を叩きつけてくる。これは、雑誌記事やネットの書き込みといった様々な媒体の断片から読者が恐怖を構築していく原作小説の構造を、映像というメディアで完璧に再翻訳する試みだ。バラバラだった事件が「近畿地方のある場所」という一点に収斂していく過程は、知的好奇心と恐怖心を同時に煽る極上のミステリーであり、白石監督の代表作『ノロイ』を彷彿とさせる見事な構成力である。この手法は単なる様式美ではない。原作の魂をスクリーンに宿らせるための、唯一無二の正解だったのだ。
深淵を覗く者たち――菅野美穂の怪演と赤楚衛二の役割
この混沌とした物語世界に、圧倒的な説得力を与えているのが主演二人の演技だ。特に、オカルトライター・瀬野千紘を演じた菅野美穂の存在感は凄まじい。彼女が演じる千紘は、ただ恐怖に怯えるヒロインではない。次々と襲い来る超常現象に対し、恐怖を感じながらも「なんなんだよ!」と激昂し、理不尽に立ち向かっていく。その姿は、まさに白石作品に登場するタフな主人公そのものだ。この「オカルトにブチ切れる菅野美穂」という構図は、本作の大きな魅力の一つであり、彼女の持つ気迫が、映画の後半で繰り広げられる常識外れの展開に観客を引きずり込む強力な推進力となっている。彼女の力強い存在がなければ、あの衝撃的なクライマックスは単なる悪ふざけに見えてしまったかもしれない。
対する赤楚衛二が演じる編集者・小沢悠生は、観客の視点を代弁する重要な役割を担う。最初は仕事として冷静に関わっていた彼が、底知れぬ謎に魅入られ、次第に常軌を逸していく様は、我々観客がこの禁断の領域に足を踏み入れていく過程そのものだ。オカルトのプロである千紘と、巻き込まれ型の小沢。この対照的な二人がバディとして謎を追うことで、物語は緊張感を保ったまま深淵へと突き進んでいくのである。
「ある場所」の正体――近畿の禁忌と宇宙的恐怖(完全ネタバレ)
さて、本作の核心、「ある場所」の正体について触れよう。数々の怪異が示すその場所は、単なる心霊スポットではなかった。そこは、「やしろさま」あるいは「ましらさま」と呼ばれる、人知を超えた存在が根を張る領域だったのである。
映画の終盤で明かされる真相は、Jホラーの枠を遥かに超えた宇宙的恐怖(コズミック・ホラー)の領域に達している。この「やしろさま」の正体は、地球外から飛来し、この土地で繁殖を試みる寄生生物のような存在だ。その繁殖方法とは、人間の女性を依り代とすること。作中で頻出する「黒い石」は、その生命の源か、あるいは卵のような役割を果たすものとして描かれる。
「赤い服の女」と息子「了」の怪異も、この文脈で理解するとその悲劇性が際立つ。彼女は亡くした我が子を蘇らせたいという母親の強い情念を「やしろさま」に利用され、人々を山に誘い込むための装置へと変えられてしまったのだ。本作の恐怖の根源は、死んだ子供を蘇らせたいという、母性の最も純粋で強力な願いが、異次元の存在によって歪められ、悪用される点にある。これは単なる侵略物語ではない。愛という人間的な感情が、人ならざるものの論理によって汚染されていく、極めて悪質な悲劇なのだ。作中で示唆される「ニギハヤヒ」や「天磐船(あまのいわふね)」といった日本神話のモチーフも、この「天から飛来した神(=異形の存在)」という物語に深みを与えている。
賛否両論の終盤――炸裂する、愛すべき「白石節」
そして、本作で最も語るべきであり、評価が真っ二つに割れるであろう衝撃のクライマックス。それまで積み上げてきたモキュメンタリーの静かな恐怖は突如として崩壊し、物語は物理的な肉弾戦を伴う壮絶なクリーチャー・ホラーへと変貌を遂げる。原作ファンや、静謐な恐怖を期待した観客からは「最後は触手モノか」「やりすぎだ」といった悲鳴が聞こえてきそうだ。
だが、断言しよう。これこそが本作の到達点であり、白石晃士監督がこの映画で本当にやりたかったことなのだ。この荒唐無稽で、暴力的で、サービス精神旺盛なクライマックスは、監督のライフワーク『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!』シリーズで培われた「白石節」の集大成である。映画は、原作小説へのリスペクトに満ちた丁寧なアダプテーションという皮を脱ぎ捨て、最終的に「白石晃士の映画」として完全に覚醒する。この変貌を以下の表で整理したい。
| 特徴 | 原作 (背筋著) | 映画 (白石晃士監督) |
| 物語の構造 | 雑誌記事やネット投稿などの断片的な資料を読者が能動的に繋ぎ合わせる。 | 発見された記録映像を登場人物が受動的に鑑賞し、謎を解き明かす。 |
| 恐怖の質 | じわじわと染み渡る知的な恐怖。乾いた文章の連なりから生まれる不気味さ。 | 序盤は雰囲気重視の心霊的恐怖。終盤は物理的で直接的な肉体の恐怖。 |
| 脅威の正体 | 輪郭のぼやけた、場所や概念に宿る呪いのような存在。 | 「やしろさま」という明確な個体を持つ、触手を有する地球外生命体。 |
| クライマックス | 全ての点が線で繋がり、恐ろしい全体像が判明する静かな絶望。 | 主人公と怪異との直接対決。血と体液が飛び散る壮絶なアクション。 |
この表が示す通り、映画は原作の「静」の恐怖を、映像ならではの「動」の恐怖へと大胆に変換した。この選択は、原作の雰囲気を愛する層にとっては裏切りに映るかもしれない。しかし、白石晃士という作家のフィルモグラフィを追いかけてきた者にとって、これほど胸が躍る展開はない。本作の評価が満点の星5つではなく4つなのは、このあまりにも過激で観る者を選ぶ結末ゆえだ。だが、その潔さと狂気こそが、本作を忘れられない一本にしているのである。
映画「近畿地方のある場所について」はこんな人にオススメ!
本作は万人に勧められる作品ではない。だが、特定の層には生涯忘れられない体験を約束するだろう。
まず絶対に観るべきは、「白石晃士監督の信者」である。『ノロイ』のじっとりとした恐怖から、『コワすぎ!』の何でもありなエンターテインメントまで、彼の作品の振れ幅を愛せる人間なら、本作は間違いなく「全部乗せ」のご馳走だ。
次に、「モキュメンタリーという手法が好き」な者。序盤から中盤にかけての、フェイクドキュメンタリーとしての完成度は極めて高い。本物と見紛うほどの質感と、そこから立ち上る得体の知れない恐怖を存分に味わえるはずだ。
そして、「理屈を超えた恐怖を浴びたい」者。予定調واの展開や、お決まりの恐怖演出に飽き飽きしているのなら、本作の予測不能な物語と常識外れの結末は最高の刺激になるだろう。
逆に、『リング』や『呪怨』のような伝統的なJホラーの静かな恐怖を求める人や、原作の雰囲気を完璧に再現してほしいと願う原理主義的なファンには、本作のクライマックスは厳しいかもしれない。これは、監督の放つ強烈な電波を受信できるかどうかが問われる、踏み絵のような作品なのだ。
まとめ
映画「近畿地方のある場所について」は、傑作であり、怪作である。序盤は原作への深い敬意を感じさせる極上のモキュメンタリーとして観る者の心を掴み、終盤ではそのすべてを破壊して監督自身の狂気を解き放つ。この構造自体が、作り手の仕掛けた最大の罠と言えるだろう。
賛否両論を巻き起こすであろうあの結末は、確かに本作を万人受けする傑作の座からは遠ざけたかもしれない。しかし、その危険な賭けに打って出た監督の覚悟、超常現象に本気でキレる菅野美穂の怪演、そしてJホラーの枠を破壊するほどのエネルギー。そのすべてが混ざり合った本作は、間違いなく2025年最大の問題作であり、ジャンル映画ファンにとって必見の一本だ。これは、激辛だが、やみつきになる味である。